

体感していない出来事の記憶
2022.10.13
- 古川日出男
昨2021年10月の村上春樹ライブラリー開館とともに、この国際文学館アネックスサイトで「村上春樹文学に出会う」と題するエッセイの連載を始め、さまざまな形で村上文学と関わってきた方々に、村上作品との“出会い”や“絆”について語っていただいています。開館一周年を記念して、本年10月は、連続して掲載したいと思います。
一周年記念の第一回には、作家の古川日出男先生にご寄稿をいただきました。
私が最初に読んだ古川先生の作品は『中国行きのスロウ・ボートRMX』(メディアファクトリー)です。ご存じの方も多いかと思いますが、それは村上春樹の名作を当時の若手作家たちがトリビュートした小説シリーズの一作です。「僕」の成長の物語であり、村上作品の「僕」を想起させながらも、それとはまた異なる感動がありました。誰かに語っているような文体から読んでいるうちに、つい声を出して読みあげたくなる衝動を覚え、非常に印象的で、その後古川先生のファンになりました。
2021年村上春樹ライブラリーの開館にあたって、古川先生に世界文学に関連する本を五冊推薦していただきました(本エッセイ末尾もご参照ください)が、その中には私の愛読書が四冊も入っており、より親近感を覚えました。その後、古川先生にエッセイを依頼したら、すぐご快諾いただきました。
それでは、古川先生の村上春樹読書体験を一緒に見ていきましょう!
監修:権 慧(早稲田大学国際文学館)
体感していない出来事の記憶
古川 日出男
小説を書いていると、いつも自分の記憶と不思議な向き合い方をする。これはまさに村上春樹さんも言っていることだけれども、エンディングが「どうなるか」を明確にわかって書いている作家ばかりが世にいるわけではない(のだと思う)。わからないでも、正しい軌道に乗せて執筆する、ということがわたしたちにはできる。「いま、筆をすすめている方角は、誤ってはいないのだ」と確信できれば、そのまま先へ先へ、そして物語の幕切れまで書きつづけられる、ということだ。
そういう執筆に没頭しているさなかに、わたしは、どうも記憶を掘っているような体感を覚えるのだ。
まだ書かれていない物語が、すでに無意識の底の底のほうにあって、そうした最下部まで降りてしまえ、そこで失ってしまった記憶を取りもどせ、と言われているような……。
失ってしまったお前の記憶を、と。
お前の、この物語のための記憶を、と。
でも本当のことを言ったら、そんなものは記憶ではないのだ。それなのに、わたし(や、ある種の傾向を具えた作家たち)は自分の魂のボトムにそっと眠っている〈記憶〉をコンコンとノックする。あるいは掘削機でガリガリと掘る。
同じように不思議なことをもう一点。わたしには再読して、三読四読した本というのが、何十冊か存在する。そういうのを愛読書と言うのだろうと思うけれども、たとえば村上春樹の小説も、幾つかのタイトルはそうした本になっている。ちょっと想像してほしい。たとえば十代のおしまいに読み、二十代の半ばに読み、三十代の後半に、四十代の前半に、それから五十代も半ばになって再び手にとった小説、のページをひもといた瞬間に、どんな感覚に見舞われるか?
第一に、「あれっ? 忘れてしまっている」だ。
前に読んだストーリーなのに、展開が思い出せない……。
第二に、「あっ、既視感がある」だ。
この主人公が彷徨した街なみの、この描写は、そうだ、ちゃんと憶えている。おれ自身が二十代で(あるいは三十代で)さまよったのと同様に……。
第三に、「違う、これは自分のストーリーではない」だ。
そんな街に、おれは、あたしは、ぼくは、行ったことはないのだった、とふと気づいて、愕然とする。この小説の〈物語〉こそが、まるで自分の体験のように、記憶の核(あるいは隅、あるいは底)に収められている……。
主人公が決定的に自分と異なる場合は、その記憶の錯誤は、ほとんど前世の体験のようだ。わたしは男性で、これは肉体的にも精神的にもそうなのだけれども、村上春樹の短篇「眠り」には初読時から強烈な印象を受けていて、この短篇というのは女性の一人称で描かれている。この女性は〈眠れない人〉である。彼女は十七日間も不眠状態にある。じつは、彼女は、〈眠れない人〉であるのと同時に〈眠らない人〉でもある。
そうした経緯が、また彼女の内面が、一人称体験として語られる。
すると、わたしはこの女性の一人称の小説を、どうしても自らの記憶には変換できないわけだけれども、あまりにも生々しい〈体験〉として記憶の核(なり隅なり底なり)に残っているので、まるで前世ではこのような、歯科医の妻だったような気がして、ふとした折に、「おれの夫が歯医者さんだった時、おれは眠らなかったから、恐い体験をしたんだなあ」と想い起こしたりして、そんな事実はないんだと数瞬後に悟って、愕然とする。
それでも怖ろしいことを経験はしたのだ。たとえば、金縛りという目に遭ったのだ。それは村上春樹の短篇「眠り」の内側での出来事で、けれどもこの短篇を私は、四度は、八度は、……たぶん九度は読み返している。そのたびにこの短篇はわたしの記憶であるような〈演技〉が上手になって、あたかも古い日記をひもといているような感覚をわたしに覚えさせて、けれどもわたしはそんな日記は持っていないのだから、それは前世の日記帳だ。
どういう恐い体験だっけ?
第一に、悪夢を見たんだった……。
第二に、目覚めたのに、体を動かせなかったんだった……。
第三に、足もとに見たことのない老人がいることを、はっきり「見て」しまったのだった……。
第四に、その老人が水差しから水を注いでいる。おれにだ。
あたしにだ。
わたしにだ。
こうやって「おれに」だの「あたしに」だの「わたしに」だのと自称を連打して、それが語り手の〈性〉を越えたりパーソナリティの越境に直結したりしているのが日本語なのだけれども、村上春樹文学というのはしばしば翻訳されて、そこからは「おれに」感や「あたしに」感や「わたしに」感は奪われて読まれている、というのはどういうことなのだろう? 奪われるとの表現はきついかもしれない。しかし、日本語の一人称単数には雑多な厚みがある。その〈雑味〉が漂白されることが、基本的には「翻訳にかけられる」ということなのかもしれない。こうした問題を考えはじめると、村上春樹文学における翻訳というのは「オリジナルの言語から何かを引き、たぶん、翻訳さきの言語に何かを足している」からこそ、きちんと読まれているはずだ、といちおうの結論が出る。
いま、わたしは引き算と足し算の話をしたのだ。
これは小説における算数である。
物語における算術だ。
たとえば、さっきわたしは「眠り」における金縛り現象を解説した。そうした現象が、どのように村上春樹の短篇「眠り」内で描出されていたか、をザッと説いた。だが、わたしは、金縛りという霊的現象(これは日本国内の文脈では心霊的な体験である)が果たして海外でも同じような現象と認識されているのか、ただの肉体的な症例として捉えられているのか、判断がつかない。仮に後者だとすると、日本語以外の言語に置き換えられた時、そこからは〈心霊的〉である部分は引き算されて、このエピソードは極めて〈象徴的〉なものなのだとの感触が足し算される。
それも、極めてダイナミックにだ。
イコールで結ばれる霊的現象が存在していない言語圏・文化圏の読者が、この引き算と足し算の果てに、式のイコール(等号の「=」)の右側に見出すのは?
水差しというシンボルだ。
老人という幻想だ。
随意な運動がいっさい許されていない、という身体の状態が表わす、ある種の〈権力〉状態だ。あなたは権力をふるわれる側にいる……。
このように〈心霊的〉なエピソードなり物語なりは、象徴的な物語に、幻想小説に、それどころか政治小説に変容して、やはりあなたに襲いかかる。化け物のように。
このダイナミックな怪物。
それを翻訳というのだ。
それを記憶というのだ。読者のあなたが金縛りに遭っていたり、金縛りではない幻想的な「何か」に襲われていたり、悪夢がえんえん(現実世界の方向にまで)延長していたり、そうした内実はどんなフォルムを採っていてもよい、しかしながらあなた=読者がそれを「自らの体験」のごとくに憶えてしまったら、記憶してしまっているのだとしたら、ほら、すでに同語反復は登場したのだけれども、それを記憶というのだ。
そして記憶というのは、過去にあると思いがちだけれども、未来にもある。
あとから獲得される記憶がある。未来に至ってから「あっ、これは知っていた……」と愕然としながら認識しなおす類いの事柄が。村上春樹の長篇『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』を、わたしはこの五十数年の生涯で幾度か通読しなおしているが、この作品の「世界の終り」パートに登場する主人公が〈古い夢〉を読むためにナイフで眼球を刺されて(そのナイフの刃さきは火で焼かれている)、結果、その両眼に傷を持ち、このことを一種の〈ライセンス〉として〈古い夢〉を読めるようになる。けれども日の光は避けなければ日常は営めない。不用意に光を浴びると報いを受ける。
報いというのは、涙を流しつづけるような羽目に陥るのだ。
苦痛とともに。
つまり「世界の終り」パートの主人公は、〈涙の流れる眼〉を持った人物である。
そして一九九五年の三月に東京で、地下鉄サリン事件が起きて、その被害者の方々が「あっ、自分の体には異変が……」と最初に気づかれたのは、その兆候は、眼が刺激されている、視界がやられている、というそのありさまだった。
その猛毒ガスは、サリンは、人間の目には見えない。
人間の目には見えないのだけれども、人間の眼を射る。刺激する。
そして被害者の方々は、涙を流しつづけるような羽目に陥ったのだ。
みな、〈涙の流れる眼〉を持った人物へと変じたのだ。
村上春樹の『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』はその出来事の十年も前に刊行されていて、そこには地下鉄サリン事件が〈象徴的〉に描かれていて、それがシンボルであったと自覚するのは、読者が何事かを悟るのは、きっと地下鉄サリン事件から何年も、何十年も経ってからの〈未来〉だ。
発見された時に初めて確認できる〈記憶〉というものは、つまり、過去には存在していない。
あなたという読者の記憶は、あるいはわたしという読者の記憶は、未来にあった。
そうした体験自体は幻想的で、もしかしたら半ば〈心霊的〉でもあって、しかし大切なのは、そこにダイナミズムが内包されているということ。
あなたには記憶があり、あなたが本を読めば、記憶はもっと、ダイナミックな<本当の姿>をあらわにする。本物の機能を。そうしたことを、わたしは村上春樹の文学に教えられている。
2022年10月1日

プロフィール
古川日出男:1966年福島県生まれ。1998年のデビュー以来、掌篇から巨篇まで様々なタイプの小説を書き続けながら戯曲や評論、ノンフィクションにも取り組む。また朗読活動を中心に他分野の表現者との共演・共作の機会も多い。2003年に発表した村上春樹トリビュート作品『中国行きのスロウ・ボートRMX』は現在英語とイタリア語でも出版されている。最新作は2022年3月に刊行した長篇小説『曼陀羅華X』。
公式WEBサイト「古川日出男のむかしとミライ」
https://furukawahideo.com
*「現在から未来に繋ぎたい世界文学作品」での古川日出男先生の選書
ガブリエル・ガルシア=マルケス、『百年の孤独』
ミラン・クンデラ、『不滅』
フォークナー、『八月の光』
閻連科、『愉楽』
スティーヴ・エリクソン、『黒い時計の旅』
(詳細は弊館階段本棚データベースをご参照ください。
https://www.waseda.jp/culture/wihl/exihibitions/collection)
Related
-

“Letters from the Haruki Murakami Library”―アンドリー・セティアワン(Andry Setiawan)
2026.01.08
-

“Letters from the Haruki Murakami Library”―レベッカ・ブラウン(Rebecca Brown)
2025.12.02
-

“Letters from the Haruki Murakami Library”―カミラ・グルドーヴァ(Camilla Grudova)
2025.10.20
-
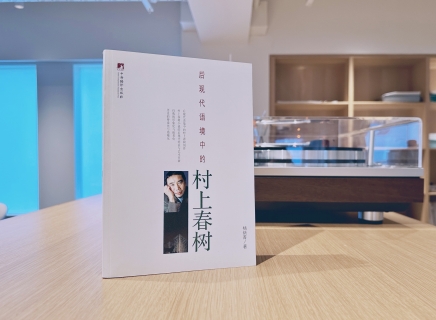
村上春樹文学とわたし
2023.11.30
- 楊炳菁
-
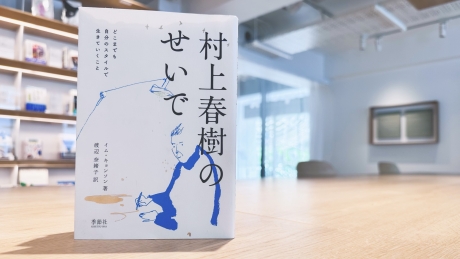
まるで空気のように
2023.07.26
- イム キョンソン
-
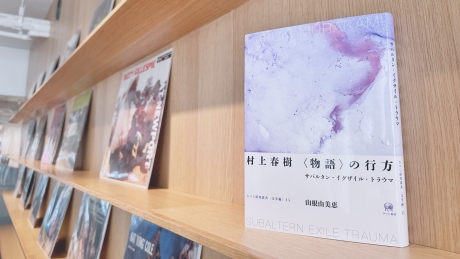
重なり合うドラマ/「森」の行方
2023.05.02
- 山根由美恵
