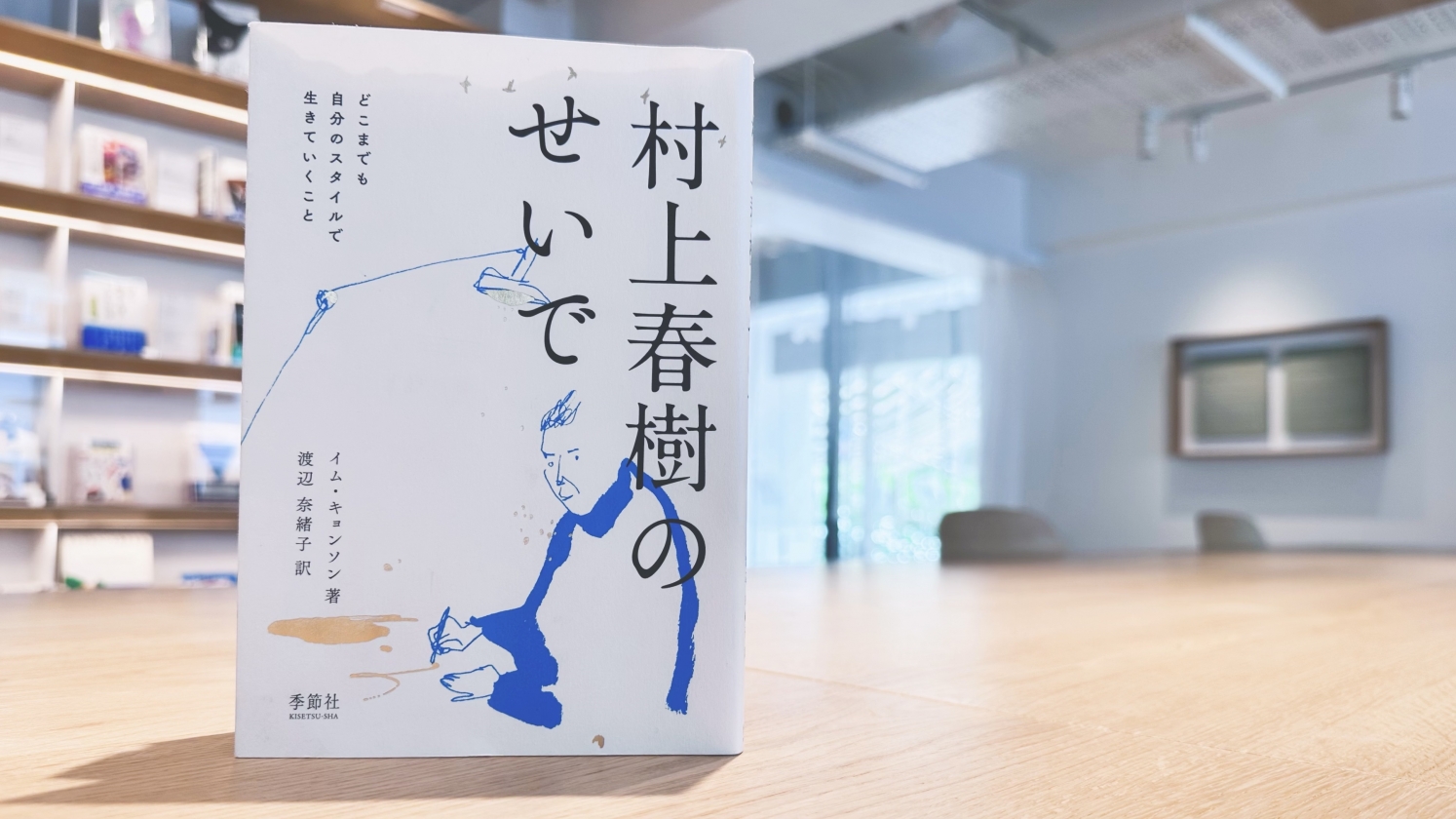
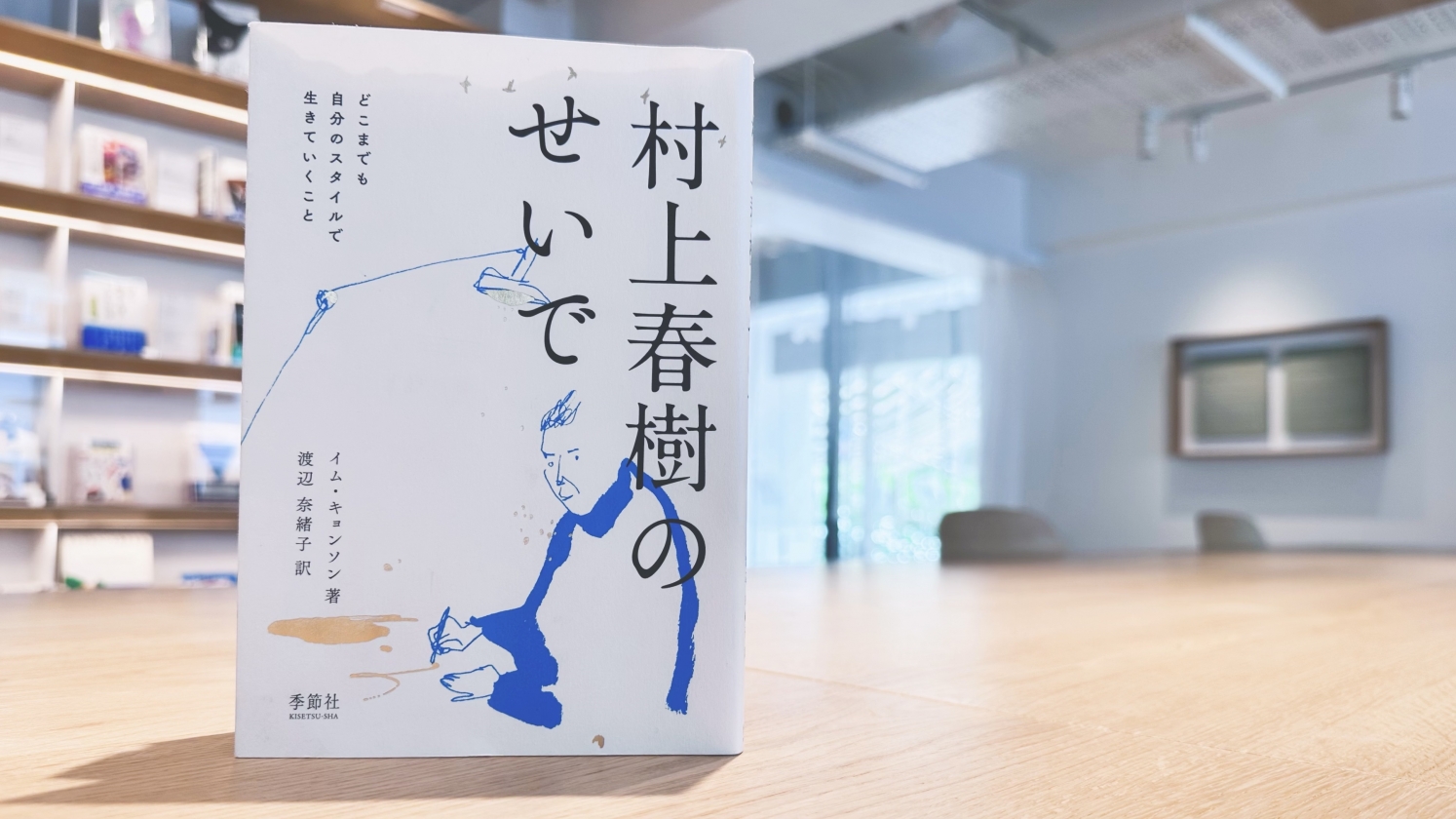
まるで空気のように
2023.07.26
- イム キョンソン
「村上春樹文学に出会う」シリーズ、2023年度第2号には韓国の作家・エッセイストのイム キョンソン先生よりご寄稿をいただきました。
エッセイ集『村上春樹のせいで』をお書きになったイム先生に、初めてお目にかかった時にふと思い出したのが「一見如故」という言葉でした。初対面なのに、ずっと昔からの知り合いだったような気がして、少なくとも私はその化学反応を感じました。イム先生の周りには穏やかな空気が流れていて、話し方から人との接し方まですべてがまっすぐで、誠実で、そのうえでユーモアのセンスもすごく、当時の最新作『ホテルストーリズ』をプレゼントされたので読んでみたら、一気に物語の世界にハマりました。ホテルの利用者や従業員が一つ一つの短編小説に登場しており、それがまさに映画のシーンのように目前に浮かんできて、頁を捲る手がとまらなかったです。近いうちに日本語訳が出版されると良いですね。
いただいたエッセイにも触れられている「打ち合わせ」は、今年5月19日に村上春樹ライブラリーで行われた公開セミナーのためのものでした。開始時間よりずいぶん前から来られた方も少なくありませんでしたが、会場を埋めた聴衆は、「韓国での村上春樹、個人への村上春樹」と題したイム先生のお話に笑い、頷き、一緒に考えようとしました。講演後にはサインを求める参加者が長蛇の列を並び、急遽予定にはなかったミニサイン会を開催することとなり、サインや記念写真を求めるファンに終始笑顔で親切に対応してくださるイム先生の魅力も改めて感じました。エッセイ集のサブタイトルにもある「どこまでも自分のスタイルで生きていくこと」、まさにその魅力が、著作からも、ご本人からも伝わってきて、日韓どちらにも多くのファンがいるのがとてもよくわかりました。
では、イム先生ご自身にとっての村上春樹はどのような作家か、村上作品をどのように読んできたか、一緒に見てみましょう!
監修:権 慧(早稲田大学国際文学館)
まるで空気のように
イム キョンソン
しばしば「イムさんが書いた本は全部読んでますよ」とサイン会などで嬉しそうに声をかけていただくことがある。そう言われるともちろんありがたいけれど、反面大変恥ずかしくもあった。しかし今では、その読者の方々の気持ちが、本物だということが理解できる。
3年半ぶりの東京だった。2月8日、早稲田大学は入試期間中のため閉館日にあたっていたが、打ち合わせで入館し、村上春樹ライブラリーをじっくりと見学することができた。隈研吾のリノベーションや、グランドピアノなどの作家にゆかりの物、書斎の再現や村上春樹の好きなジャズが流れるオーディオルームなど、長年の読者としては目を輝かせっぱなしだったが、心の中では村上春樹の全作が置いてあったギャラリーラウンジばかりを気にしていた。それなりの村上本コレクターであった私ですら手に入れることの出来なかった希少本(たとえば『波の絵、波の話』)をそこで発見して心拍数が上がった。
ああ、見物はもう良い。いち早く長テーブルの椅子に座って読み残した本たちを読み尽くしたい。自分の素直な心の働きを見つめながら、作家のファンが心の底で一番望むことは、その作家が書いたものを一文字も残さず貪り読むこと、ただそれだけであることを知った。それ以外のものは実は付録に過ぎない。
村上春樹さん本人がふらっといきなりラウンジに現れたりしたとしても、「ちょっと勘弁してください。今は早くこれを読みたいのであっちに行ってもらってもいいですか」と顔をしかめて言うかもしれない。何よりも作家の本が一番読みたい、という気持ちに自然になれてよかったと思う。そして作家は結局「本」を残す人だという当たり前のことをありありと感じた。
Old Habits Die Hard. 無理もない。大阪で在日朝鮮人学校に通っていた15歳の頃、『ノルウェイの森』を初めて読んで以来、30年間にわたり一人の作家を地道に読んできた。誰かの本をこんなに長いあいだ夢中になって読み続けた事があっただろうか。多分無い。人々はある作家をさまざまな理由で好きになる。作品が面白かったからとか、あるいはインタビューなどでの発言やライフスタイル、もしくは横顔の写真が気に入ったからかもしれない。私が村上春樹を作家として好きになったのは、彼が作り上げた物語の中で自分が理解されたいように理解されていると感じたからだ。
5歳の時に韓国を離れ、17歳になるまで自分の意思とは関係なくいろんな国を梯子しながら成長した。そのため私の中には「転校生」のメンタリティーが深く刻まれている。「主流」から外れ、「境界」から内側を眺めていて、「何を考えているかわからない」と言われがちな子だった。みんなはどうでも良さそうなものに自分だけが敏感になって、「それはちょっとちがうでしょう」という気持ちにもなった。それは時として私をすごく孤独にさせるものでもあった。だが、彼の小説を読んでいると「その問題について考えることはきっと大丈夫」と思えてきた。孤独なままでいてもさっぱりと生きていける、と。
そして時は流れ、私はどういうわけか韓国で作家になっていた。子供の頃から本を読むのは大好きだった。というより、2〜3年に一度は転校生にならざるを得ないということは、初めの頃は友達が出来ず本ばかり相手にしなくてはならないということだった。だけど自分が将来本を書く人になるなんて考えたこともなかった。大学では政治学を専攻し、卒業後は平凡な会社員生活を12年間送った。その間もずっと本を手放す事はなかったが、それでも自分が何かを書きたいなんて思ったりはしなかった。読者でいるだけで十分ハッピーであったのだ。
きっかけは人生のちょっとした不運がもたらしてくれた。二十歳の時からしつこく再発を繰り返したある病気のため私は35歳でとうとう会社を辞めるしかなかった。代わりに人と接することなく家で出来る「書く仕事」を始めた。最初は雑誌のコラムから書き始め、あれよあれよといううちにエッセイや小説に領域を広げていった。もちろん途中で会社に戻ろうともした。それが「いや、一応これだけ書いてから」と引き延ばしているうちに、いつの間にか本を20冊書いていた。
個人的不運がもたらした作家業のこうした裏事情を知らない人々はたいていこういうことを言う。「やはりお好きな作家、村上春樹さんの影響で作家になったのですね」と。
私は少し考え込む。まあ、好きなのは確かなわけだけど。私を作家にさせたのは村上さんではなく病気であって(あとでわかったことだが、ちゃんとした作家業をこなすには会社員以上に体力が必要だった)、私に作家業を続けさせたのが村上さんであった。『職業としての小説家』で彼はこう語っている。
「リングに上るのは簡単でも、そこに長く留まり続けるのは簡単ではありません。(…)それでも書きたい、書かずにはいられない、という人が小説を書きます。そしてまた、小説を書き続けます。そういう人を僕はもちろん一人の作家として、心を開いて歓迎します。リングにようこそ(p.15〜p.27)」
歓迎すら必要なかった。彼の存在自体が役割を果たした。よりによって一番好きな同時代の作家がワーカーホリック。あまりにも誠実に作品活動を続けているため、ファンの私も気を休めることができない。書くことを止められない。国際文学館の壁に描かれた村上春樹著作年譜を眺めていたら、「確かにこれはこまめにアップデートするだけでもかなり面倒だろうな」という心配が湧いてくる。これは言い過ぎかもしれないが、村上春樹さんがもしも途中で引退などしていたら、多分私も会社に戻ったかもしれない。ありがたいが、時として勝手ながら恨んだりもする。
いや、でもやはり好きな作家は人生の役に立つ。原稿を書く途中、つまずいたら、私には三つの逃げ口がある。一つ、有酸素運動をして脳を動かす。二つ、ぐっすり寝て脳を休める。そして三つ、村上春樹さんの短編小説を読む。彼の短編小説が特に好きで160篇以上の短編小説の中から最も好きな20篇(例えば「ハナレイ・ベイ」「タイランド」「蜂蜜パイ」「独立器官」など)を、BGMを流すようにただただ繰り返し読むと、落ち着きを取り戻し、自分の居場所を再確認する。
信頼できる作家の作品は、一人の個人として人生を渡っていくすべも教えてくれる。生まれた以上、人は必ず予期せぬ苦しみに出会わざるをえない。それを静かに受け入れ、人のせいにせず、自分の規則を守りながら、限られた状況の中で自分が出来ることをする。その重要さを身に染みて知ることができた。昨年の9月、突然肺がんになって手術を受けた後、これからこの体で小説を書いていけるかずっと戸惑っていたが、国際文学館に掲げられた村上さんのメッセージ「息をするのと同じように」を読んで、自分のペースで呼吸を整えながらやっていけばいいんだと思うようになってきた。今は日々のランニングでリハビリしながら再び書く準備を整えている。
ぼちぼちと書いていたら、村上春樹さんは、まるで空気のように人生のいろんな場面で何かと作用し働きかけていた。そのせいか、自然な成り行きで村上春樹さんについてのエッセイを書き(2006年に村上さんの事務所を通じてフレンドリーな許可を得た時は本当に嬉しかった)、日本語訳も出た(恥ずかしい)。韓国の出版界では村上春樹オタクとしても知られるようになり、彼の新作が出た時や、ノーベル賞発表の時なんかはマスコミから何かと頼み事が多くなり結構迷惑なものだ。私は村上春樹の専門家なんかじゃない、ただの長年の読者である、と言いたいところだが、韓国の新聞なんかでよく「ハルキ」と呼び捨て表記してあるのを見かけたら、ムッとして抗議のメールなんかを書いている。それ以外はただひたすら好き勝手に作家の本を読むだけだけど。
とはいえ、サイン会や講演などで、たまにそのエッセイ『村上春樹のせいで』(韓国語で 『어디까지나 개인적인』)をスッと取り出す読者さんがいたらちょっとうれしくなる。サインをしながらじっと顔を見上げたり、こっちから握手なんかを求めたり、いきなり親切になる。だって、『村上春樹のせいで』はこれまで書いた本の中で一番売れなかった本なのだ(そしてこれはもちろん「村上春樹のせい」ではない)。その本にサインを求められるのは稀な経験だからこそ、その本を持ってきてくださる人たちが大切に思えてきて思わず微笑んでしまうのだ。でもたまに、「イムさんのおかげで村上春樹という作家を初めて知りましたよ! その作家さんの本も結構よかったですよ〜」と無邪気に話しかけて私をビビッとさせる方々もおられる。作家業って本当に大変ですね、村上さん。
プロフィール

イム キョンソン:小説家、エッセイスト。1972年生まれ。日本、アメリア、ポルトガル、ブラジルなどで成長期を過ごす。12年の会社員生活を経て、2005年からは韓国ソウルで小説やエッセイを書き続けている。代表作に、小説『ホテル物語』、『そっと呼ぶ名前』、『そばに残る人』、エッセイ集『自由でいること』、『態度に関して』、『村上春樹のせいで』などがある。
Related
-

“Letters from the Haruki Murakami Library”―アンドリー・セティアワン(Andry Setiawan)
2026.01.08
-

“Letters from the Haruki Murakami Library”―レベッカ・ブラウン(Rebecca Brown)
2025.12.02
-

“Letters from the Haruki Murakami Library”―カミラ・グルドーヴァ(Camilla Grudova)
2025.10.20
-
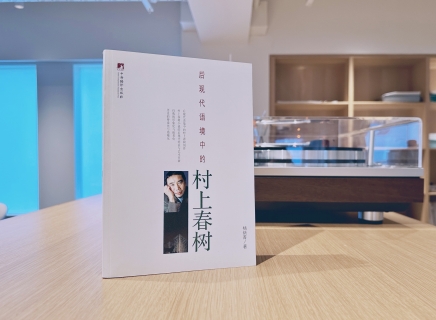
村上春樹文学とわたし
2023.11.30
- 楊炳菁
-
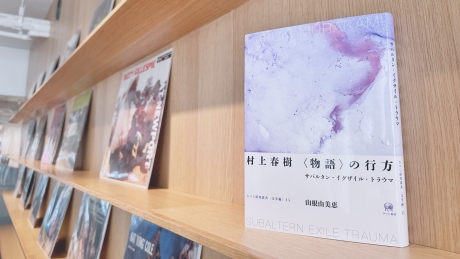
重なり合うドラマ/「森」の行方
2023.05.02
- 山根由美恵
-

村上春樹のマジックと私
2022.11.01
- アンナ・ツィマ
