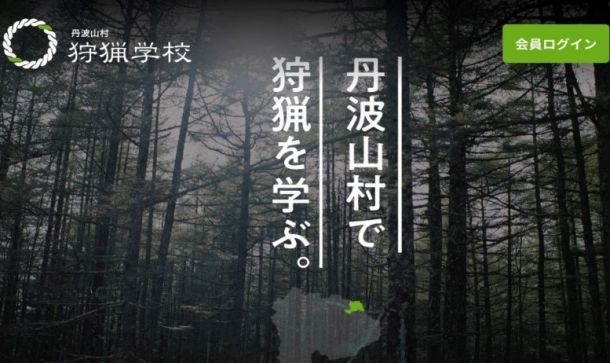実習科目「狩猟と地域おこしボランティア」の履修生による体験レポートです。自然豊かな山梨県丹波山村で、猟師さんや地域おこし起業家さんたちと出会い、履修生は何を感じ考えたのか?
ぜひお読みください!
【第5回】獣害を自分ごとにする話。
ー体験的学習科目「狩猟と地域おこしボランティア」2022ー
清水 遥人(社会科学部2年)
2022年11月27日、丹波山村に2回目の現地実習で訪れました。今回は電車とバスを利用しましたが、たくさんの登山客でバスはまるで都心のラッシュ時のような混み具合でした。もう少し本数を増やしてほしい…と思ってしまいました。それでは、早速レポートに移りたいと思います。

行きのバスから撮った写真
今回は到着早々「鹿が獲れたから解体する」と言われ、目の前で解体を見学させていただく運びになりました。解体を見学するのは初めてだったので、興味が湧く一方、少し怖さもありました。
いざ解体が始まると、そのような感情はすぐになくなって、前回も講義してくださった中澤さんの知識の豊富さと手際の良さに、ただただ感心するばかりでした。結局、何か考える間もなく、解体をショーとして見ているうちに終了していました。お昼に食べた鹿のメンチカツも、今回は売り切れる前に食べることができた鹿ばぁーがーも、鹿の解体を見た直後だったことも関係なく、ただただ美味しくいただいてしまいました。
1回目の時に、「解体を見た後なら食べ物の味も感じ方も変わる」と思っていたのは浅い考えだったようです。1回目と同様に、やはり自分自身で狩猟を経験してみないとわからない、やってみたい、と改めて思いました。

絶品の鹿ばぁーがー
さて、今回は狩猟の目的の一つでもある、獣害対策について触れたいと思います。現在、多くの農村がこの獣害に悩まされています。増えすぎた鳥獣は、農水省によると年間に150億円を超える農作物への被害を出すそうです。大谷翔平選手の2022年の年棒が43億円くらいなので、大谷選手三人分以上の作物が毎年被害を受けています。
また、農地だけでなく、木々の樹皮を食べたり森の植物を食べつくしたりと、生態系への影響も懸念されています。それを防ぐ手段の一つが、狩猟を行うことです。

柵に囲われた丹波山の畑
丹波山村では、写真のように畑一帯を頑丈な鉄柵で囲っています。それに加えて狩猟も継続的に行っており、被害はかなり抑えられているそうです。ですが、地域によっては狩猟の担い手がおらず、柵の整備も不十分で、収穫直前に農作物が全て食い荒らされてしまうこともあります。
僕たちは2回の実習で、大豆の収穫や脱穀などの農作業も体験させていただきましたが、ほんの少しやっただけでも非常に大変でした。それを1から99までやって、最後に全てが獣害で荒らされて無駄になってしまったとしたら…想像するだけでゾッとします。そんなことが実際に各地で起こっており、それにより農業をやめてしまう方も多いそうです。

脱穀作業をした大豆
農業に直接かかわっていなくても、僕たちは農業で作られたものを食べています。もし獣害がさらに深刻化し、農作物の価格が上昇したら、あるいは食べることすらできなくなったらどうなるでしょうか。「自分には関係ない」と切り離さず、起こっていることに目を向けたいと僕は思いました。
今回のレポートでは、狩猟や獣害対策の問題点や、中澤さんに伺った数々の興味深いお話などについては触れられませんでした。気になる方は、ぜひ丹波山村狩猟学校へ足を運んでください!
僕は二度の丹波山村狩猟学校で、沢山のことを学ばせていただきました。この授業は「狩猟と地域おこしボランティア」なので、本来ならば僕もなにか丹波山村を興すために貢献するべきだったのですが、ほとんど頂いてばかりの授業でした。すみません。
せめてこのレポートが、ほんの少しでも、丹波山村に足を運ぶ一助になれば幸いです。丹波山村の皆様、本当にありがとうございました。
体験的学習科目「狩猟と地域おこしボランティア」
2022年度連載一覧はこちら
【Instagram】https://www.instagram.com/waseda_tabayama/ 
【Twitter】 https://twitter.com/Waseda_Tabayama