連載 ワークライフバランス挑戦中! 第31回
「想定外」が「ふつう」だった子育て
文学学術院 教授 石田 光規

▲娘の最後の登園の見送り(子育てが一段落した瞬間でした)
私の子どもは第一子が9歳、第二子が7歳なので、さすがにもう育児期は通り過ぎている。51年も生きているので、子育て以外にもいろいろと経験してきたけれど、育児の記憶は今も鮮明に残っている。あまりに衝撃的だったので、一冊の本を出してしまったほどだ。そこで、この短い論考では、あらためてこれまでの研究を振り返り、子育てに対する目線のあり方について考えてみたい。
子育ての研究をしていて衝撃的だったのは、いわゆるアンケート型の社会調査から得られたイメージと、当事者が語る現状のギャップである。私は松戸市で2020年に出産した母親に、質問紙調査と聞き取り調査を行った。その結果が実に興味深かったので簡単に紹介したい。
質問紙調査では母親の幸福感や子どもを産んでよかったと思う頻度を尋ねた。その結果、幸福感については「ひじょうに幸せ」50%、「やや幸せ」48.6%、「あまり幸せでない」1.4%、「まったく幸せでない」0%、子どもを産んでよかったと思う頻度は「なんどもあった」95.9%、「ときどきあった」4.1%、「ごくまれにあった」と「まったくなかった」は0%であった。つまり、調査対象のほぼ全員が幸せと答えており(98.6%)、子どもを産んでよかったと思う瞬間が何度もあったと答えているのである(95.9%)。
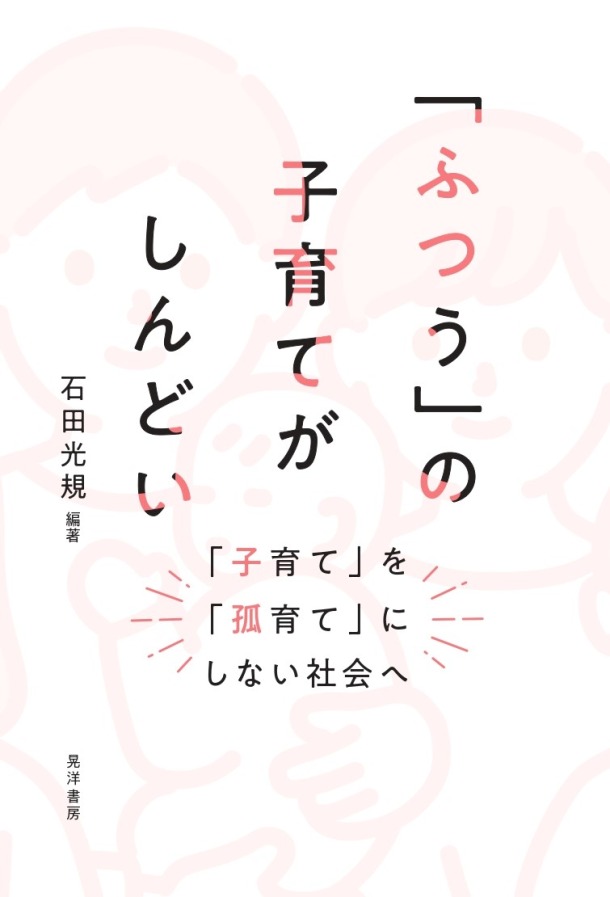
▲執筆・出版書籍「「ふつう」の子育てがしんどい」
これまでの研究生活でいろいろな社会調査を見てきたが、これほど多くの人が幸福を感じ、肯定的な意見を答える調査を見たことがない。しかも、この傾向は、松戸市の出生率の高い地区に住み、2020年に出産した母親全員に対して行った調査でも同様であった。つまり、サンプルの偏りによる影響ではなかったのである。この結果を受けて、それくらい子どもの誕生は幸せなことであり、母親にプラスの影響をもたらすものなのだと改めて感心していた。
しかし、質問紙調査の回答者に聞き取りを実施すると、統計で示された幸せのイメージは一変した。母親たちの語りから得られたのは子育ての幸せではなく、日々の子育てがいかに綱渡り的に維持されているかという、リアルな実情であった。日々の予定も立てられず、数分単位で変わる現実に慌ただしく対応する。しかも、発生する現象は今まで体験したことのないものばかり。混乱して途方に暮れているうちに、一日、一週間、一ヶ月と過ぎていく。そんな現実がため息とともに語られたのである。
たしかに僕もそうだった。日々「ままならない」現状に叫びそうになりながら対処し続けた。乳児をお風呂に入れるには、「入れる人」と「受け取る人」の二人が必要だ、など素朴な事実に気づいたのも子育てが始まってからである。とはいえ、当時アンケートで「今幸せか」と聞かれれば、「幸せ」と答えてしまうだろう。そこに私たちの見落としがちな子育ての「真実」がある。
子育ては日本に住む多くの人が経験するという意味では「ふつう」であり、また、子どもの誕生は未だ幸せなイメージで彩られている。それはそれで悪いことではない。やはり、子どもの誕生や子育ては幸せであってほしい。他方、「ふつう」の子育てをしているそれぞれの家庭の日常は、「想定外」の繰り返しで構成されている。つまり、「ふつう」と「想定外」が交錯するのが子育てなのだ。

そこで、「ふつう」に焦点を当てると、「ふつう」の人が当たり前にこなせるはずの子育てをできない自分を責めてしまったり、「ふつう」のことなのだから愚痴をこぼしてはいけないと不満を押さえ込んだりしてしまう。周りの人も、親が子育てをするのは「ふつう」なのだからしっかりして、と厳しい視線を注ぐようになる。
そうならないためにも、私たちは「想定外」の部分に目を向ける必要がある。いま「想定外」の事態にいるのだから、もっと周りを当てにしてよい。当事者も周りの人もそう考えられるようになれば、子育ての環境はもっとよくなるだろう。
早稲田大学文学学術院准教授を経て、2016年4月より同学術院教授。2010年第7回日本労働社会学会奨励賞を受賞。【「ふつう」の子育てがしんどい】の他、【「友だちがしんどい」がなくなる本】【「友だち」から自由になる】等、多くの書籍を執筆、出版。










