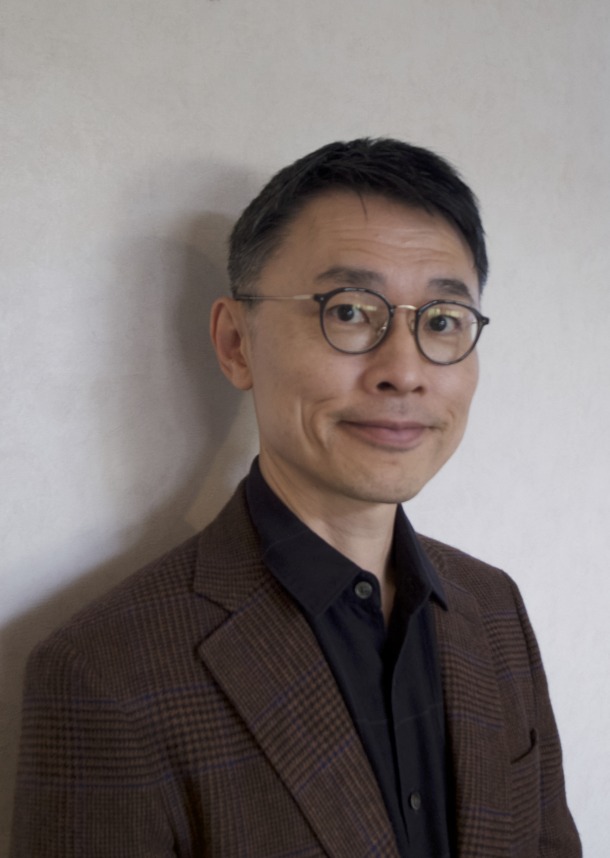2023年度開講科目早稲田大学ティーチングアワード
総長賞受賞
対象科目:アジアの宗教と政治(E)
受賞者:見市 建
「アジアの宗教と政治」は、東南アジアの宗教や政治を専門とする見市先生が担当する大学院生対象の授業である。修士課程の1年目の学生が多く受講し、研究の基礎を固める場ともなっている。授業では、東アジアから東南アジアの国家と宗教の関係を多角的に分析し、それを理論的に理解することを目的としている。毎週異なるテーマを設定し、国家と宗教の問題を掘り下げる。ナショナリズム、ジェンダー、民主主義、暴力といったテーマごとに、事前にビデオ講義を視聴し、指定された論文を読んだうえで、対面授業に臨むという形式で進められる。
この授業の特徴の一つは、幅広い理論的枠組みを用いながら、具体的な国ごとの事例を分析する点にある。各国の状況を比較しながら議論することで、学生は宗教と政治の関係の普遍的な構造や、それぞれの地域特有の特徴をより深く理解することができる。
この授業は、宗教そのものを専門としない学生にも開かれている。政治学を学ぶ学生にとっても、「宗教」という要素を加えることで、より包括的な視点から国家や社会を分析できるようになるという意図がある。「国家と宗教の関係を単に事例の羅列として見るのではなく、体系的な視点で理解することが重要です」と見市先生は述べる。
事前の講義ビデオ視聴と対面授業での議論による反転形式の授業
授業は、事前学習と授業内の議論で構成される。ビデオ講義(約60分)を授業の数日前に視聴し、関連論文を2~3本読んだ上で、短いレポートを提出する。このレポートの内容をもとに、対面授業では議論を展開する。
当初、学生に自由にディスカッション用の質問を考えさせていたが、学生それぞれが異なる視点から質問をするため、議論が拡散してしまうことがあった。そこで、現在は授業のテーマに即した問いを教員が提示し、学生はそれを意識しながら論文を読む形式に変更された。「議論の軸が定まり、論点が明確になったことで、より深い議論ができるようになりました」と見市先生は語る。
対面授業では、まず論文の内容を確認する時間が設けられる。特に、学生が読んだ論文の要点を整理し、議論の前提を共有することに重点を置く。その後、教員が提示した問いに基づいてディスカッションが行われるが、学生が活発に発言することで、しばしば想定外の方向へと議論が展開することもある。「学生が自分の国の事例を持ち出すと、話が盛り上がります。しかし、そのまま終わると何の議論だったのか分からなくなることもあるので、適宜軌道修正を行うようにしています」。
学生の既成概念に挑む議論
この授業には、日本や中国、東南アジア諸国の学生が多く参加しているが、年によっては南アジアや中東、ヨーロッパなどからの留学生も加わる。多国籍の学生が集まるため、議論は非常に多様な視点を含むものとなる。「学生は自国の状況を当然のものと考えがちですが、他国の事例と比較することで、新たな視点を得ることができます」と見市先生は語る。例えば、宗教と国家の関係についても、異なる宗教間の比較や地域を越えた比較、多国間の比較など、比較の組み合わせによって意外な発見があるという。
また、民族的・宗教的マイノリティの学生が議論に参加することも、授業の質を高める要因となっている。「(民族的・宗教的に)多数派の学生と少数派の学生では、国家と宗教の関係に対する認識が異なることが多いです。その違いが議論の中で明らかになることは、非常に興味深いです」。ただし、センシティブなテーマを扱うため、議論が緊張感を帯びることもある。見市先生は、「学生の既成概念に挑戦するような問いを投げかけることもありますが、それによって生じる緊張や反発は、むしろ学びの機会だと考えています」と述べる。自分の考えを見つめ直し、他者の視点を理解することこそが、この授業の醍醐味である。
学生の関心に合わせたテーマでの最終レポート
学期末には最終レポートの提出が求められる。この最終レポートは単なる学期末の課題ではなく、授業を通じた学びを集約する重要なプロセスとなっている。
レポートの内容は、学生の関心によって大きく異なる。ある年度には、日本や東アジアの宗教政策に興味を持つ学生が多く、国家の宗教統制や宗教的マイノリティの権利といったテーマが選ばれていた。異なる国の事例を比較しながら、理論的に考察することが求められるため、学生にとっては大きな挑戦となる。
最終レポートのテーマは学生自身が決定するが、途中で2回のフィードバックを受ける仕組みが導入されている。まず、3週目にプロポーザルを提出し、教員からのフィードバックを受ける。その後、最終週には途中経過の発表を行い、再度修正点を指摘される。「修士論文の練習として、論文の組み立て方や議論の展開を学んでほしいと考えています」と見市先生は言う。
この授業は、単に知識を得るだけでなく、理論と実証のバランスを取りながら思考を深める場として機能している。最終レポートは、その集大成であり、受講生にとっての重要な学びの機会となっている。