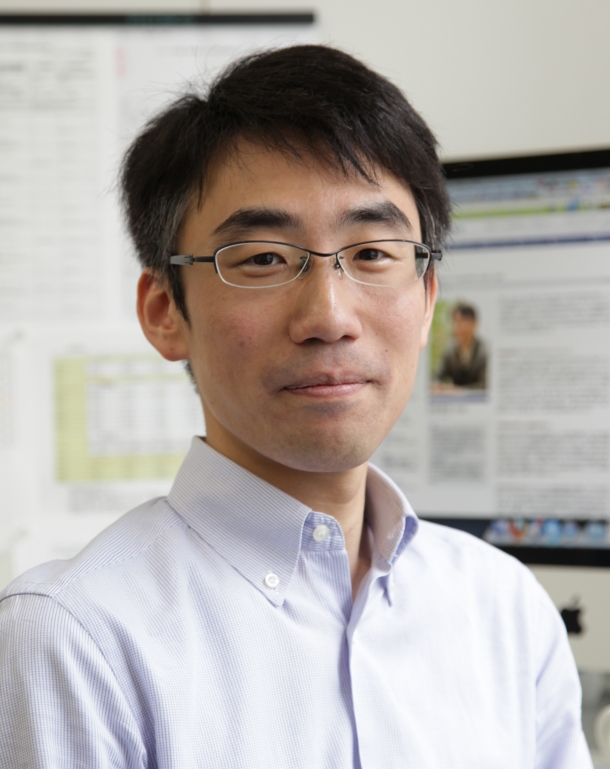2020年度春学期ティーチングアワード総長賞受賞
対象科目:基礎物理学A 総合機械(2)
受賞者:湯浅 一哉
湯浅一哉教授は「総合機械(2)」のクラスを受け持ち、総合機械工学科の1年生、
約80名に力学の基礎を講義している。スライド投影ではなく板書をしながら授業を行い、
学生には手書きのレポートを課すなど、伝統的な授業スタイルにこだわっている。
オンラインでの授業になっても、従来のやり方を維持できるように工夫を施し、
学生が基礎力を身につけられる授業を作り上げている。
板書ベースで進めながら、学生がノートを取る伝統的な授業スタイル。手を動かすことの意義を強調
「基礎物理学A」の授業を10年以上、担当している湯浅教授。長年、教員が説明をしながら板書をして、学生はそれをノートに取るという伝統的な授業スタイルを取っている。「手書きでノートを取ること」にこだわるのには理由がある。「自分で手を動かしていると、見える景色が確実に違うからです。ただ式を眺めていてもわからなかったことが、鉛筆を持って書き始めた途端に『あっ』とわかる。学生を見ていても、私自身にも、そのような体験が今までに何度もありました。書くことが思考、理解の助けになると確信しています」。
毎年最初の授業では、学生にノートを取ることの大切さを必ず伝えている。オンライン授業となった2020年度春学期も、オンデマンド配信の最初の授業動画で例年通りの内容を話したという。実際、春学期の最後には「先生の言う通りにノートを取ってよかった」という感想が複数から寄せられたそうだ。
コロナ禍で対面での授業ができなくなっても、湯浅教授はできる限り従来のやり方に近い授業ができるように工夫した。具体的には、黒板の代わりにタブレットを活用し、タブレットの画面に「板書」する方法を取った。また、授業をしている湯浅教授の顔も合わせて表示した。もちろん、「板書+音声」のみでも授業としては成立するが、学生には絶対に顔を見せたいと考えたそうだ。
「私が楽しく講義をする姿を見せることが、学生にもよい効果があると思ったからです。デスクトップ画面をそのまま収録できる『EverLec』というツールを使い、画面の中央に板書を、左下に私の顔が写るように配置して授業を行いました。先生や友達と顔を合わせる機会がないままに授業を受けることになった2020年度の新入生にとって、『先生の顔』が見えたことはうれしかったようです」
ちなみに、授業はオンデマンド配信を選択した。当初は、対面授業により近い感覚のリアルタイム配信を検討したというが、「好きな時間に見られる、繰り返し見られるなど、学生にメリットがあると考え、最終的にオンデマンド配信としました」。実際、よくわからなかったところに巻き戻して何度も見られるのがよかったという声が学生から届いたという。
毎回の手書きレポートは、自己添削後に再提出。振り返ることの重要性を伝える
手書きでのレポート提出を課しているのも、この授業の特徴の一つだ。レポートは提出して終わりではなく、対面授業の場合は、提出後の次の授業で解答を示しながら湯浅教授が解説。学生は、それを受けて自身のレポートを自己添削をした上で、再度提出する。A4用紙1枚程度の小さなレポートを10回実施するが、2回目の提出があるため合計で20回提出することになる。
「実は、この方法は過去に先輩の先生から教わったものです。学生には、自分で自分が書いたレポートを見て、振り返ったり反省したりする作業が重要だと伝えています。また、20回分の手書きレポートを見れば、一生懸命に取り組んでいるかどうかが一目瞭然になります」
オンデマンド授業でも、手書きレポートの提出は対面のときと同様に実施した。学生たちは、ノートなどに解答を書き、スマホ撮影やスキャンなど何らかの方法でそれをデジタル化して提出。提出期限後に、湯浅教授が解説を含めた解答例を載せたPDFファイルを学生に配布するという手順を取った。
また、Waseda Moodleのアナウンスメント機能を使い、学生に毎回レポートの感想も伝えたという。「レポートの文字を通じて、学生たちの一生懸命さがよく伝わって来たので、『皆さんの頑張りは伝わっていますよ』という励ましのメッセージを繰り返し送りました」。オンデマンド授業で直接話す機会がない中、こうした気遣いは新入生にとっても心強いものになったようだ。
新入生にとってはハードルが高かった「質問の共有」については、現在も試行錯誤中
さまざまな工夫によって、オンデマンド配信でも対面と同様の授業スタイルを実現している湯浅教授だが、現在も試行錯誤していることがある。それが、学生からの質問の受け付け方と回答の方法だ。2020年度の春学期は、質問のある学生はWaseda Moodleの「Message My Teacher」機能を使ってメッセージを送り、湯浅教授が1対1でその質問に答えていた。
「ただ、誰かの疑問は、他の人も疑問に思っていることが多い。春学期終了時の学生授業アンケートで『質問箱を作ってほしい』という要望も寄せられたので、秋学期は質問や回答をみんなで共有する仕組みを作りました」。しかし、1年生の場合は逆効果だったかもしれないと湯浅教授は語る。
「お互いをまだよく知らない1年生で、人数も多いため、全員から見られることは恥ずかしかったようです。上の学年では同様の方法がうまくいっている例もあるようですが、このクラスでは質問が減ってしまいました」。今は、学生から個別に寄せられた質問に対する回答を、質問者の名前は伏せた形で全受講生に共有する方法をとっているとのこと。
「基礎物理学A」という講義名に、「自分は別に物理学の専門家を目指しているわけではないから...」と考えがちな学生がいるように思われると湯浅教授。「物理学にとどまらず、理工系のあらゆる分野に必要で、理工学部生が当然知っているべき基礎的事項を学ぶ授業です、ということを繰り返し伝えています。学年が進み、学生たちがそれぞれの専門分野に挑む際にそれを思いきり楽しめるように、この基礎科目をしっかり履修してほしいと願っています」。学生を置き去りにしない丁寧な指導は、学生授業アンケートでも非常に高く評価された。