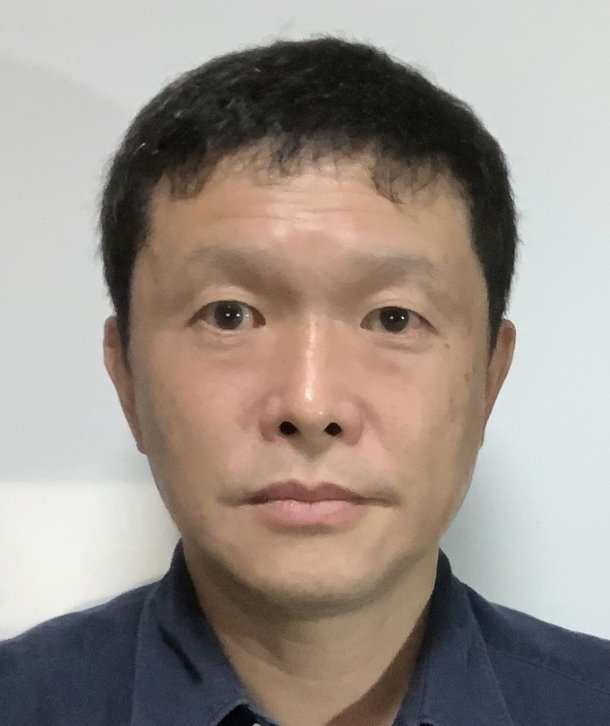2021年度春学期ティーチングアワード総長賞受賞
対象科目:数学C(ベクトル解析) 電生2
受賞者:米田 元
2018年度にも同じ授業で本賞を受賞している米田教授。2021年度春学期はフルオンデマンドで実施されたが、
10年以上続けている授業でもあり、ほぼ例年と同じように進められたと振り返る。
対面時と同様、「ゴールに向かういろいろなルートを用意し、各自がやるべきことを明確にする」という指導法は、
「着実に力をつけることができた」など、その有意義性が高く評価された。
普段の授業は動画+小テスト、試験はZOOMでリアルタイムに実施
オンデマンド授業は、10分程度の動画を視聴した後に5分ぐらい小テストに取り組むセットを、1回の授業で5回ほど繰り返すのが基本だ。動画の視聴履歴は取っていないが、毎回の小テスト提出が平常点となる。「小テストの問題は、動画の中に似たような例題やヒントを入れてあるので、動画を見ていればそれほど難しくはありません。点数で差別化するというよりは出席点のようなものですね。ちょっと工夫したのは、スライドだけ見て分かった気にならないよう、ヒントの部分はスライドには書かず、口頭で話すのみにしたことでしょうか」。
小テストは、学生が紙に書いたものをスマホで撮影しPDFで提出することとし、詳しい手順を解説したマニュアルも用意し提示しておいた。「勝手にやらせると、縦横が混在したり歪んでいたり、ひどいクオリティの画像ファイルをたくさん送ってきたりします。こちらの処理が大変になるので、マニュアルを作りました」。Moodleの設定上でも、送信できるファイルの拡張子や数を指定し、規定のもの以外は受け付けないようにした。
自動採点できるMoodleの小テスト機能を使わなかったのは、「ファイナルな答えだけ書く」状況を避けたかったからだ。「採点の手間はかかりますがTAの助けも借りて対応しました」。動画はいつ見ても良いが、課題は翌週の授業前日夜までの提出とする。「全部まとめてやろうとすると教育効果がないので、毎回期限を設定し溜め込まないようにしました」。
学期末の試験だけはリアルタイムに実施。学生はプリントアウトした試験用紙を机の上に置き、何も見ずに独力で問題を解く。その間、ZOOMでつないだカメラをオンにした状態とし、答案を書き込む様子が映るようにしておく。「遠隔でやる以上完璧な監視は無理ですが、履修生は41人で全員の映像を一画面で同時表示できる人数だったので、ギリギリなんとかなったかなと思います。一番抑止効果があったのは、『後から録画も確認する』と伝えておいたことかもしれません」。
単位の取り方も理解の仕方も、複数の選択肢から選べるようにする
米田教授が常に心がけているのは「ゴールに向かうルートを複数提示すること」だ。たとえば単位を取るには、期末試験重視と平常点重視のどちらでもよいとする。「前年度のテストを提示し、何点取ればよいのかも公表します。それを見て自力でなんとかなると思えば試験重視でいい。自信がない、説明を聞きたいと思う学生は、毎回の小テストをしっかり提出して積み上げていけばいい。どちらの道でも単位を取れるようにしました」。
複数の方法を用意するのは、授業での説明も同じだ。「ある定義を学ぶ場合、それをまるごと覚えなさいではなく、この例題を通して理解する方法もあるし、あるいはこういう考え方をしてもいいなど、いくつかの説明をします。そのなかで自分にとって一番しっくりくるもので理解すればいい。よく分からないものはスルーしていいよと話しています」。複数の説明を提示するのは、教員として授業を始めた頃から意識しているという。「たとえば図解的な説明と言葉による説明とどちらが分かりやすいか、物理的な面と数学的な面とどちらからのアプローチがいいのかなど、理解しやすい方法には個人差があるからです。それに、私自身もひとつのことを理解するのに、違う方向や方法で納得するほうがスッキリするように思うんですよね」。
大きな目標より、「これがわかれば、これができる」と実感させる
この授業は2年生を対象とした必修科目だが、1年生のときに学んだ内容をきちんと理解している学生とそうでない学生とが混在しているのが現実だ。どちらのレベルに合わせるかについては、「思いきり下の方にフォーカスしている」と言い切る。「実際は上の20%と下の5%を切って、その他の75%の学生にちょうどいいぐらいが一番効率的でしょうか。経験的に、少し下の層に向けると、結果的に全体の習熟度が上がるような感触があります」。
学生のモチベーションを上げるには、目の前の具体的なゴールを提示するのが効果的だともいう。「学問的な面白さを感じさせる話もしたいのですが、あまり高尚な話をしても学生はついてこないような気がしています」。それよりは、<この説明を聞くとこういう問題ができるようになる>、<この問題が解けるとこういう現象がわかるようになる>というような話の方が学生に受け入れられやすいと感じている。「<こういう経験値を積んでこのぐらい強くなれば、次の敵を倒せる>というような、いわばゲーム感覚でしょうか。極端な話、学生は<10分勉強したらこのぐらいのことがゲットできる>ぐらいの具体的な手応えがないと、なかなかやる気になりません。その尻を叩くため、目の前に人参をぶら下げてる形ですね」。
今回学生からの高い評価を受けたポイントを尋ねると、「笑顔で楽しそうに授業をする」という点を挙げた。「学生の顔が見えない分、カメラに向かって笑って話すのはむずかしかったですが、学生に<見てみよう>と思ってもらうため、そこはかなり意識して取り組みました。それも効果があったのかもしれませんね」。