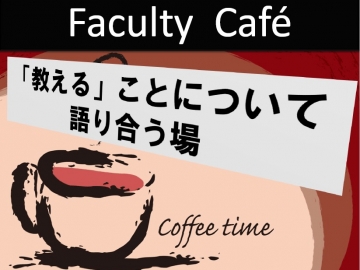2023年度開講科目早稲田大学ティーチングアワード
総長賞受賞
対象科目:日本語教育学特殊研究(1)(アカデミック・ライティングⅠ)(秋)
受賞者:小林 友美
大学院の修士課程で必要となるスキルのひとつが、アカデミック・ライティングだ。特に、初めて修士論文を書く留学生にとって、日本語での論文執筆は大きなハードルとなり得る。2020年度に日本語教育研究科に設置された科目「アカデミック・ライティングⅠ」は、修士課程での留学生の増加と日本語のアカデミック・ライティングを学ぶ機会の少なさが背景にあった。主とする対象者は修士1期目の留学生だが、実際には留学生から日本語が母語の学生、修士1期目以上の学生、すでに修了した学生まで、専門分野もさまざまな学生が履修する。小林先生の授業では、論文の書き方の基礎から学生各々の研究計画作成まで段階を踏みながら、個々の関心や進捗に合わせた柔軟なサポートで多様な学生のニーズに応えている。
留学生を中心に、日本語母語話者の学生のニーズにも応える授業設計
この科目は、日本語でのアカデミック・ライティングに不慣れな留学生を主な対象としている。しかし、日本語母語話者である学生も履修することができ、どちらの学生からも高い評価を得ている。
日本語が母語でない留学生にとって、日本語特有の論文スタイルや表現を学ぶことは容易ではない。この授業ではモデルとなる論文を例として参考にしながら、具体的な書き方を学び、学生それぞれが自分のライティングに取り組んでいく。先行文献の探し方や引用の仕方もきめ細かく指導する。中には悪意なく剽窃と見なされる表現を使ってしまうケースもある。適切な引用方法や自分の意見を加える重要性を丁寧に伝えることも大事にしている。
また、日本語が母語であっても日本語の論文を簡単に執筆できるというわけではない。日本語母語話者の学生にとっても、この授業から学ぶことは多い。たとえば、文章を書くことに自信がなかったり、論文執筆の経験がなかったりする学生にとって、この授業は自身のスキルを再確認しブラッシュアップする場となっている。日本語母語話者である学生からは「ライティングの弱点を認識できた」「日本語教師として役立つ内容だった」等のポジティブなフィードバックが寄せられている。
基礎から応用まで、段階的にスキルを高める
日本語での論文の書き方を学ぶこの科目。授業では論文の基本的な構造や表現方法を学ぶことから始まり、最終的には各学生が自分のテーマで修士論文の序論と研究計画書を書き上げることを目指す。半年かけて学生が無理なくライティングスキルを身につけることができるよう、課題を段階的に設けている。
授業の初期段階では、アカデミック・ライティングの基礎として、論文の構造や表現について学ぶ。授業の回ごとに、論文の序論や先行研究の書き方、研究方法、結論などの各セクションの書き方に焦点を当て、まずはモデルとなる論文を分析して議論するところから始める。
モデル論文は、日本語教育の分野から小林先生が選定したものを始めに提示する。どのような表現や構造が読みやすいのか、先行文献ではどのように記述されているのかを学生とともに分析する。さらに、学生自身も自分が専攻する分野から論文を選び、授業で紹介する。この授業は日本語教育学の過程の一環ではあるものの、履修する学生の専攻分野は多岐にわたる。分野が異なれば論文の形式やルールにも違いがある。この授業では日本語教育学をベースとしつつも、学生それぞれが自分の分野で論文を書けるようになることを支援する。そのための工夫がここにも見られる。
モデル論文から学んだあとは、学生それぞれがライティングに取り組む。課題として執筆した文章を授業内のペア・グループワークで互いにコメントし合う。そのコメントをもとにリライトしたものをWaseda Moodleで提出し、教員が個別にフィードバックを返す。このサイクルは学期中に3回から4回繰り返される。このプロセスを何度も経験しながら、学生は他者の論文を読み解くだけでなく、自分で論文を執筆する力を少しずつ養っていく。
個別のフィードバックで学生一人一人の悩みに寄り添う
この授業では、修士1期目の履修者が多いこともあり、学生が自身の研究計画書を完成させることを目標としている。しかし、研究テーマの絞り込みや適切なライティングの方法でつまずく学生も少なくない。そこで、学生同士の学び合いと教員による個別のフィードバックを組み合わせ、各自の課題に寄り添った指導を行っている。
授業では、ペアワークやグループワークを活用し、学生同士が互いの成果物にフィードバックを行う。これにより、自分の文章を客観的に見つめ直し、他者の視点を取り入れる機会を得ることができる。フィードバックの際には、あらかじめ注目すべきポイントを指示し、学びが深まるよう工夫している。ペアの組み合わせは毎回変え、必要に応じて教員が介入し、適切なアドバイスを行う。さらに、優れたモデル論文を参照し、それを自分の執筆に生かすことで、文章の質を高める手助けをしている。
教員による個別のフィードバックも充実している。学生同士のコメントに加え、小林先生が課題を丁寧に添削し、口頭でもアドバイスを行う。提出された課題に対するフィードバックは、オンラインツールを活用して詳細に行われるほか、授業内でも直接指導を実施する。このプロセスにより、学生一人ひとりの進捗や悩みに応じたきめ細やかな対応が可能となる。
フィードバックを通じた相互学習は、単なる知識の習得にとどまらず、批判的思考や表現力の向上にもつながる。学生が互いに意見を交わしながら文章を磨き、個別の添削を受けることで、より深い学びを得ることができる。こうした丁寧な指導により、学生は自身の成長を実感しながら、研究計画書の完成へと着実に歩みを進めている。