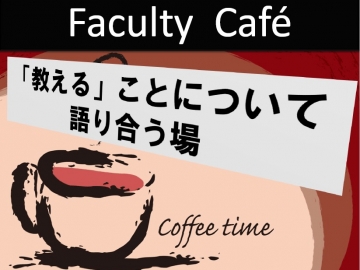2021年度春学期ティーチングアワード総長賞受賞
対象科目:General Management(総合経営)(全日制)
受賞者:菅野 寛
 「会計」や「組織論」といった個々の経営系科目で学んだ理論を生かし、
「会計」や「組織論」といった個々の経営系科目で学んだ理論を生かし、
ディスカッションを通して経営課題の解決策を模索する「General Management(総合経営)」。
担当する菅野寛教授は、学生が活発に発言できるように工夫すると共に、
コーディネーターとしてディスカッションをよりよい方向に導いている。
学生がディスカッションを通じて主体的に学びを深める授業は、
「有意義」で「よく理解できた」と学生から高い評価を得ている。
設備+細やかなフォローで、ハイブリッド環境でもスムーズなディスカッションを実現
General Management (総合経営)はファイナンス、マーケティング等の個別の科目で学んだ知識を総合的に使って経営課題を解くための「同総合力」を養う科目である。英語で教える科目で、約50人いる履修者の9割以上は外国人だ。ディスカッション主体で授業を進める点に大きな特徴がある。しかしコロナ禍で、2021年度の春クォーターは学生の半数以上が海外からのオンライン参加となった。
「教室」と「オンライン」というハイブリッド環境の中、菅野教授はディスカッションをスムーズに進めていく方法を検討した。「まず教室を作り変えました。具体的には、天井に数十センチ四方の平たい大きなマイクを取り付けて、教室のどこで話していても声をしっかり拾えるようにしました。また、カメラを教室後方にセットして、オンラインの学生が教室全体を見渡せるようにしました」。カメラは、TA(ティーチング・アシスタント)が操作を行い、必要に応じてホワイトボードと教室全体などフォーカスを切り替えた。
さらに、授業が始まった後もオンラインに関する要望に耳を傾け、何かあればすぐに解決へと動いた。例えば、オンライン参加の学生から「声が聞き取りづらい」という声が出たときには、教室の学生に声を出してもらい、どの程度の音量ならオンラインでもよく聞き取れるのかを確認して対応した。こうした工夫の結果、ハイブリッド環境でも問題なく履修者全員でスムーズにディスカッションを行うことができたという。
初回に「心得」を明確に提示することで、活発なディスカッションを促す
この科目にはいわゆる「正解」はないと菅野教授。「現実の経営問題では、答えは一つではありません。授業では、実在する企業が実際に直面した経営上の問題について、自分が経営者ならどのように考えて意思決定するのかを話し合っていきます。ある結論だけを正しい答えとするのではなく、他の意見も聞いてさまざまな見方やその理由に気づけることがもっとも重要です」。学生は、毎回取り上げるケースの資料を事前に読み、自分の考えをまとめた上で授業に臨む。
ディスカッションが主体の授業では、学生の積極的な発言が求められるが、活発なディスカッションのためには工夫も必要だという。「まず初回の授業で、ディスカッションの『心得』を伝えました。例えば、どんなレベルの発言でも、発言をすること自体が授業へのコントリビュート(貢献)になるといったことですね。何を言ってもいいという心理的安全性の確保で発言がしやすくなります」。
意見が出にくいときには、少人数でのディスカッションに切り替えることも工夫の一つだ。「1対1のペアや5人一組など少人数になれば、話をせざるを得ないからです。少人数のディスカッションで出た意見を全員の前で発表してもらって、改めて全員でディスカッションをすることもあります」。また、オンライン参加の学生は発言のタイミングを図ることが難しいため、なるべく参加しやすいようにより目を配ったという。
菅野教授は、コーディネーターとしてディスカッションをよりよい方向に導く役割を果たす。議論の収拾がつかなくなるような場面では、介入して話をロジカルに整理し、論理的でない部分があれば学生たちの発言を補足。時には、議論の内容をホワイトボードにわかりやすく図式化することもある。「ディスカッションが想定通りにいかないのはよくあることですが、ティーチングプランから著しく外れた場合は、『論点はAになると思っていたけれど、みんなはBについて話している。どうしてそうなったのか考えてみよう』などと投げかけることもあります」。自由に発言できる環境を確保した上で適切に教員が関わることで、内容的にも充実したディスカッションが実現できたと言える。
毎回の授業を振り返り、授業への意見や要望を伝えられる「takeaway memo」の存在
もう一つ、この科目の特徴となっているのが「takeaway memo」という、毎回の授業後に提出する簡単なレポートの存在だ。Googleフォームの定型フォーマットで作成されていて、①授業で発言した内容、②発言の機会がなかったが発言したかった内容、③今日の授業での学び(takeaway)、④講師への提言(suggestion)の4項目からなる。学生は、授業の翌日いっぱいまでに提出する。
授業時間内には伝えきれなかった意見や疑問に思ったことなどを、学生たちはこのメモを通じて菅野教授に伝えることができる。「これを読めば、学生がどこまで理解したか、どこに問題を感じているのかなどがわかるので、翌週の授業ではそのフォローアップのディスカッションから始めます」。また、授業の内容以外の要望や提言も、そのままにはせず必ず対応するようにしている。「不満や要望、意見などは、学生にもオープンにして『こんな声が出ているが、どうすればいいと思う?』と学生自身に解決策を考えさせるようにしています」。
今後の課題としては、「非同期のディスカッションの活用」を挙げる。リアルタイムのディスカッションだけでなく、Waseda MoodleやSlackなどのチャットツールを使ったディスカッションができないかと検討しているという。「授業後にまだ気になっていることがあったら自由に書き込んでもらい、それに対して他の履修者が意見をどんどん書き込むといったことをイメージしています。また、こちらからテーマを与えてもいいかもしれません。どのようなやり方がよいか、今後仕組みを作っていきたいですね」。