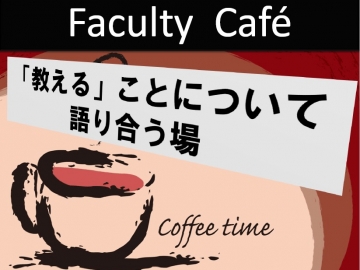2021年度春学期ティーチングアワード総長賞受賞
対象科目:実験経済学I 01
受賞者:上條 良夫
人間の感情や非合理性が経済行動に与える影響を考える「実験経済学」。
新しい分野の経済学を学ぶこの授業で上條教授が目指しているのは、
①経済学の面白さを再発見すること、②経済学的思考を日常に応用する力を醸成すること、
③学術的な知見や研究に触れることの3点だ。学生とのコミュニケーションを大切にし
「知らないのが当たり前」の感覚で寄り添う姿勢は、「非常にわかりやすく、
勉強したいという意欲が湧き上がってくる」など、学生に大きく評価された。
学生同士の繋がりが、学習意欲を向上させる
基本的にオンデマンドで実施されたこの授業の工夫でまず挙げられるのが、講義動画を見る前に毎回実施したアンケートだ。「質問は講義内容に関連した簡単なもので、その後に講義を聞くと、さっきのアンケートはこういう意味があったのかと理解できるような、講義のフックとして使いました」。
回答すると他人の答えも表示されるため、学生に横の繋がりを感じさせる効果もある。「正直どう答えたかはあまり大事ではなくて、自分以外にもこの授業を受けている学生がいると感じてほしいと思いました」。
学生の繋がりは以前から重視してきた。「他の授業を対面で行っていたときは、問いに対して学生同士で相談する時間を設け、その後に答えさせていました。他の学生と繋がって考えを共有することが自信となり、発言のハードルも下がります。授業態度も積極的になりますね」。オンラインでも何とか学生同士の繋がりを実感させたいと考えた仕掛けのひとつが、このアンケートだった。
体験による生きた理解で、経済学の面白さを感じてほしい
15回のうち2回だけはZOOMでつなぎ、リアルタイムで実験を行った。「今繋がっているというリアリティに加え、実験経済学なので実験をライブで見せるのが一番インパクトがあると考えました」。たとえば、<この状況で人はどう考えるか>などと尋ね学生に答えてもらった後、関連する論文を読ませている間に集計し、その回答結果を公開する。「単に論文を読んだだけではピンと来ないけれど、先に実験をしてから論文を読み、結果を見ると、実体験として納得できます」。
生で行う実験は思惑通りにならないこともあれば、教員自身が予期しなかった点に気づくこともある。「実験とはそういうもので、それも含めて研究なのだと伝えています。遠いところにあると思っている研究を、身近に感じてくれればうれしいですね」。
授業で読ませる論文が英語の場合は、翻訳ツールの利用も許可している。「良い論文は英語で書かれていることが多いので、こういうものを使えば自分でも読めるんだと体感してほしいのです」。根底には、学部の2年生であっても、できるだけ学術的な知見や研究に触れさせたいという狙いがある。
アンケートや実験を取り入れるのは、机上の空論ではなく、個人の体験による生きた理解や見解を獲得させたいからだ。「実感を伴わない論理は虚しいので、体験した上での理解を促したいのです。極論を言うなら、論理的な理解が多少間違っていても、実感が伴って生きた理解に達している方が、生きる知恵になると思うのです」。
同時に、経済学の面白さを再発見させたいという願いもある。「大学で経済学を学び始めると、こんな数字や抽象的な話が日常の理解に役立つのか?という虚無感を覚えがちです。そんな認識を一新させ、経済学の面白さを伝えたいのです」。
ここで学ぶ目的は、経済学の理論が現実の人々の行動の理解にどう役立つか考え、理論的な見解を自分の言葉で述べられることだと考えている。「単に経済現象だけでなく、日常に応用できるような思考の訓練をしてほしいと思います」。
「知らない」を前提にしたレベルに設定し、一方では高い到達点を目指す
2回に1回は単元テストという小テストも実施した。ユニークなのは回数無制限で受け直せるところだ。「問題の難易度は高めです。そのかわり何度やってもいいので満点目指して頑張ってという感じですね」。点数は平常点として加算されるため、学生は何度も挑戦した。「自動採点ですぐ点数が出るので挑戦したくなるのでしょうか。『おかげで健全な学びにつながりました』と書いてくる学生もいました」。
期末試験もオンラインだが、その出題方法にも工夫がある。全6問のうち前半3問は頑張ればできる問題、後半3問は頑張っても解けない問題を用意。解答時間は3日間あるが、後半の問題は正解率が10%を切るほどの難問だった。「単位が目的なら前半だけ解けばいいと言ったんですが、8割9割ぐらいの学生が後半も解答していました」。
研究を身近に感じさせ、意欲のある学生を意識して高い到達点を目指す一方で、講義自体は「知らないのが当たり前」という前提で行っている。「導入から聞けば高校生でも理解できるレベルです。まじめにやれば単位は取れるが、いい成績を取るにはかなり頑張る必要がある、そんな設計にしてあります」。
毎回講義の後に書かせた感想は、必須ではなく加点もされない。それでも多くの学生が積極的に書いてくれた背景には、感想から抜粋して説明を加えた動画を作り公開するという、丁寧なフィードバックがある。300人規模のクラスではかなりの労力だが、「読むのは結構楽しかった」と苦にしていない。「こちらが寄り添うから、実は難しいけれども学生は頑張ってついてきてくれる。その関係性のおかげで成り立っている授業なのかなと思います」。
教育者である大学教員が研究も行う意味は何か。悩んだ結果、良い教育のためには良い研究をしなければいけないと思い至ったという。「自分が生み出した知識を教えるのが大学教員なのだと。いつかは学部生の授業で扱う価値があるような研究論文を書くのが私の目標です」。