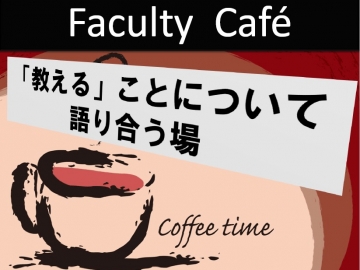2021年度春学期ティーチングアワード総長賞受賞
対象科目:Professional Presentations
受賞者:ドーラン ダニエル P.
「Professional Presentations」を担当するドーラン・ダニエル教授は、オンラインに移行するにあたり
従来の授業構成を大きく変更した。プレゼンテーションのデザイン(構成)を学ぶことに重点を置き、
対面授業で行っていたプレゼンテーションは行わないことにしたのだ。
教授は、学生が直面している事情に配慮し、現在利用できるツールを効果的に活用しつつ、
彼らの学習目標の到達をサポートしている。
学生になるべく多くの選択肢を与え、オンデマンドでも安心して学べる場を提供
ドーラン教授が教鞭を取る「Professional Presentations」は会計研究科設置科目で、2021年度春学期には13人の学生が履修した。授業はすべてオンライン、オンデマンドで行われた。授業の流れは以下のとおりである。まず教授は事前にMoodle上でPDFとビデオの両方を提供。ビデオではPDFを教授が音声で説明する。学生はPDFだけを読んでもいいし、ビデオだけを見てもよいし、両方でもよい。重要なのはオプションを与えることだと教授は考えている。ビデオ制作の際、教授は「EverLec」というソフトを使用した。次に、各授業の学習目標に関連した画像やYouTubeビデオ、ウェブサイトのリンクを示した。また、Moodleのチャットルーム機能を利用して、学生同士で交流するための場所を授業ごとに用意し、教授は参加しないことと、英語でも日本語でもOKと伝えた。自由に安心して話し合える場を提供するのが狙いだそう。「通常は授業前後に友だちになれる機会がありますが、この状況下ではできません。私は彼らにそういう機会を持てる選択肢を与えたい。この学期は使われていない様子でしたが、負担も少ない方法なので、今後もオンデマンドで授業を行うときは必ず設置したいと思っています」。
各授業のあとには学生はMoodle上でフィードバックを書くことができる。教授はそこから学生たちの反応や習熟度などの情報を得て、細かく修正を加えていくという基本方針だ。
授業構成を大胆に変更し、現在使えるツールによる効果的な学びを模索
今学期の最大の変更点は、プレゼンテーションの練習を授業内容から省くことにしたことである。この科目の重要項目は2点あり、1点目がプレゼンテーションのデザイン(構成)について学ぶこと、2点目がプレゼンテーションのパフォーマンス(演じ方)についてだったが、この変更により、1点目のデザインに焦点を絞ったのだ。「実はオンライン1年目にはZoomを使用し、生徒にリアルタイムでのプレゼンを行わせたのですが、期待していたような結果が得られませんでした。そこで、2年目の2021年にはパフォーマンスに関しては、実際プレゼンをさせることはやめ、TEDのビデオへのリンクを『お手本』として示すことにしました。デザイン(構成)について基本的な知識を得て、他の人のやり方を知ることにより、学生もできるようになるというのが私の根本的な考え方です。今のところ学生からの不満はありません。この調整は大きなもので、最善の方法ではありませんが、今使えるツールではこれが最もうまくいく方法で、学生たちは新しいやり方でも学んでくれていると信じています」。
この科目の評価方法としては、レポート提出が2回。1回に最高45%ずつ得点を与えた。Wordのフォーマットを配布し、どのような点が評価されるかを明確に示した。提出されたものには教授がフィードバックコメントを書き入れ、返却した。配点の残りの10%はさまざまな事情を考慮し努力点として与えた。
また、英語のレベルは評価の対象外だ。「評価は学生たちの考えについてのみ行い、英語の文法などについては評価の対象にしていません。将来のキャリアで重要なのは英語のスキルではなく創造性や熱意であり、自分の考えを明確に伝えるためにベストを尽くすようにとシラバスでも明記してあります」。
オンデマンドに移行して以来、この科目に限らず教授は課題の締め切りをなくしたのだそうだ。「もちろん、最終的な成績はつけなくてはなりませんが。コロナ禍でのストレスにより、学生たちは感情的、心理的、身体的または個人的な理由などにより影響を受けていて、それが科目の成績にも影響していると認識しています。レポート課題の提出形式も、全部エッセイでもいいし、イラストでもパワーポイントでもいい。生徒たちがそれぞれのやり方で心地よく学べるように柔軟性を与えたいのです」。
学生は『students』ではなく『learners』。学習目標の到達を助けたい
教授は、日本の学生がコミュニケーションの際にリスクを取らない傾向があると指摘する。「日本の文化的背景からそのことは理解できますが、特に将来国際的な環境でビジネスに携わるときにはリスクを取ることを期待されます。私はどの授業でも、リスクを取る練習をすることを奨励しています。レポートガイドに『Don’t take a small bite. Take a big bite.(小さく一口食べるな、大きく齧れ)』『“lazy thinking report” (手抜き思考レポート)や、常識的にみんなが知っている事柄についてのレポートは書くな』とよく書いているのですが、新しい考えで私を驚かせてほしいのです」。
教授は、学生たちを『students(生徒)』ではなく『learners(学習者)』であると考えている。学ぶ過程にフォーカスしている『study』という言葉に比べ、『learn』という言葉は結果に重点を置いている言葉だからだ。「学生たちを『learners』と考えることは、彼らの学習の目標に到達するのを導く私を助けてくれると信じています。この状況下で、学生たちは日常生活で危機に直面しています。ですから私はできる限りの柔軟性を与え、パートナーとして協力し合い、彼らの学習目標の達成への手助けをしたいと考えているのです」。