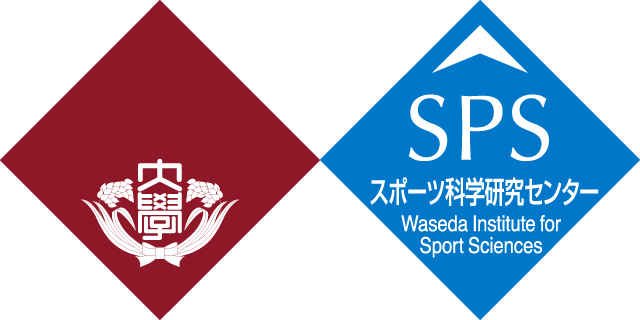第6回 2003年12月15日
演題1
随伴陰性変動(CNV)によるタイミングの研究
演者
望月芳子先生(早稲田大学大学院人間科学研究科D1)
内容
本研究では,連続タイミング事態下で,時間間隔変化がCNVに及ぼす影響を調べた.刺激間間隔(inter-stimulus interval: ISI)と試行間間隔(inter-trial interval: ITI)を操作した.実験の結果,CNV波形に及ぼすISI効果は中心-頭頂部に,ITI効果は前頭-中心部に観察された.タイミングの情報処理には,ISIとITIの両効果が影響していることを紹介する.
演題2
脊髄の歩行パターン生成能力とその回復可能性
演者
中澤公先生(国立身障者リハセンター)
内容
最新の神経科学の進歩は従来不可能とされていた脊髄損傷者の歩行機能回復を、既に実現可能な目標として捉えはじめている。 ここでは、最新の歩行トレーニングの科学的基礎をなす、脊髄の歩行パターン生成能力とその可塑性に関する近年の研究動向について紹介する。
第5回 2003年11月10日
演題1
スポーツの精神障害者生活時間への影響
演者
福田敬子先生(早稲田大学大学院人間科学研究科スポーツ精神医学研究室)
内容
スポーツ活動が精神障害者の生活に具体的にどのような影響を与えているのかは、十分に明らかになっていない。そこで本研究では、精神障害者のスポーツ活動と生活時間の関連性について調査を行った。方法:東京近郊のデイケア患者を対象に、スポーツ活動の頻度調査と生活時間調査を実施した。調査項目のうち、睡眠覚醒に関しては、睡眠をとっている時間帯を、連続する2日間、被調査者全員分の値を加算し、睡眠中の人の割合の推移を求めた。また、入眠時刻、覚醒時刻についての差異についてStudent t-testを用いて有意差検定を行った。結果:週3回以上スポーツをしていると答えた群(スポーツ群)と全くスポーツをしていないと答えた群(非スポーツ群)で、生活時間について比較した。覚醒時刻の平均値はスポーツ群、非スポーツ群でそれぞれ6:45、7:19、入眠時刻は、20:45と22:14であり、覚醒時刻入眠時刻供にスポーツ群で早かった。統計的には有意ではなかったが、入眠時刻はより強い傾向を示していた(P=0。096)。また、スポーツ群においては、全く昼寝をしているものがおらず、また夜間においても全員が睡眠を取っている時間帯が存在した。考察:週3回以上スポーツをしていると答えた人は、全くスポーツをしていないと答えた人と比べ、早寝早起きの傾向があ り、さらに昼寝はせずに夜は必ず眠るという規則正しい生活リズムを示していることが明らかになった。しかし、今回の調査では、規則正しい生活リズムとスポーツ頻度の因果関係は明らかになっていない。今後は、スポーツをほとんどしていない患者を対象とし、スポーツ活動を行った場合どのように生活リズムが変化するのかを調査する必要があ る。もし、スポーツが実際の生活リズムに好影響を与えているのであれば、生活リズムが乱れた患者群に対して、積極的にスポーツ活動を導入する根拠となる。
演題2
Resistance exercise combined with vascular occlusion
演者
宝田雄大先生(早稲田大学スポーツ科学部スポーツ医科学科)
内容
Skeletal muscles adapt themselves to varied exercise stimuli in a manner that they respond appropriately to the new mechanical and metabolic demands: intense resistance exercises generally cause increases in muscular size and strength (McDonagh and Davies 1984), whereas exercises with much smaller load and larger volume result in an increase in the muscle oxidative capacity without considerable increase in muscular size (Holloszy and Booth 1976). For the particular purpose of muscular hypertrophy and concomitant increase in strength, it has been believed that intensity higher than 65% of one repetition maximum (1RM) is to be used (McDonagh and Davies 1984).
On the other hand, we have shown that a low-intensity resistance exercise (20-50%1RM) combined with vascular occlusion (occlusive resistance training) induced marked increases in size and strength in elbow flexor muscles of old women and in knee extensor muscles of athletes, even if the intensity of exercise was much lower than expected to promote muscular hypertrophy (Takarada et al. 2000b; Takarada et al. 2002). The mechanisms underlying such an effect of externally applied occlusive stimulus have been interpreted as follows: 1), additional recruitment of fast-twitch fibres in a hypoxic condition (Takarada et al. 2000a; Takarada et al. 2000b) 2), stimulated secretion of growth hormone (GH) and norepinephrine (Takarada et al. 2000a). I will first talk about the acute effects of the occlusive resistance training, then chronic (long-term) effects of that. In addition, I am going to show the latest data concerning the effects of the occlusive resistance training on fMRI-measured brain activation in my laboratory.
第4回 2003年9月29日
演題1
アレイ電極を用いたEMG計測とその応用
演者
小田俊明先生 (東京大学大学院生命環境科学系)
内容
1980年代以降、複数の電極を直列に配列したアレイ電極を用いて、対象筋から多チャンネルの表面EMGを計測することが行われてきた。本発表では、この方法を利用することにより可能となる測定法・解析法(筋線維の活動電位伝導速度、電流発生源[運動終盤位置]推定、運動単位のデコンポジション等)について紹介し、その身体運動科学への応用例を示す。
演題2
硬膜下電極を用いた睡眠覚醒時の皮質律動の研究
演者
内田直先生(早稲田大学スポーツ科学部スポーツ医科学科)
内容
てんかんの外科手術適応判定の際に行う硬膜下電極慢性留置は、ヒトの皮質電気活動を測定するための非常に貴重な機会であ る。我々は、都立神経病院脳神経外科清水弘之部長らのグループと共同で、これまでに覚醒、自然睡眠を通じてのヒト大脳皮質各部位での皮質電気活動について記録してきた。これらの結果について、まとめて報告したい。
側頭葉内側部では、大きく二つの特徴ある波形が記録された。一つは、15Hz前後の我々がベータ1と読んだ帯域であ る。この15Hz前後の律動は、非常に規則的で連続性がよく、睡眠覚醒の中では、覚醒とレム睡眠期に出現していた。側頭葉内側部の重要な部位は海馬であ るが、げっ歯類などの哺乳類では海馬で覚醒時とレム睡眠期にシータ活動が記録されることが知られている。ヒトで記録された15Hz前後の律動がこの海馬シータ活動とどのような関連があ るのか興味がもたれる。もう一つは30-150Hzのガンマ活動である。この活動は徐波睡眠期でやや減少するものの、覚醒睡眠を通じて一貫して側頭葉内側部に出現していた。また、セボフルレン麻酔では麻酔濃度が上昇するにつれてガンマが減少した。また、あ る一例では、側頭葉内側と同時に前帯状回に電極が装着されたが、ここからは非常に規則的なシータ律動が覚醒時とレム睡眠期に出現していた。
このように、硬膜下電極記録は通常の表面脳波では記録できないヒトの大脳皮質電気活動の特徴を捉えるのに非常に貴重な情報を提供する。これまでの研究では、これまで報告の無いいくつかの特徴的律動を記述することができた。今後はこれらの律動がどのような生理学的な機能を持っているのかを明らかにすることが課題となる。
第3回 2003年9月2日
演題
運動準備電位と脳内情報処理過程
演者
正木宏明先生(早稲田大学スポーツ科学部)
内容
長時定数で増幅記録した脳波を随意運動の開始時点で加算平均すると、運動開始前1~2秒から陰性方向へ緩徐に立ち上がる準備電位(readiness potential;RP)が観察される。RPは前期成分BP(Bereitschaftspotential)と後期成分NS’(negative slope)から構成され、BPは全般的な準備状態を反映し、NS’は当該運動に特異的な準備過程を反映するものと解釈されている。BP振幅は左右半球間で差はないが、NS’振幅は運動肢と対側半球で大きい。従来の報告を概観すると、RPは力量や運動速度などの運動要因や、注意、構え、動機づけなどの心理要因の効果によってその波形は変化する。いずれの要因の効果も、RPの振幅増大や立ち上がり時点(出現時点)の移行として現れる。ここでは、課題遂行に関与する心的努力によってNS’振幅が増大する知見を紹介したうえで、90年代以降の認知心理学研究にもたらしたRPの貢献について紹介する。NS’は当該運動の準備-実行に直接関与する脳内プロセスを反映することから、NS’の偏側性は、1985年以降,認知心理学のモデルを検証する道具として注目されるようになった。NS’の偏側性を表現するために左右半球間で算出した差波形は、lateralized readiness potential(LRP)と呼ばれている。LRPの出現時点は反応処理系の開始を反映することから、LRPは反応処理系のタイミングを知るツールとして捉えられている。しかしながら、認知心理学で提唱されている各処理段階(刺激評価段階、反応選択段階、運動プログラミング段階、運動実行段階、など)のうち、どの処理段階とLRPの出現時点が対応しているかについては明確にされていなかった。最近行った実験によって、LRPが反応選択段階直後かつ運動プログラミング段階直前から出現することを示せたので,この知見についても紹介したい。
第2回 2003年5月24日(早稲田大学精神生理学研究会共催)
演題
Monitoring and Evaluation Processes of the Medial Frontal Cortex
演者
William J.Gehring (ミシガン大学心理学科助教授)
第1回 2003年4月22日
演題
Measuring Brain Activation and Connectivity by Means of Combined EEG and fMRI Recordings
演者
Pedro A. Valdes-Sosa(キューバ神経科学センター副所長)