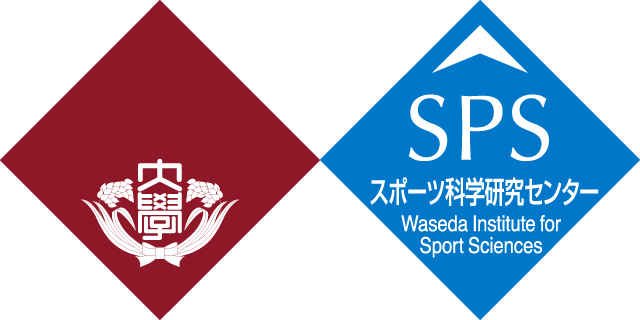- その他
- 所沢 スポーツサイエンス研究会(2004年度)
所沢 スポーツサイエンス研究会(2004年度)
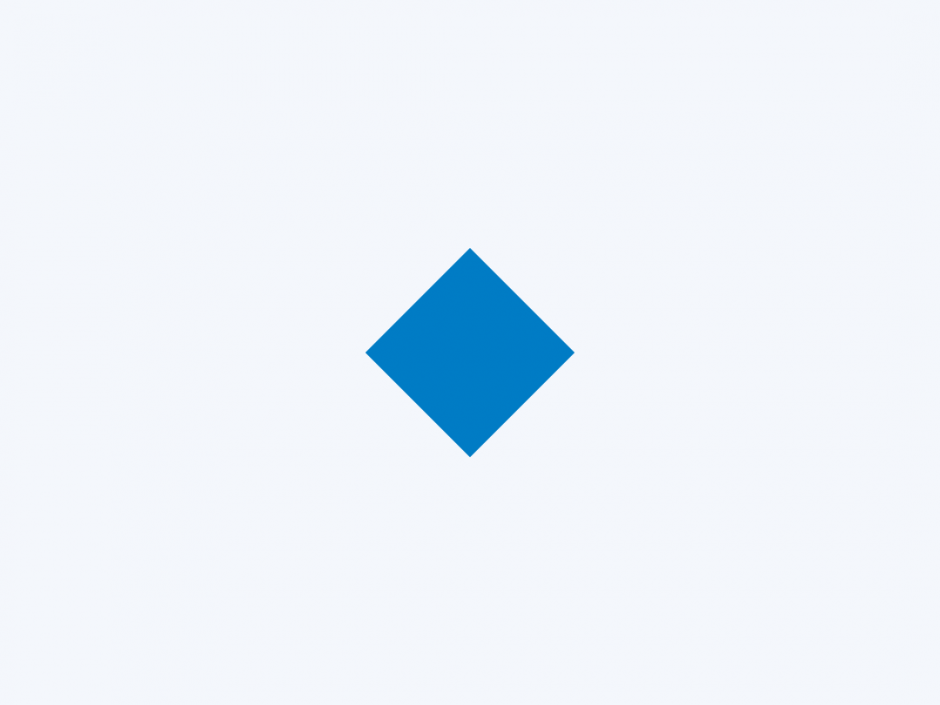
- Posted
- Thu, 02 Dec 2004
第17回 2004年12月14日(火)
演題
加齢に伴う力調節能力の変化
演者
篠原稔氏(コロラド大学ボゥルダー校 統合生理学部 上級研究員)
内容
加齢に伴って筋量や最大筋力、最大パワー、反応時間などの最大容量が低下することはよく知られている。ここでは、日常生活でより頻繁に行われる最大下収縮における、力を調節する能力の加齢に伴う変化とその神経生理機序を中心に発表する。
第16回 2004年11月9日(火)
演題1
てんかんとスポーツ
演者
松浦雅人教授(東京医科歯科大学大学院)
内容
てんかんをもつ人のスポーツへの参加をめぐる問題については、小児期の発作頻発例や重複障害例にみられるVulnerable Child Syndrome、運動中の突然死、水泳中の事故などについて紹介する。また、運動によって誘発される発作や、バイオフィードバックを用いた発作の行動療法についても紹介したい。ついで、一般の人が運動中に生じることのあ るけいれん発作をめぐる問題についてふれたい。最後に、運動が脳機能に与える影響、とくに運動によって脳内ドーパミン活性が亢進し、てんかん発作の閾値を下げる可能性について考察したい。
演題2
オーバートレーニング症候群とうつ病
演者
内田直教授(早稲田大学スポーツ科学部)
内容
オーバートレーニング症候群(OTS)は、長期間の過度なトレーニング負荷の結果出現する身体的、精神的な症候を呈する病態であ る。特に、精神的症候はうつ病に酷似しており、また発症の形式も長期の慢性的ストレスへの暴露という点で類似しているため、OTSの中枢における病態を理解するためには、うつ病研究の成果が大きな助けになる可能性があ る。近年のうつ病研究では、セロトニン仮説、グルココルチコイド受容体仮説などが提出されているが、これらとオーバートレーニング症候群研究の知見には共通した部分もあ る。これらを踏まえ今後のOTS病態解明の戦略としては、臨床的には経過の丁寧な観察、特に身体的症状と精神症状の関連;OTSの症例に対するSSRI等使用の治験の積み重ね;OTSに陥り易い性格傾向や小児期のストレスなどについての調査研究;最近のうつ病研究の方法(脳機能画像など)をOTS患者に当てはめるなどが考えられる。
第15回 2004年10月19日
演題1
大学生の睡眠-覚醒パターンと精神的健康
演者
浅岡章一先生(早稲田大学スポーツ科学部)
内容
大学生の就床時刻は他の年代と比較して後退していることが知られている。我々はそのような睡眠習慣を引き起こす要因について検討するとともに、睡眠習慣の乱れが大学生の精神的健康に与える影響を検討してきた。
演題2
投球競技者の肩関節回旋腱板筋の形態・機能特性
演者
長谷川伸氏(早稲田大学スポーツ科学部)
内容
投球やラケットスイングを伴うオーバーヘッド型スポーツの選手には棘下筋萎縮や、外転・外旋筋力の低下が示されることが多い。しかし、こうした現象が競技歴の長期化に伴う必然的なものかどうかは明らかではない。そこで中学~大学生までの野球選手を対象に回旋腱板筋の形態・機能について検討した。
演題3
発話動作における感覚フィードバック機構
演者
誉田雅彰先生(早稲田大学スポーツ科学部教授)
内容
発話動作は脳の内部モデルに基づくフィードフォワード制御によると考えられている。一方、発話獲得時においては聴覚フィードバックが不可欠であることが知られている。ここでは、発話動作と感覚フィードバックの関係に関する知見を紹介し、これらの知見から導かれる発話動作の運動制御機構に関する仮説について述べる。
第14回 2004年7月13日
演題1
身体運動トレーニングによる骨格筋代謝機能向上のメカニズム
演者
寺田新(早稲田大学スポーツ科学部、日本学術振興会特別研究員)
内容
食事などで摂取した糖質の80%以上が骨格筋で処理される。したがって、糖尿病(2型)は、骨格筋の代謝機能異常が原因となって発症すると考えられている。身体運動は、骨格筋の代謝機能を高めることから、糖尿病の予防および治療に効果的であ ることが良く知られている。しかしながら、身体運動が、骨格筋代謝機能を向上させる分子メカニズムはほとんど明らかとなっていない。我々は、身体運動が骨格筋代謝機能を向上させる分子メカニズムの解明、さらにはそれに基づいた運動処方プログラムの開発を目指して研究を行っており、本研究会では、これまでに得られた我々の研究結果の報告を行う。
演題2
ローイング運動の健康科学
演者
樋口満先生(早稲田大学スポーツ科学部教授)
内容
ローイング(ボート漕ぎ)は脚・体幹・腕などほぼ全身の筋肉を動員して行われる持久性運動であ り、ボート選手は筋量が多く高い呼吸循環器系機能を有することが知られている。そこで、日常規則的に行われるローイング運動は中高年者の健康増進、生活習慣病予防にとっても有効であ る可能性がある。我々は中高年ローイング愛好者を対象として、このような視点から研究を行っているので紹介する。
第13回 2004年6月29日
演題1
前額部への機械的外乱の予測可否による頸部筋反射応答の変調
演者
倉持梨恵子先生(早稲田大学スポーツ科学部助手)
内容
ヒトの運動にとって重要な頭部姿勢を制御する頸部筋を対象に、外乱の予測可否が筋の反射応答に与える影響を検討した。特に頭部への外乱に対する頸部筋の反射応答には、前庭器官と筋紡錘という異なる受容器からの入力情報が含まれることに着目し、分析した。
演題2
日本の相撲は古代オリンピックと赤い糸でつながっている
演者
寒川恒夫先生(早稲田大学スポーツ科学部教授)
内容
スイスのバーゼル大学の古典学教授カール・モイリは、紀元前8世紀に始まる古代オリンピックは、中央アジアの騎馬遊牧民の葬礼競技に発するとの仮説を提出した。この説を展開すると、日本古代の相撲と古代オリンピックとが結びつくことになるのだが‥‥
第12回 2004年6月15日
演題1
変形性膝関節症患者の膝関節モーメント
演者
内藤健二先生(早稲田大学人間科学研究科博士課程)
内容
演題2
生活フィットネスの加齢変化;貯筋のススメ
演者
福永哲夫先生(早稲田大学スポーツ科学部教授)
内容
健康で活発な日常生活を遂行する為には生活環境に適応できる身体能力が必要であ る(この能力を総称して「生活フィットネス」と呼ぶ事にする)。「生活フィットネス」は加齢と共に低下するが、その低下パターンに個人差が大きい。平均的な生活を送っている場合に比較して、日頃 活発な身体活動(スポーツ)を実施している場合には「生活フィットネス」は高い水準を維持する事が出来る。一方、運動不足状態が続くと「生活フィットネス」が低下し、また、病気などをきっかけにして急激な「生活フィットネス」の低下が観察される。「生活フィットネス」の中でも特に重要な要素に脚の筋機能があ る。筋機能は筋量により決まる。脚筋機能の低下は、「歩く」「階段を昇る」「立ったり座ったりする」といった日常生活動作の遂行に支障を来し、関節への負担を増し、ちょっとしたバランスの崩れを修正できず転倒の危険性を高める。 加えて、身体不活動は骨量の低下をも引き起こすので、骨折しやすくなり、ひいては寝たきり状態をもたらすことにもなりかねない。
正常な日常生活が維持できなくなる機能水準(仮に「寝たきりフィットネス」と呼ぶ事にする)に近づく事は生活能力に余裕が無くなる事を意味する。高齢者にとって「自立して生活できるだけの身体能力があればそれ以上の体力は不要である」との意見も聞く。しかし、病気ではなくとも「寝たきりフィットネス」に近い状態で生活する事は病気になった場合(例えば、風邪をひく、骨折をする等)の安静状態(身体不活動)がもたらすフィットネスの低下は「寝たきりフィットネス」を簡単に達成する事(脚筋機能低下)になり、その結果、病気は治ったけれども「歩けない」→「寝たきり」と云った状態を引き起こす事になる。一方、高水準の「生活フィットネス」所有者は病気などの状態になったとしても「寝たきりフィットネス」まで時間を稼ぐ事が出来、充分に回復する為の時間的余裕を有する事が出来る。いざと云う時の為の「貯金」と同じく、日頃 高い「生活フィットネス」を保証する身体諸機能を貯えておく事「貯筋」が必要である。
高年齢になるに伴い筋骨格系機能が低下することは生物学的特性として致し方のないことではあ るが、その能力は日常生活習慣や環境条件などにより強く影響されると考えられる。加齢変化は人為的に変えられようもないが、その変化に身体運動は見事に影響を与える主要条件であ る。身体を構成する器官や組織の形態と機能に対する加齢変化を的確に把握し、自分の生活習慣にフィードバックする事が出来るかどうかは、まさしく各自の知性と教養によるものであ ろう。その為にも、ヒトの身体組成とその運動機能に対する加齢現象とその運動の効果に関する正確な情報を得、その知識を自らの身体を創造する為に生かされなければならない。
第11回 2004年5月20日
演題
MR Phase Contrast Study of the Differences in Structure-Function Relationship during Isometric and Passive Movement of the Lower Leg
演者
Dr. Shantanu Sinha(Assoc. Prof., Dept. of Radiology,UCLA School of Medicine)
第10回 2004年5月18日
演題
スポーツ免疫学の課題
演者
赤間高雄先生(早稲田大学スポーツ科学部助教授)
内容
適度なスポーツ活動は免疫機能を高めるが、過剰なスポーツ活動は免疫機能を低下させる。この現象の測定と応用の可能性について、唾液分泌型免疫グロブリンAのデータを中心に解説する。
第9回 2004年4月20日
演題1
健康づくり事業における行動科学の役割
演者
武田典子氏(早稲田大学大学院人間科学研究科)
演題2
上腕三頭筋の力-速度関係の生体計測
演者
川上泰雄先生(早稲田大学スポーツ科学部助教授)
内容
人間を対象として、最大努力の肘関節伸展動作中の筋線維短縮速度の実測を通じて、筋線維の力-速度関係を決定し、関節における観察結果から推定した筋の力-速度関係との比較を行った実験結果を紹介します。
第8回 2004年3月10日
演題
Motor and Cognitive Development in Adolescence Concomitant with Pubertal Hormonal Changes
演者
Patti Davies (Colorado State University)
第7回 2004年1月19日
演題1
中高年の運動処方の現状と状来
演者
能勢博先生(信州大学・加齢適応医科学系独立専攻・スポーツ医科学教授)
内容
高齢化社会を迎え、高齢者を対象とした運動処方に基づく予防医学は、医療費削減の見地から国家運営の戦略上、早急に整備されなくてはならない問題であ る。米国では、10年以上前より高齢者の医療費の節約を目標として、Healthy People 2000 プロジェクトが、国家レベルで行われ、その効果が現れつつあ る。しかし、我が国では厚生労働省主導で、昨年度よりこのプロジェクトの日本版、「健康日本21」が行われているが、その「運動処方」の部分については、現場で用いるには具体性に乏しく未完成であ るという指摘が多い。特に、高血圧、糖尿病治療のための運動処方が、健康保険適用(保健全体の5%)の対象となった昨今、我が国の実状に合わせた運動処方の「具体的」な運動強度の基準の確立が求められている。この点のデーターを補強すべく、松本市は平成9年度から7年間、40歳以上の中高年を対象とした健康スポーツ教室を開催している。その成果と将来展望について述べ、健康スポーツの今後の予防医療における重要性について述べる。
演題2
同一筋内における運動昇圧反射の部位差の検討~漸増運動中の骨格筋脱酸素化と心血管反応の変移点負荷の関連性に注目して~
演者
水野正樹先生(早稲田大学大学院 人間科学研究科D2)
内容
我々は、安静時および運動後回復期において、同一筋内における近位部と遠位部でhemodynamicsが異なることを報告した(Mizuno et al. J Appl Physiol;2003;Mizuno et al. Jpn J Physiol;In Press)。そこで、この同一筋内におけるhemodynamicsの不均一性と運動昇圧反射の関連性について検討したので紹介する。
- Tags
- 研究活動