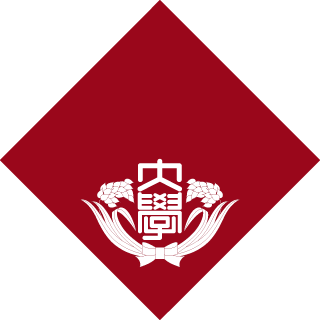- 海外派遣学生
- 荒川深映 Shinei ARAKAWA
荒川深映
Shinei ARAKAWA

- Posted
- Wed, 20 Aug 2025
先進理工学研究科 博士1年 荒川 深映
- 派遣期間:2025年2月~7月
- 派遣先大学:アールト大学
- 派遣先国・地域名:フィンランド・エスポー
海外派遣を希望した理由
私はこれまで、実世界の画像をコンピュータに理解させ、新たな画像を生成する技術である「画像生成」に関する研究を進めてきました。かねてより、本分野の最前線で革新的な研究を続けている Jaakko Lehtinen 教授に注目しており、そのもとで学ぶことを強く希望していました。今回、SGU から渡航支援の機会をいただき、同教授の指導を直接受けることで、自身の研究スキルをさらに発展させるため、海外派遣を希望いたしました。
研究内容・成果
私は画像生成技術の一つである拡散モデルを用い、階層的な画像生成を実現する研究に取り組みました。拡散モデルとは、実画像のようなデータをランダムな状態に変換し、その逆過程で元の構造を復元することで生成分布を推定する技術です。元々は物理学で分子運動を記述するランジュバン動力学から発展した手法で、明快な物理・数学的基盤を有しています。
しかし、実際の拡散モデルはこの理論を基盤としつつも、ニューラルネットワークの構造や推論アルゴリズムの工夫など、様々な改良が加えられています。その結果、理論的な理想形と実装上の最適解は必ずしも一致せず、現実的な手法ではヒューリスティックな調整を伴う場面が少なくありません。これは、理論と実践の間に依然として橋渡しの余地が残されていることを意味します。
この現状を踏まえ、私は人間が絵を描く過程に着目しました。多くの場合、まずは輪郭線で全体像を描き、次に部分ごとに形や色を補い、最後に細部を描き込むという段階を踏みます。粗い情報から順に詳細を追加することで、各段階で描くべき内容が明確になり、構図の整った作品が仕上がります。この考え方を拡散モデルに応用し、生成過程を粗から細へと段階的に構築することで、各ステップで追加する情報の操作性と分離性を高め、より直感的かつ制御可能な画像生成の実現を目指しました。
研究の過程では、先行研究の調査から手法の実装まで一貫して行い、その中で研究設計や評価方法に関する大きな学びを得ました。また、開発した可視化プログラムは生成過程の理解やモデル比較に有用であり、渡航先の研究室でも活用されています。渡航期間中に研究を完結させることはできませんでしたが、帰国後も改良を継続し、国際会議への論文投稿を目指しています。
学校環境
アールト大学は、フィンランドの首都ヘルシンキから地下鉄で10分ほどの場所に位置しており、また木々が生い茂る森に囲まれた場所にあります。アールト大学は、歴史的に著名な建築家・デザイナーであるアルヴァ・アールト氏の名に由来しており、キャンパスはアーティスティックで個性が際立った雰囲気を持っていました。研究室の現役学生は合計で10人程度と比較的小規模で、広々とした研究室でゆったりと研究や議論に身を投じました。大学には、最新のGPUを搭載した計算機クラスターが数多くあり、様々な実験を実施することができました。
 Aalto大学のキャンパス
Aalto大学のキャンパス
 研究室の風景
研究室の風景
国際交流
研究室では、英語およびフィンランド語が話されており、研究の議論や雑談など様々な機会を通して、英語で物事を説明するスキルを身につけることができ、渡航前よりも自信を持って英語を話せるようになりました。また、フィンランド語についても少しずつ勉強し、フィンランドの歴史や価値観について学ぶこともできました。また、私はシェアハウスに住んでおり、ヨーロッパ各地出身の他の学生と共同で生活することで、遠出をしたりアクティビティへ参加したりする過程で、それぞれの持つ価値観を理解し合うことができたと思います。
 研究室のメンバーとディナー
研究室のメンバーとディナー
住居環境
私は、アールト大学から地下鉄で約15分離れた Espoonlahti(フィンランド語で「エスポーの湾」の意)という場所にある共有アパートに滞在していました。周囲は森に囲まれ、とても静かで落ち着いた環境でした。フィンランドは高緯度に位置するため、渡航直後の2月は午前8時頃に日の出を迎え、午後5時頃には日没する状況でした。一方で、夏至が近づくにつれて夜11時を過ぎても明るさが残り、研究後に研究室の学生たちと共に飲みに出かけたり、サウナを楽しんだりと、日本では味わえない時間の過ごし方を経験できました。
 アパートの近くの海岸で見た夕暮れ
アパートの近くの海岸で見た夕暮れ
周辺環境
フィンランドは国土の約74%が森林に覆われ、約19万の湖が点在しています。自然が非常に豊かで、現地の人々は仕事の後に森へ出かけ、友人と語らったり、一人の時間を過ごしたりすることが多いです。私自身も、研究で疲れたときには森を訪れ、ゆったりと気持ちを整理する時間を取っていました。研究室からは地下鉄やバスでヘルシンキ中心部へ容易にアクセスでき、買い物や観光にも出かけました。アパート周辺には森や港に加え、大型複合商業施設があり、日用品や食材の調達にも困りませんでした。また、対岸の国エストニアへはフェリーで約2時間と近く、観光で訪れることもできました。
 夏のラップランド地方
夏のラップランド地方
 中世の面影を残すエストニアの首都・タリン
中世の面影を残すエストニアの首都・タリン
現地の文化
フィンランドでは、労働法によってコーヒー休憩が保障されており、キャンパス内にも複数のコーヒーマシンが設置されています。そのため、研究室のメンバーとコーヒーを片手に議論を交わすことが日常的に行われており、特に印象に残っています。また、研究室には余分な椅子があり、教授や学生たちはそれを持ち寄って私のデスクや他の学生のデスクに集まり、相談や議論を行っていました。常に研究内容を説明できるよう準備する姿勢があり、その雰囲気が活発な議論を生み出していたと感じます。
一方、フィンランドの冬は非常に厳しく、その反動から人々は春の訪れを心待ちにしています。特に5月1日は「Vappu」と呼ばれる祝日で、伝統的なお菓子や飲み物で盛大に祝います。また、夏至の日には「夏至祭」が行われ、サマーコテージで家族と過ごすのが習慣です。私はその時期、ヘルシンキ近郊のビーチで夕暮れを楽しみ、季節の移ろいを肌で感じることができました。
 フィンランドの夏至
フィンランドの夏至
海外経験を経て、今後の目標
今回の海外経験を通じて、自身の研究分野における知見を深めただけでなく、研究の進め方や議論のあり方といった、博士課程で基盤となる「研究姿勢」についても大きな学びを得ました。今後は博士課程において、これらの学びを活かしながら研究を発展させ、人々の喜びや社会に貢献できる技術の開発を目指します。その過程で、トップレベルの国際会議に論文を投稿し、そこで今回お世話になった Jaakko Lehtinen 教授や研究室の学生たちと再会することを、直近の目標としています。
終わりに
今回の海外派遣を通じて、日本で研究を続けていただけでは得られなかった貴重な経験を積み、新たな挑戦をすることができました。これらの経験は、今後の日本での研究活動に必ず活かせると確信しています。最後に、留学前から何度もご助言をくださった SGU 拠点事務支援チームの皆様をはじめ、渡航費用等を全面的にご支援いただいた SGU に心より感謝申し上げます。