- ニュース
- 【開催報告】RCLIPイブニングセミナー「AIと著作権 日中の最新動向と課題」が開催されました
【開催報告】RCLIPイブニングセミナー「AIと著作権 日中の最新動向と課題」が開催されました

- Posted
- Wed, 28 Feb 2024
RCLIPイブニングセミナー「AIと著作権 日中の最新動向と課題」
主 催:早稲田大学知的財産法制研究所(RCLIP)、香港城市大学
共 催:早稲田大学比較法研究所、早稲田大学法学部
日 時:2023年12月11日(月)18:00~20:00
場 所:早稲田大学3号館4階405教室& Zoomウェビナー
言 語:英日逐次通訳
司会:鈴木將文(早稲田大学法学学術院教授)
講演者:何天翔(香港城市大学准教授)、謝晴川(武漢大学法学部准教授)、奥邨弘司(慶應義塾大学教授)、上野達弘(早稲田大学法学学術院教授)
参加者:45人(うち学生27人)
2023年12月11日(月)、早稲田大学にて、イブニングセミナー「AIと著作権 日中の最新動向と課題」が開催されました。今回のセミナーでは、鈴木將文教授が司会を務め、中国と日本におけるAIと著作権の関係をめぐる動向につき、中国側は、香港城市大学の何天翔准教授及び武漢大学の謝晴川准教授から、また、日本側は慶應義塾大学の奥邨弘司教授及び早稲田大学の上野達弘教授から、それぞれ報告を行い、議論を行いました。
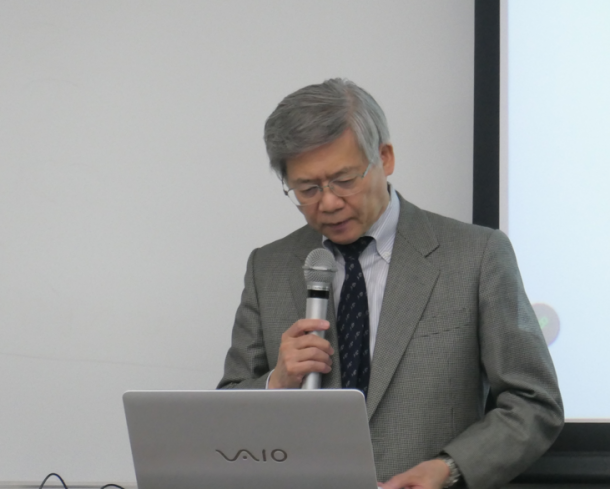

まず、何天翔准教授が「生成AIと中国の著作権保護」をテーマとする報告を行いました。何准教授は、生成AIがもたらす著作権法上の問題について、特に独創性の判断基準、著作権の目的等の問題を取り上げて、AI生成物を著作物として判断した中国の最新判決にも言及し、AIをめぐる著作権法上の問題を分析しました。そして、これらの問題に対する解決策として、デジタル署名等により技術的かつ法的に人間の作品とAIによって生成されたコンテンツを区別すること、AI生成物保護法を設立すること、著作物の登録制を再開し、技術によって登録申請された作品を審査すること等を挙げられました。

次に、謝晴川准教授から、「中国における著作権制限規定の革新」と題するテーマの報告が行われました。謝准教授はまず、中国著作権法では、立法の遅れ、裁判官による立法的判断、権利制限規定における一般条項の位置づけの不明確性等の問題が存在すると指摘しました。続いて、謝准教授は、TikTokをはじめとするショートビデオプラットフォームにアップロードされたAI技術を利用したビデオが増えたことから、新技術に対応する法律が要請されているが、技術の発展を促進することが公正使用の決定的な根拠ではなく、そこでは、公平性という要素も考慮されるべきであると説明しました。最後に、謝晴川准教授は、「使用目的」を主とし、「公平性」を補助的要件とする多層的な規範の確立を解決案として提示するとともに、日本法からの示唆も踏まえて、権利制限規定のあり方が今後の課題である旨を指摘しました。
続いて、日本側から、奥邨弘司教授は「AI生成表現の著作物性」及び「機械学習と著作権権利制限規定」という二つの論点から検討を行いました。奥邨教授はまず、AI生成物が著作物となるか否かについて、人間による創作的寄与の有無を著作物性の基準とする考え方が日本及び米国で取られている旨を説明しました。続いて、米国のZarya事件と中国の春風が優しさを運ぶ事件の判旨を分析した上で、日中米は、AI生成表現について、人間が創作したと評価できなければ、著作物として認められないという点は共通しているが、表現の生成過程に、人間による強い関与を必要とするのが日本と米国の考え方である一方、中国は、弱い関与でも良いという考え方を取っていると指摘しました。二番目の論点である機械学習と著作権制限規定については、機械学習のために必要な行為と、それに対応する日本著作権法上の権利制限規定(30条の4、47条の5)を紹介し、機械学習に関する設例を交えながら、権利制限規定の適用可能性について検討を行いました。

上野達弘教授は、何天翔准教授及び謝晴川准教授の報告に対してコメントを行いました。何准教授の報告で提示された著作物の登録制度について、上野教授は、仮に登録するとしても、誰が権利を有するかについて質問を提起しました。また、謝准教授の報告で言及された一般規定としての権利制限規定について、上野教授は、日本の柔軟な権利制限規定と中国で検討されている受け皿規定との間には共通する部分があると指摘した上で、情報解析の権利制限規定について、中国ではどのような議論が行われているのかについて、質問を提起しました。さらに、奥邨弘司教授の報告で言及された裁判例を踏まえて、人間による創作的行為はどこまで認めるべきかが重要な論点となると指摘した上、権利制限規定30条の4の但書の判断基準について、論点を示しました。
パネルディスカッションの段階において、何天翔准教授は、中国の最近の判決については、既存の法制度との調和に問題があると指摘し、謝晴川准教授は、中国著作権法実施条例の改正をすることによって問題を解決することを提案しました。奥邨弘司教授からも、本日の論点についての総括的なコメントがなされました。さらに、質疑応答では、会場から様々な質問が出されて活発なやりとりが行われました。
(文:譚天陽・比較法研究所助教)

