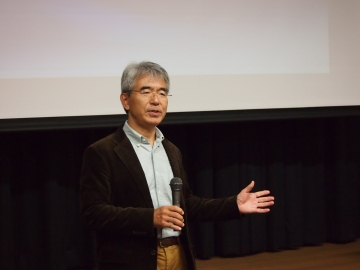- ニュース
- 【開催報告】映画上映会「検事、弁護人、父親、そして息子」が開催されました
【開催報告】映画上映会「検事、弁護人、父親、そして息子」が開催されました

- Posted
- Wed, 18 Oct 2017
日時 2017年10月13日(金)14時45分~18時00分
場所 26号館地下多目的講堂
司会 中村民雄
題目 『検事、弁護人、父親、そして息子』
参加人数: 25名(うち学生18名)
主催 早稲田大学比較法研究所
後援 ブルガリア共和国大使館
概要:
映画の上映に先立ち、ブルガリア共和国大使館のイリヤナ・コストヴァ氏(文化担当)より挨拶があり、ブルガリア共和国の地理、文化、歴史などの基本情報について紹介があった。
次に、本学で国際法を担当している河野真理子教授から、今回の映画を観るにあたっての予備知識として、旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所とはいかなる組織なのか、その役割と権限について簡潔な説明を行った。
映画は、オランダのハーグの旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷における、ボスニア紛争の司令官であったクルスティッチの戦争犯罪をめぐり、女性検事のカトリーヌ・ラグランジュと弁護人のミハイル・フィンの攻防について描いている。クルスティッチの部下であったと自称する青年、デヤン(後に本名がミロであることが明らかとなる)の証言内容に疑問をもった弁護人ミハイルは、彼の両親を探すためボスニアまで行き、見つけることに成功する。法廷のなかで参考人として久々に再会を果たした父子であったが、ミロの証言内容が虚偽であったとして、検事のカトリーヌによってミロは強制送還されてしまい、父子の再開は束の間となり、その後のミロの消息は不明となるという、実話に基づく内容となっている。
映画の上映後は本学の三人の教員による補足説明が行われた。まず西洋史・ジェンダー史を専門としている弓削尚子教授より、ミロの母親はイスラム教徒で父親はキリスト教徒であるというように、ユーゴスラビア国内にはさまざまな民族と宗教が混在しているということを、実際に地図を示しながら説明があった。こうした多種多様な民族と宗教の混在がユーゴスラビア内戦の要因となったが、ユーゴスラビア内戦における民族浄化は、単に特定の民族を根絶させるのではなく、その民族の女性を強かんし、自分たちの子孫を作らせることを目的とした点で特異であると指摘した。
次に、河野真理子教授は、被告人のクルスティッチが有罪になったものの死刑判決ではなかった点に着眼し、裁判所がヨーロッパ的な価値に基づいて行われているという点を指摘した。また本来、国が行った犯罪に対しては本来は国が責任を負うものであるが、人道に対する罪や大量殺戮についてなどはニュルンベルグや東京裁判のように国の政策立案に携わった者に対しても責任を追及する傾向が脈々と受け継がれているとしている。
それから映像論を専門とする谷昌親教授は、本映画が検事と弁護人といった論理的な存在と父子という感情的な存在という関係と、検事カトリーヌと偉大な法律家であった父親・弁護人ミハイルと老人ホームにいる父親・そしてミロとその父親など、さまざまな物事がそれぞれ対比的な関係にあるという点を指摘するなど、映画作りの観点からのコメントがあった。
フロアーからの質疑応答のセッションでは、ある学生から旧ユーゴ国際戦犯法廷のような、当事国とは異なる第三の国の者によって裁かれるのは、見方によっては非常に傲慢なのではないかという意見があった。また別の学生からは、法廷において弁護人のミハイルがミロに対して、信仰する宗教は何か尋ねる場面についての質問があり、ユーゴスラビアにおける個人のアイデンティティの複雑さについてあらためて考えさせられるとともに、司法の場においてそのような質問をすることについて、日本人の立場からみた違和感についても議論が展開された。
参加した学生や院生や教員から回収したアンケートでは、日本ではなかなか観ることのできないブルガリア映画を観ることができてよかったという意見、先生方の解説を聞きながら映画の表現の仕方や裁判制度の問題点などを考えさせられたという意見、深く知ることがあまりないユーゴスラビア紛争とその後の歴史について勉強になったという意見、映画が扱う事柄の前提についても考える必要があると感じたという意見、ボスニア紛争という重いテーマを扱う映画において紛争自体はいわば通奏低音として背景におき、裁判を舞台に輪郭のはっきりしたキャラクターを配置して状況に翻弄される個々の人間の感情の動きに焦点を合わせることで、言語や国を横断して観客に訴えかける普遍性を獲得しているといった意見など、映画を高く評価し、またこの新規の企画を好意的に評価する多数の感想が寄せられ、学生・大学院生そして教員にとっても大変有意義な会となったことが示された。
- Tags
- イベント