- 研究所プロジェクト
- 旧社会主義圏諸国における法と社会(Ⅱ) ─1956年と現代/世界史的転回点とその帰結
旧社会主義圏諸国における法と社会(Ⅱ) ─1956年と現代/世界史的転回点とその帰結
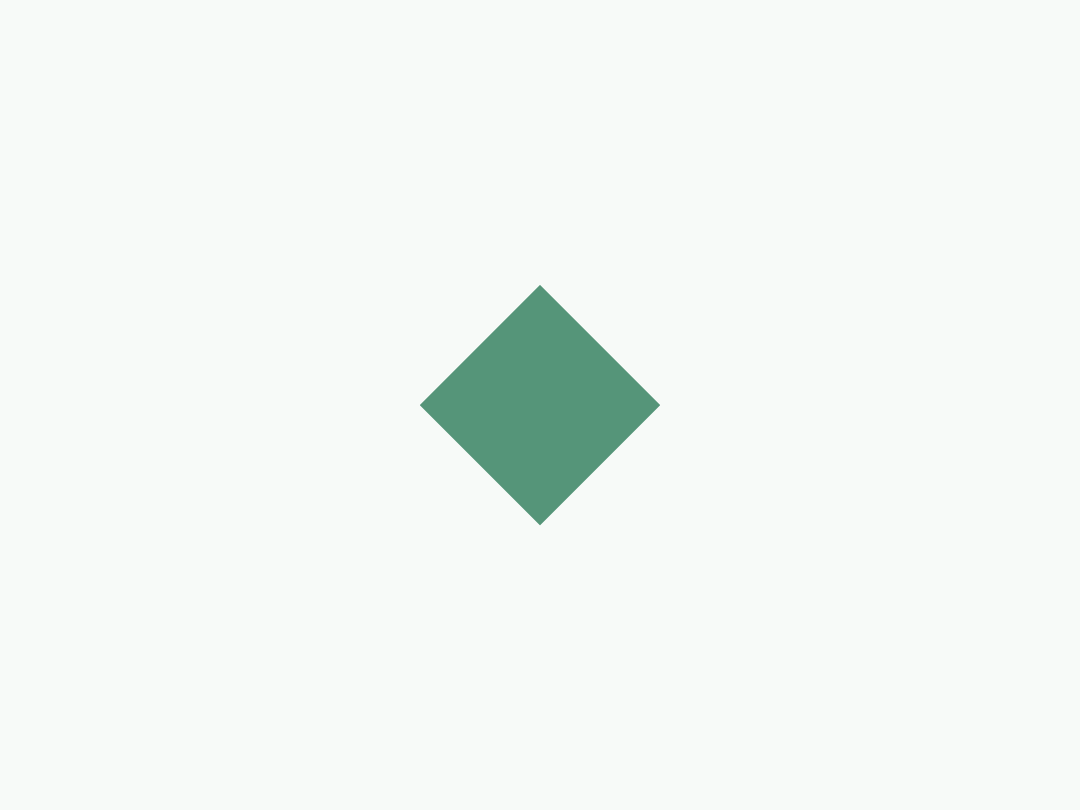
- Posted
- Wed, 09 Jul 2014
比較法学の視座から、20世紀に存立した「体制としての社会主義」を理論的に総括し、21世紀にあって転形・展開する「旧社会主義圏諸国」の現状を分析することを通じて、この時代の「社会主義問題」を究明することを目途とする。
プロジェクト講演会
| 【第1回】ソビエト・ロシアから民主共和制ロシアへ | |
|---|---|
| 日時 | 2010年10月22日(金)17:30-20:00 |
| 演題 | スターリン批判とソビエト法の変容(刑事法の視点から) |
| 講師 | 渋谷 謙次郎 特別研究員(神戸大学 教授) スターリン批判がソビエト法に最も大きな影響をもたらしたのは、刑事法領域であると言える。この問題をめぐって、スターリン時代の刑事司法とスターリン死去後の法改正をもとに検討する。 |
| 演題 | フルシチョフ<秘密>報告の今日的再読 |
| 講師 | 佐藤 史人 特別研究員(法学学術院 講師) 1956年のいわゆるフルシチョフ「秘密報告」は、世界に衝撃を与え、種々の議論を誘発してきた。同報告は、ソビエト法史においても重大な画期をなすが、体制転換以降、法学の領域で改めてその意義を探る試みは少ない。本報告では、スターリン批判前後の党と国家、司法省と裁判所、中央と地方の緊張関係に着目することで、当時の具体的社会状況の中にフルシチョフ「秘密報告」を定位し、ソビエトおよびロシア法史を再検討する手がかりとしたい。 |
| 司会 | 笹倉 秀夫 研究員(法学学術院 教授) |
| 会場 | 早稲田大学早稲田キャンパス8号館2階会議室 |
| 共催 | グローバルCOEプログラム《企業法制と法創造》総合研究所(基礎法関係グループ) |
| 後援 | 早稲田大学ロシア研究所 |
| 【第2回】東西ドイツから統一ドイツへ | |
|---|---|
| 日時 | 2010年12月17日(金)17:30‐20:00 |
| 演題 | 東西ドイツ統一の法的諸問題 ―1989年東欧革命の今日的評価 |
| 講師 | 広渡 清吾 (専修大学 教授) 1990年の東西ドイツ統一は資本主義と社会主義の対抗を基軸とした20世紀において、いかなる意味を有したのか。またドイツ「民族」の現代史においてどのような意義を担ったのか。さらに統一ドイツはどのような発展を示して世界のなかでの役割を果そうとしているのか。他方で統一ドイツ社会はいかなる問題を抱えているか。これらについて法的視点から分析を試みる。 |
| 演題 | 東ドイツ1953年事件の今日的解読 |
| 講師 | 水島 朝穂 研究員(法学学術院 教授) 1953年6月17日事件とは何だったのか。ハンガリー事件、チェコ事件に先行するこの事件を今日的視点から再検証することは、1989年東欧革命への「深層海流」を探る上で意味があろう。 |
| 司会 | 楜澤 能生 研究員(法学学術院 教授) |
| 会場 | 早稲田大学早稲田キャンパス8号館3階大会議室 |
| 共催 | グローバルCOEプログラム《企業法制と法創造》総合研究所(基礎法関係グループ) |
| 後援 | 早稲田大学ロシア研究所 |
| 【第3回】1956年から1989年=1991年へ | |
|---|---|
| 日時 | 2011年1月28日(金)17:30‐20:00 |
| 演題 | コミンテルン・コミンフォルム解散と国際共産主義運動の変容 ―1989年=1991年への帰結 |
| 講師 | 加藤 哲郎 (政治学研究科 客員教授) ロシア革命の影響で作られた国際共産主義運動は、世界革命の夢が後景に退いた1930年代以降、ソ連邦外交に従属するものとなった。1943年のコミンテルン解散、1947-1956年のコミンフォルムも国際関係の従属変数だった。その東欧・アジアへの作用を読み直す。 |
| 司会 | 岡田 正則 研究員(法学学術院 教授) |
| 会場 | 早稲田大学早稲田キャンパス8号館3階大会議室 |
| 共催 | グローバルCOEプログラム《企業法制と法創造》総合研究所(基礎法関係グループ) |
| 後援 | 早稲田大学ロシア研究所 |

