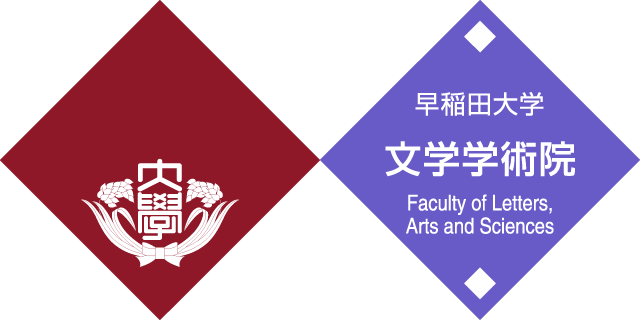- ニュース
- 開催報告:講演会「Shadowlands : Reflections on One Hundred Years of Modern Japanese Literature」6/14
開催報告:講演会「Shadowlands : Reflections on One Hundred Years of Modern Japanese Literature」6/14
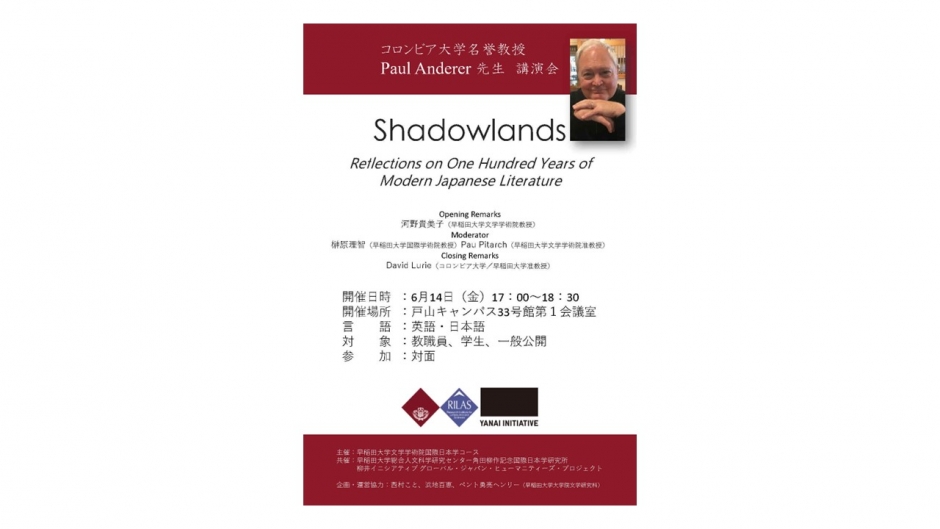
- Posted
- Tue, 25 Jun 2024
国際日本学コースは、2024 年 6 月 14 日、ポール・アンドラ氏(コロンビア大学名誉教授、東アジア言語文化学部)をお迎えし、講演会「Shadowlands : Reflections on One Hundred Years of Modern Japanese Literature」を開催した。
講演の冒頭で、アンドラ氏は近代日本文学の始まりとされる時代に遡った。「私小説」と呼ばれるジャンル以外でも、ほとんど男性である近代日本文学の作家は「あるがままに」事物を描写しようとした。彼らは主に英雄には程遠い存在を主人公にし、非常に個人的で現実的な(あるいは現実に基づいた)物語を語ることを目指していた。氏は、このような前提下で形成された近代文学において、最も典型的な作品として田山花袋などの自然主義者による小説を取り上げ、論じた。
大都会である東京はそのような現実的な物語の舞台として選ばれた。しかし、アンドラ氏が指摘するように、東京は、芥川龍之介のような作家が現実に基づかない物語を語ることを可能にする「影の都市」でもあった。氏は、文学作品と共に岡倉天心の『茶の本』(1906)も言及し、茶室という空間は現代における吉本ばななが描いた「キッチン」にあった冷蔵庫と似たような役割を果たすと論じた。このような「影の空間」は、自然主義的な現実性に限らない様々な可能性を秘めており、「shadows」の中では何も起こりうる。そして、日本近代文学の代表とされる夏目漱石の『こころ』にもこの「影」が見出せる。暗い部屋に住む「先生」は家族に裏切られ、更に「K」を裏切ることによって心身ともに影に覆われる人生を送ったのである。
アンドラ氏によれば、明治後期から、特に 1923 年の関東大震災以降、日本文学は以前ほど明確ではない世界(「shadowlands」)に踏み込むようになった。川端康成の『浅草紅団』(1929)は、形式と内容の両方で現実的な物語から逸脱している例として挙げられた。さらに、この「shadowlands」をよく表している代表的な作品として、衣笠貞之助が監督したサイレント映画『狂った一頁』(1926)も重要だとされた。なぜなら、映画はこの時期から小説の特権的な地位に挑戦し始めたメディアであり、この作品では特に関東大震災の文化的な余震が描かれているからである。
震災後、東京と横浜の廃墟を通じて、近代性はいろんなメディアによって見直されるようになった。その結果、明治後期から始まった「shadowlands」に進む過程は地震による破壊によって加速された。そして、前述したように新感覚派の作家と映画制作者たちは「非現実」的な物語を語ることに挑戦し始めたのである。
講演会は、本学だけでなく、スタンフォード大学やコロンビア大学の先生方や大学院生も参加された。質疑応答の時間においても、有意義な討論が繰り広げられていた。
(国際日本学コース 博士後期課程 ソン ロカ)
(国際日本学コース 博士後期課程 マルティネス・ムリージョ トマス)
開催概要
- 日時:2024年6月14日(金) 17:00〜18:30
- 形式:対面
- 会場:早稲田大学戸山キャンパス33号館第1会議室
- 対象: 教職員、学生、一般公開
- 言語: 英語、日本語
- 主催:早稲田大学文学学術院国際日本学コース
共催:早稲田大学総合人文科学研究センター角田柳作記念国際日本学研究所・柳井イニシアティブ グローバル・ジャパン・ヒューマニティーズ・プロジェクト
企画・運営協力:西村こと、浜地百恵、ベント勇亮ヘンリー(早稲田大学大学院文学研究科)
- Tags
- イベントレポート