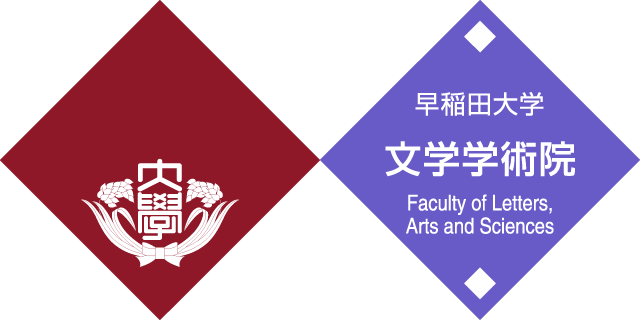- ニュース
- 開催報告 柴田元幸氏&マイケル・エメリック准教授―日本文学としての翻訳文学―
開催報告 柴田元幸氏&マイケル・エメリック准教授―日本文学としての翻訳文学―

- Posted
- Wed, 10 Oct 2018
≪対談≫柴田元幸氏&マイケル・エメリック准教授――日本文学としての翻訳文学――

本対談は十重田裕一教授(文学学術院)の開会の辞から始まり、司会進行は由尾瞳准教授(文学学術院)により行われた。
2015年1月、UCLAにて柴田元幸氏、マイケル・エメリック氏が共同で、「日本文学としての翻訳文学」というタイトルでの授業が行われた。本対談はまず、その授業の振り返りを行うところから始まり、取り上げられた明治初期からの翻訳文学が順次紹介された。それを受け、日本文学を考える上で翻訳文学を入れた方がよいという所感があったことや、文学を論じるとはどういうことかなど、翻訳文学をめぐる諸点が指摘された。
続いていくつか実際の翻訳が朗読され、検討された。二葉亭四迷訳、ツルゲーネフの『あひゞき』の1888年と1896年のバージョンについては、当時の書評で漢語の使用をめぐる格調の高さについての意見があった。また平井程一(呈一)訳のラフカディオ・ハーン(ヘルン)「耳なし芳一のはなし」の1940年版と1965年版とを比較すると、読点の打ち方の観察から、文章の緊密さよりも見やすさ(リーダビリティ)が優先されている様、つまりは時代性が見える。一方でA・A・ミルン『クマのプーさん』(石井桃子訳、2000年)には読点が多く見られるが、これは先の「耳なし芳一」とは逆に、リズムのよさを感じさせるものである。他にも普通の日本語訳ならば省略されるような表現も、石井訳の独特のリズムを生み出しているところがある。
また話題は多岐に亘った。いくつかの話題をピックアップしてみたい。
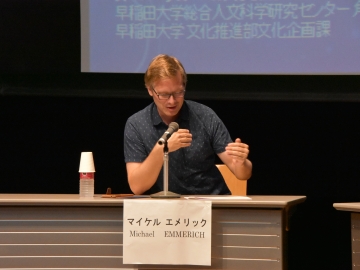
日本語訳された作品を見ないと、日本文学の流れがわからなくなる。それ以前の翻訳を念頭に置かないと、例えば村上春樹の文章は突然変異のように出現したかに見える。
日本文学というのは、作者が日本人で日本語で書いたものと捉えるのが一般的であるが、そうした考え方では漠然とした「日本らしさ」が感じられている。一方で日本文学として翻訳文学を見るという視点からは、日本という国に流通している本について「読者」から捉えることができ、従来の日本文学の方法論とは違う視点が生まれるのではないか。一方、例えばアメリカ文学を読んだときにアメリカらしさを感じることがあることも実際確かであり、そう思えること自体も重要である。同様に、日本文学を読んだときに日本らしさを感じることを蔑ろにする必要もない。日本らしさを感じたならば、それがどこから来るのかを反射的に自分に問うてみた方がよい。
文学を読む際には作者像を作りあげてしまいがちであるが、翻訳の場合にはある表現が原作者によるものなのか、翻訳者によるものなのか、非常に曖昧である。しかし実は同じ曖昧さは(翻訳ではない)普通の文学にもあるのだが、それが文学の場合には見えにくいのである。
このように、翻訳文学を日本文学の重要な一環として捉えることにより、新たな視点が生まれることの提言が多くあった。どう考えるべきか、どう捉えるべきかを聴衆とともに考える対談であった。
質疑応答も活発であった。翻訳文学から影響を受ける日本文学は世界的には特殊なのか。翻訳と逸脱について。翻訳の影響を受けていると感じられること。そして文体・翻訳について近世文学の観点からと、多様な質問が寄せられ、それを受けて対談が展開された。
最後に河野貴美子教授(文学学術院)から閉会の辞が述べられた。古典をどのように現代語訳するのかも古典を読むことにつながることなど、古典研究者としての感想があり、盛会の内に閉会となった。
【開催概要】
日時:2018年7月4日(水)16:30~18:00
場所:早稲田大学 小野記念講堂
主催:スーパーグローバル大学創成支援事業 早稲田大学国際日本学拠点
共催:早稲田大学総合人文科学研究センター、角田柳作記念国際日本学研究所、早稲田大学文化推進部文化企画課
登壇者(対談) 柴田元幸(東京大学名誉教授)マイケル・エメリック(UCLA上級准教授・早稲田大学准教授)
開会の辞 十重田裕一(早稲田大学教授)
閉会の辞 河野貴美子(早稲田大学教授)
司会 由尾瞳(早稲田大学准教授)
コーディネーター 金ヨンロン(早稲田大学研究院客員講師)松本弘毅(早稲田大学研究院客員准教授)
- Tags
- イベントレポート