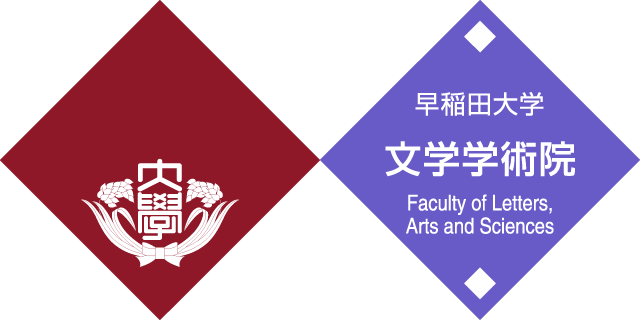- ニュース
- イベント報告:陝西師範大学郭雪妮教授講演会「『暁風集』における本草図注と室町時代の学問」
イベント報告:陝西師範大学郭雪妮教授講演会「『暁風集』における本草図注と室町時代の学問」

- Posted
- Mon, 07 Aug 2023
陝西師範大学郭雪妮教授講演会「『暁風集』における本草図注と室町時代の学問」(Annotated Illustrations of Herbsin “Gyōfūshū” and Confucianism During the Muromachi Period)が、2023年7月5日(水)に早稲田大学戸山キャンパス33号館232教室にてZoom併用のハイブリッド方式で行われました。 中日古典文学交流史、日本漢籍注釈学を専門とする郭雪妮教授は、漢籍に対して日本で生み出された解説書や講義録、すなわち抄物と称される書物群を主たる研究対象として、昨年7月より早稲田大学に訪問教授として滞在され、研究活動を展開してこられました。今回の講演は、宋人周弼が編纂した『三体詩』に対して、室町末期の相国寺禅僧万里集九が漢文で注釈を記した抄物『暁風集』を取りあげて、その注釈方法について検討したうえで、抄物文献の日本宋学思想史における意義を探るものでした。
中日古典文学交流史、日本漢籍注釈学を専門とする郭雪妮教授は、漢籍に対して日本で生み出された解説書や講義録、すなわち抄物と称される書物群を主たる研究対象として、昨年7月より早稲田大学に訪問教授として滞在され、研究活動を展開してこられました。今回の講演は、宋人周弼が編纂した『三体詩』に対して、室町末期の相国寺禅僧万里集九が漢文で注釈を記した抄物『暁風集』を取りあげて、その注釈方法について検討したうえで、抄物文献の日本宋学思想史における意義を探るものでした。
講演はまず、日本における漢籍受容の歴史を概観し、抄物についての基本事項が紹介され、従来抄物は室町時代の口語資料として国語学の立場からの研究は進められてきたものの、漢文で書かれた抄物に対しては国語学からのアプローチは必ずしも多くはなされてこなかった点が指摘されました。そして、『三体詩』は、14世紀頃に日本に伝来して以後、唐詩の教科書として五山禅林において盛んに用いられたテクストで、『三体詩』に対する注釈書は日本で数々作られたものの、万里集九の『暁風集』は室町期の古写本が残ること、また、北宋期の本草学文献が多数引用されていること、中でも特に本草図が大量に使用されている点にスポットが当てられました。
講演では、『暁風集』の記述が詳しく取りあげられ、万里集九が本草学文献や本草図を用いながら詳細な訓詁考証を展開したり、博物学的あるいは地理学的な考察をも呈示していること、また、医学書の知識とも深い関係にあることなどが具体的に浮かび上がりました。郭雪妮教授は、そうした考察を通して、万里集九をはじめとする五山禅僧がいかに北宋の学問を重視していたかを指摘され、今後はさらに朱子学や北宋の詩話、類書の受容についてより深く考究していくべきであるとの課題を示されました。

講演の後は、参加者との質疑応答が行われ、会場で参加していた大学院生からも、万里集九の注釈態度や注釈の方法、万里集九が使用していたテクストについてなど、次々と質問が出され、活発なやり取りが行われました。
なお本講演会は、スーパーグローバル大学創成支援事業 早稲田大学国際日本学拠点、および早稲田大学総合人文科学研究センター角田柳作記念国際日本学研究所の主催、早稲田大学総合研究機構日本古典籍研究所の共催により開催されました。
(文責:河野貴美子)
イベント概要
- Links
- 陝西師範大学
- Tags
- イベントレポート