- その他
- 宮崎里司(日研教授)
宮崎里司(日研教授)
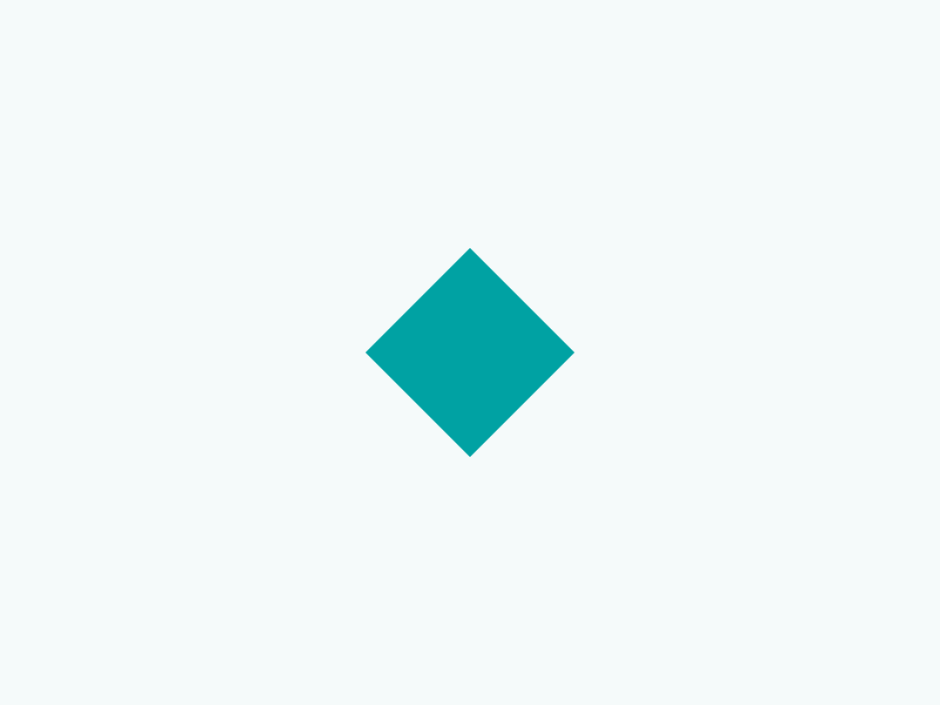
- Posted
- Fri, 01 Apr 2011
現職:早稲田大学大学院日本語教育研究科 教授
私の専門を特徴付けるキーワードとして、「(第二)言語習得」や「言語(教育)政策」などが挙げられる。日研では、社会的文脈性を視座に入れながら、実践共同体の中で日本語を習得する学習者のインターアクション問題を検証している。そして、得られた知見から、日本語教育をどのように捉えるかという意識を、院生と共有してきた。その結果、外国人力士の日本語習得に加え、少年刑務所における外国人受刑者に対する矯正教育や、夜間中学校で学ぶ外国人生徒に加え、移民政策の一環として、外国人看護・介護従事者の日本語教育の問題など、独自の研究課題を模索することができ、前任校であるモナシュ大学では、十分得られなかった実践知を学んでいる。
作家であるリービ英雄は、その著作の中で、「日本語を使って小説を書くことは、日本の文化の内部に入りこむことであり、日本研究者として、外から日本語を分析するのとは決定的に異なる体験」だとして、この体験を「越境」と名付けている。同じく作家の多和田葉子は、『「エクソフォニー」の境地を問う』の中で、近年、母語以外の言語で書く作家が少なくないという現象に着目し、「母語の外に出て書く」といった意味で、「エクソフォニー」と名付けた。こうした作家の主張から、日本語教育を非専門とする人々が、日本語教育に関心をもつエクソフォニーが、「市民リテラシー」を学び取ることに繋がると考えるようになった。同時に、「越境」を試みる人々に立ちはだかる、「日本語教育のいう職業は、日本語母語話者のものだという占有意識」に抵抗しつづけることが、私なりのレゾンデートル(存在意義)であり、その自己実現に向かうことが最優先課題であると確信している。
日本語を教えるという専門性を高めながら、占有意識を払拭する作業はたやすくはない。しかし、この作業を遂行しないと、「誰のための日本語教育か」、「誰が日本語教育に関心を持つべきか」という問いの答えが見えてこない。
日研は、そんなことを常に考えさせてくれる。
