- その他
- 岡田亜矢子(日研修士10期生)
岡田亜矢子(日研修士10期生)
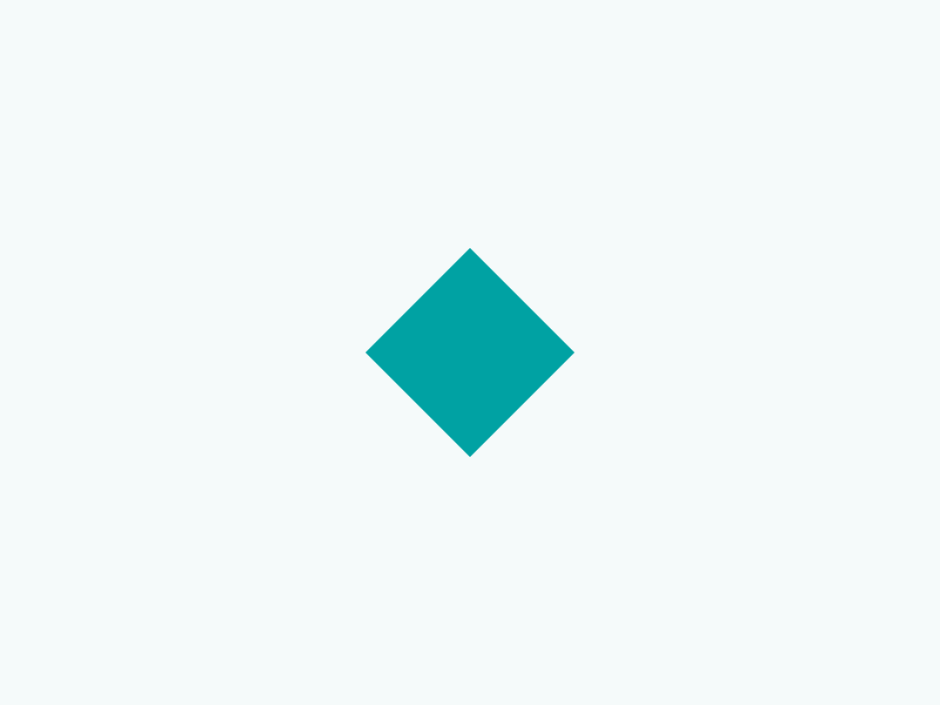
- Posted
- Fri, 01 Apr 2011
現職:大阪大学国際教育交流センター(旧留学生センター) 非常勤講師
日研創設10周年おめでとうございます。日研の歴史の中に自分も加わっていたということを光栄に思う。現在の私は、有り難いことに地元関西の大学で日本語を教えている。院進学前に、既に国内外で日本語教師をしていたが、大学で教えたいという夢と、質の高い日本語教育を存分に学びたいという希望を実現するためには日研が自分にとって最適ではないかと思い上京した。その選択はいま振り返ってみても正しかったと思う。
2005年9月開室したばかりの地域日本語教育研究室(現・池上研究室)の初の学生として入学した。翌年4月に「地域日本語教育実践研究」が新開講、実践の場である「わせだの森」(以下、「森」)を7名で立ち上げた。理論と実践と修士論文をやり遂げた日研での2年と、その後の契約講師としての半年は正に無我夢中で、最も多忙だったときは230%ぐらいのエネルギーを使っていたように感じる。3年前に早稲田を去る際、同期の友人も私も客観的に自分が何を得たか振り返ることができなかった。しかし友人は、「日研での経験は、必ず私たちの血肉となっているはず。それを信じて頑張ろう!」と言い、それを信じ私たちはそれぞれの場所へと旅立った。
とはいえ、地元に戻ってもすぐには仕事が見つからなかった。活躍する日研の先輩方や同期達を見て焦りもした。しかし「いま与えられた仕事を丁寧にこなしていくこと」「研究業績を増やすこと」「公募が出れば応募すること」といった先生方や日研メンバーからの助言に地道に取り組んだ。ちょっぴり時間はかかったが、早稲田を去って1年後に念願の大学で教える仕事に就いた。
大学で教えるようになって、日研で学び経験した様々なことが、「あーあれはこういうことだったんだ」と感じる瞬間がしばしばあった。技能クラス(口頭表現)では、私の専門や実践で学んだ「発音」「コミュニケーション」を担当し、日研カラーが発揮されていると思う。特に私の専門の「伝え合いの活動」(グループディスカッション)では、「森」でやってきたことや現在も後輩が継続中の「森」から学ぶことなどを援用し実践している。実際、他にも授業はあるので準備が大変である。しかし、いいもの・時間を学生と共有したいという思いのほうが、大変だとか面倒だという気もちを凌ぐようである。これは好きだからこそできることなのだろう。そして改めて「伝え合いの活動」が自分の研究分野であり、ライフワークであり、どうして・どんな日本語教育をしていきたいのかといった根底と繋がっているのだと感じている。
今ようやく「日研とわたし」を振り返ることができる。日研で得たものは、いま大学で教えていて活かしているすべてであると言えよう。教える際の技術的なことは勿論だがそれだけにとどまらない。理論と実践の両輪が必要であることを日研で学んだ。理論で学んだことを実践し、実践したことを省察する実践研究も身につけられた。日研でなければこのレベルまで学ぶことは無理だったのではないか。教える技術に特化した、または研究だけを追究する研究科もあるが、日研は両方の機会をバランスよく提供してくれた。両方やるのは本当に大変なのだが、必要なことだと思う。これからも日研で得た多くの宝物を携えて、実践研究家として日本語教育に取り組んでいきたいと思っている。
