- その他
- 池上摩希子(日研教授)『オシゴトとしての日研のセンセイ』
池上摩希子(日研教授)『オシゴトとしての日研のセンセイ』
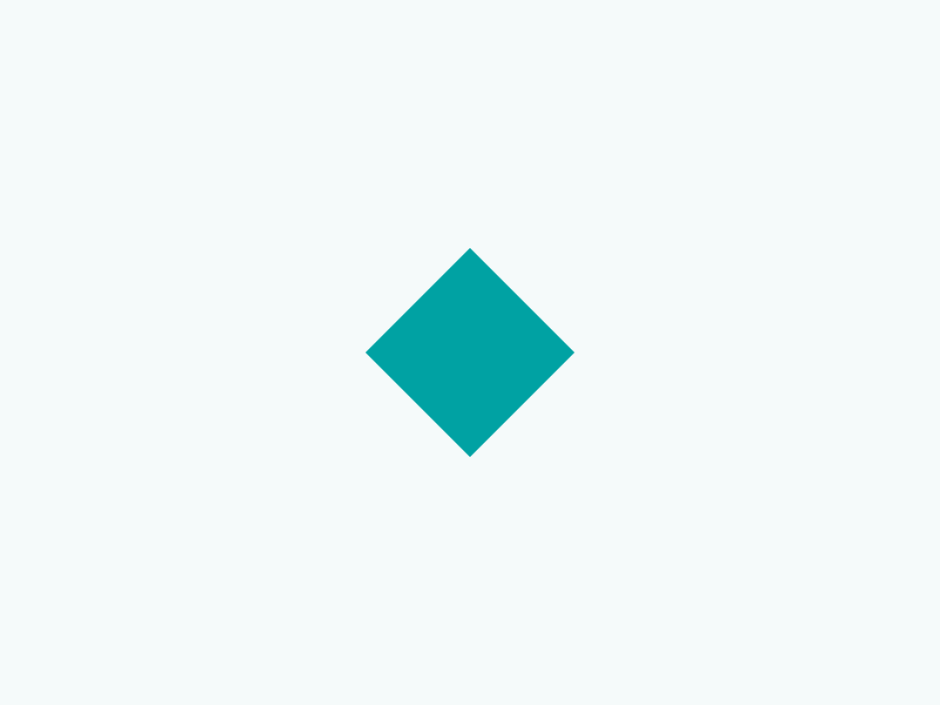
- Posted
- Fri, 01 Apr 2011
現職:早稲田大学大学院日本語教育研究科 教授
「おまえにそんな仕事ができるの?」というのが、私が大学に本務を移したと言ったときの、母親の第一声でした。日研着任が2005年4月ですので、6年ほど前のことになります。その意図するところは「大学生にいじめられないの?だいじょうぶ?」といったものでしたが…。「教えるのは大学院生だから、だいじょうぶなんじゃないの」と答えになっていない答えを返したのを覚えています。前職の若い同僚には「ワセダで何するんすか?ジョキョウジュ?女(じょ)教師みたいっすね、かっこいいっすね」と言われ、一瞬なんのこっちゃと思ったのですが、彼の頭の中では「女教授」と漢字変換がなされていたことにすぐに気づきました。「助教授」だよとの訂正には「なんすか、それ。教授を助ける仕事っすか?」とつっこまれましたが、自分でも答えはわかっていませんでした。
このように、アカデミズムとは無縁のところから、ひょっこり日研に来てしまい、当初は「日々是異文化体験」でした。詳細を述べていると紙幅が足りなくなるのは必定、なので、割愛いたします。しかし、今思うのは、教える人のオシゴトとして考えれば、日研のセンセイだってそれほど変わったものでもないかなということ。日本語教師として日本語の教室で様々な学習者に出会い、様々な学習を支えてきましたが、日研という学びの場でも、行うことにそれほど違いはありません。様々な学生の様々な学習と研究に向き合う、考えたことをことばにする、それは何のためかを明確にする…。
違いは、私の感覚です。日研に来るまで、教師の仕事は「教師が要らなくなるためにはどうすればよいか」を考えて実施することだと思っていました。しかし、日研に来てからは、まず、「要らなくなる存在として今はどうあるべきか」をより強く考えるようになりました。日研生との関係が「今ここ」の2年間に限定されているからではなく、むしろ、「今ここ」で日本語教育について何を考えるかが、「次」の深さを決めると感じるからです。日本語教育の世界が広く深くなっている現在、日研生には今ここで、とことん考えてほしいと思っています。オシゴトとしての日研のセンセイを6年やり、私も、今なら「なんすか、それ」に答えられるつもりです。
