- その他
- 井口翔子(日研修士15期生)
井口翔子(日研修士15期生)
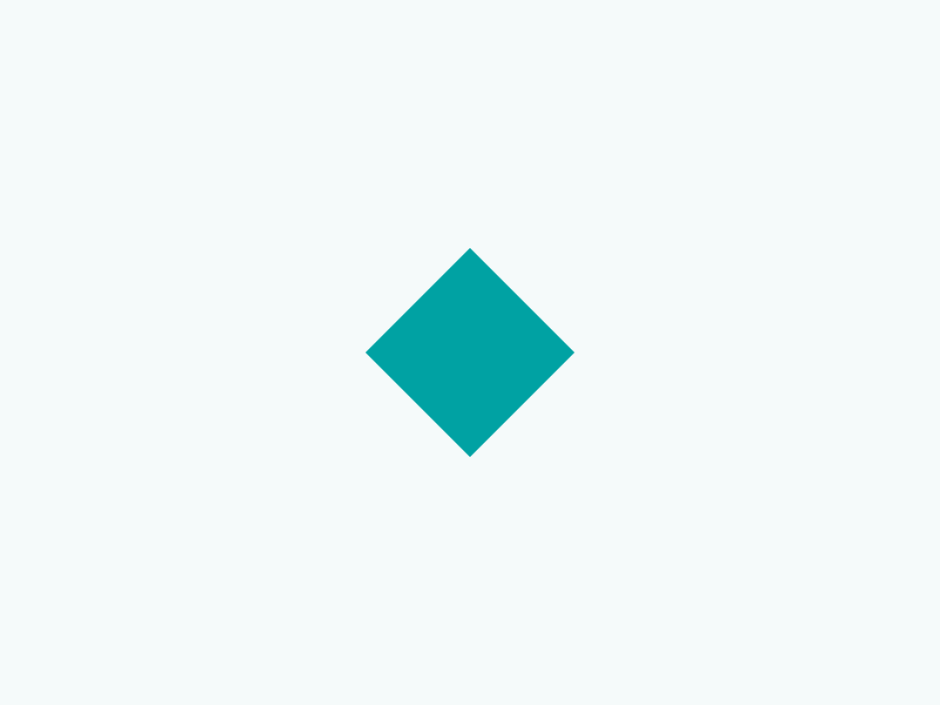
- Posted
- Fri, 01 Apr 2011
現職:現地法人ドミニカ日系人協会 ドミニカ共和国日本語学校 教師 『人間の移動から言語教育へ』
人が移動しようとするとき、そこには学びがあります。そして、その移動に言語の境界がともなうとき、そこには言語の学びがあります。このことが、わたしが日研で日本語教育を学びたいと思った最初のきっかけでした。
わたしが初めて日本語教育というものを知ったのは、ラテンアメリカの日系人社会における日本語教育の存在を知ったことがきっかけです。しかし、そのことを知った時、私が関心を持ったのは日本語教育よりも、むしろ、かつて日本人がラテンアメリカへ移住したという歴史と、そして現在そこで社会を形成し生活しているという事実でした。人間の移動、生き物としてあたり前の営みであるこのことに人間の大きなエネルギーを感じました。学部で文化人類学を学び、日本に暮らすラテンアメリカ出身の日系人の生活をテーマにフィールドワークを行ううちに、その子どもたちへの教育問題、とりわけ、言語教育が重要な課題であることを目の当たりにしました。このような視点をもって、日本語教育を学びたいと日研に入ったのがわたしの日研生活のはじまりです。
修士課程を修了した今、日本語教育の存在を知るきっかけとなったラテンアメリカの日系人社会で、日本語教育に関わることができていることを幸せに思います。大学に入ってから今まで私が勉強してきたこと、考えてきたことは、人間の移動から言語教育へとつながっていきました。
今、日本語教育は様々な社会的事象と深いつながりをもっています。中国・サハリン帰国者支援、インドシナ難民受け入れ、日系人労働者の増加、フィリピン、インドネシアとの経済連携協定、留学生30万人計画などです。日本語教育は、このような様々な分野や社会的事象と深い関係にあり、それぞれの分野や立場から日本語教育を考えることが現代の日本語教育を創造していきます。そして、そこに日研があるのだと思います。
