- その他
- 山﨑遼子(日研修士9期生)『日研との出会いと学んだこと』
山﨑遼子(日研修士9期生)『日研との出会いと学んだこと』
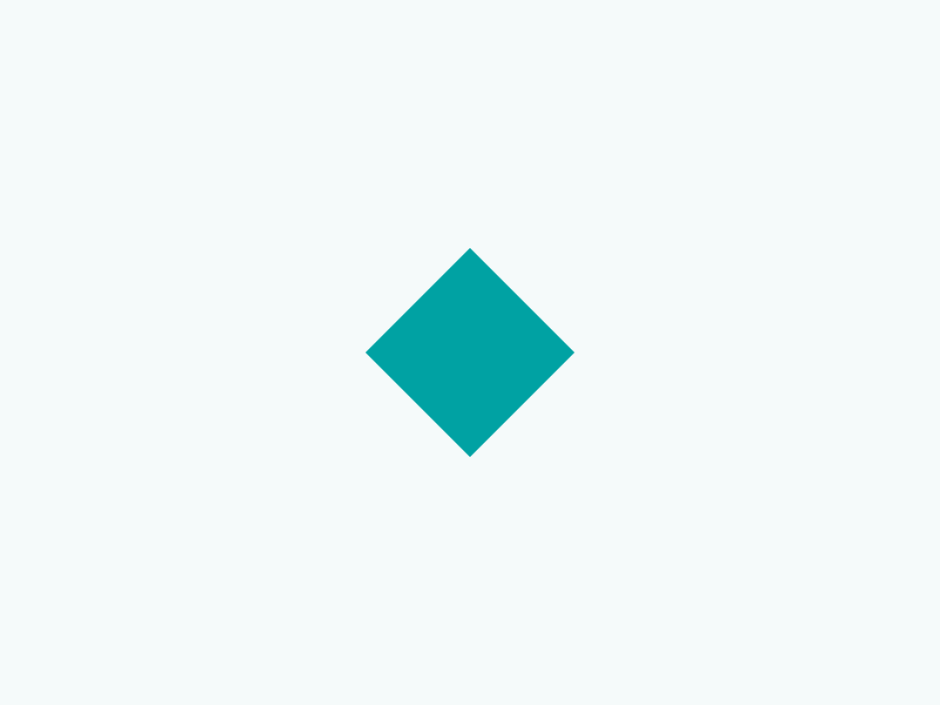
- Posted
- Fri, 01 Apr 2011
現職:早稲田大学大学院日本語教育研究センター インストラクター(非常勤)
すみだ国際学習センター 支援員
「へえー、こんな世界があるのか。」私が日研に興味をもったのは、細川先生が主催していた「ことばと文化の教育」について考える会に参加したことがきっかけだった。私は当時、大学4年生で、進路をどうしたいのかわからないまま、日本語教育の教材にまつわる卒論を書いていたところだった。そんなある日、卒論を書くために立ち入っていた22号館のエレベータ横に貼られたちらしを見て、ふと、こんな会もあるのか、と思い参加してみた。そこでは、一種の緊張感の中で話し合いが行われていた。沢山の他の参加者からの、「ことば」や「文化」にまつわる発言が、私の脳を働かせた。そしてついに私も、気持ちが高ぶり緊張しながらも自分の疑問をぶつけてみた。それは、「私も今思っていること発言してみようかな。そしたら、ここの人たちはどういうことばを返してくれるのかな」と期待がふくらんだから。そんな期待をさせた場の雰囲気に加え、私自身の無知による好奇心の強さがあった。そして、迷っていた進路に一筋の光が差した。
このようなきっかけで日研の存在を知り興味をもったのだが、入院(笑!)してからも、その期待は裏切られなかった。私は、自分にとって魅力の感じられたいくつかの研究分野の著作を読んだ後、最終的に川上先生の年少者日本語教育研究室を希望した。それは、自分が地元で子どもの日本語ボランティアをしていたこと、プラス、直接的に「社会につながる」研究ができると思えたことが決め手だった。が、いざ入院した日研では、領域を越えて学ぶことが可能だった。だから、子どもの日本語教育だけでなく興味のある研究領域にはとにかく全部体当たりしていった。そして、多様な分野における議論や書くという作業、教育現場での経験を通して考えたし、考えたことは私を変容させ、今でも私の価値観に大きな影響を与えている。今、日研で学んだ多くのこと(自分から考えて動くなどの行動規範、多角的な視点、学んだ理論など)は私の糧となっている。だから、それは私という媒体を通して、直接的にも間接的にも今結局「社会の現場で生きている」と思うのである。
