- その他
- 山内薫(日研修士11期生)
山内薫(日研修士11期生)
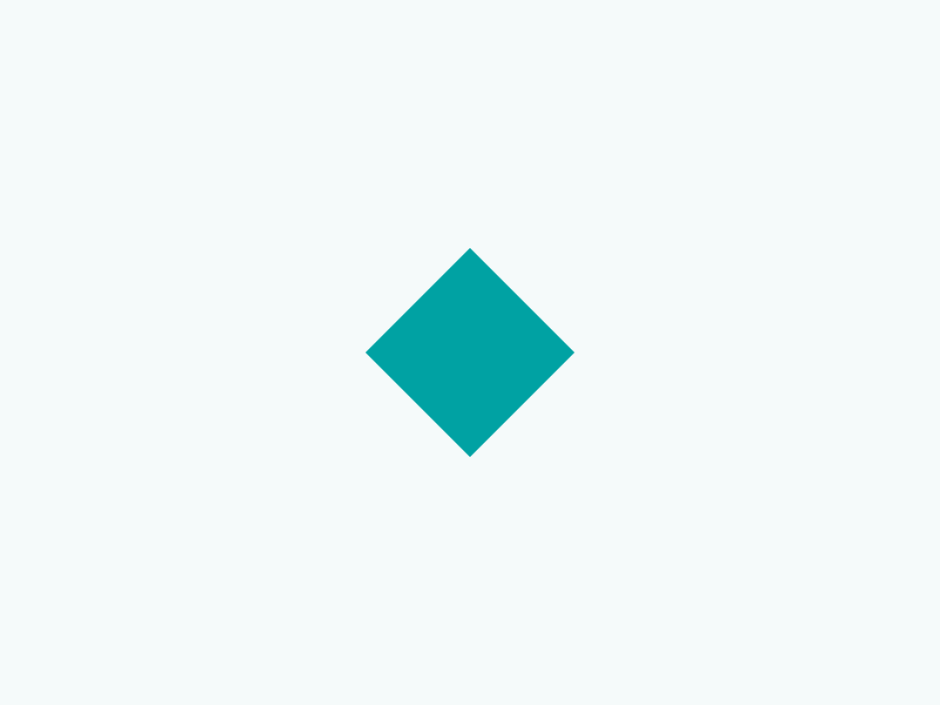
- Posted
- Fri, 01 Apr 2011
現職:フランス シャルル・ド・ゴール リール第三大学 常勤講師
日研の修士課程で一番強く残っている思い出は、仲間と応え合い、そして援け合いながら、ともに日本語の授業を創ったことだ。私が3期目に受講した「実践研究14-15-16」は、①日本語の授業を企画立案し、運営するための実践能力を高めること、また、②日本語センターの契約講師を担当することが可能な基礎能力を身につけることが、目的とされた実践研究であった。私たちのグループは、4期目で修士論文の執筆を始めた友人と私、他の研究室から3名が集まり、計5名で始まった。
それまで、私は、仲間と協働で、しかも何もないところから授業活動を創るという経験をしたことがなかった。グループの仲間と、それぞれの教育観を持ち寄り、ともに考え、話し合いを重ねた。時には、夜が明けるまで、教案や教材の推敲のためにメールを交わした。鳥の声を聴いて、ようやく、お互いに「そろそろ・・・」ということになった。一週間にひとコマだけの授業に、何十時間という時間を掛け、取り組んだ。授業活動がかたちを変えながら出来上がっていくことも嬉しかったが、なによりも、仲間と応え合える、その「いま」に、嬉しさと感謝を感じた。
4年後の今、当時の授業活動を振り返ると、見えていなかった多くのことに気付き、自身の未熟さが恥ずかしくなる。だが、仲間と応え合い、援け合った1学期間を通して、授業活動、そして、そこで仲間や学生たちと共有する時間が、その時々の「いま」にしか無い唯一のものであることを学んだ。今年度は、「実践研究14-15-16」の時の約10倍分の授業活動の企画立案、運営を一人で行うことになった。だが、一つひとつの授業活動は、学生たちや同僚の先生と、応え合い、そして援け合うことで、協働で創られていたと思う。私は、今後も、応え合いと援け合いを大切にしながら、実践研究を続けていきたい。
