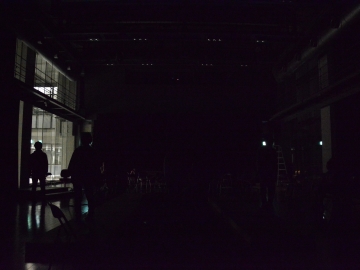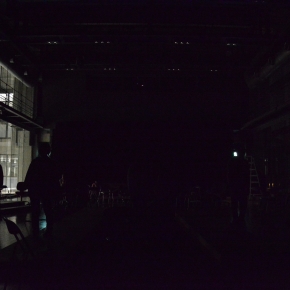2015年4月30日、早稲田キャンパス近くの南門通り商店街にグランドオープンした「早稲田小劇場どらま館」。すでに多くの団体がその舞台を彩ってきました。演劇研究・批評を専門とする演劇博物館助手による公演のレビューで、早稲田演劇の今をお伝えします。
Vol.7 2016年4月8日(金)~11日(月)
ヨハクノート『余白の音』
早稲田小劇場どらま館ではこの週末〔2016年11月19日(土)~21日(月)〕、「フェス早稲田シェイクスピア」の一環として学生劇団によるシェイクスピアの翻案劇、くらやみダンス×ヨハクノート『ロミオと俺とジュリエット』(以下『ロミ俺』)が上演される。(劇団)森を母体とする「くらやみダンス」は、9月に『スケルトンの呼吸』で「シアターグリーン学生芸術祭vol.10」にて最優秀賞を受賞し、名実ともに現在の早稲田演劇を代表する劇団の一つだ。2017年3月には、「2017道頓堀学生演劇祭」10周年メモリアル公演での大阪進出が決まっている。一方、劇団「こだま」を母体とする「ヨハクノート」を主宰する臼杵遥志は、早稲田の学生ではなく、立教大学現代心理学部映像身体学科でマレビトの会・松田正隆のゼミに所属。早稲田演劇にそのメインストリームとはまた異なる思考・作風を持ち込んでいる。『ロミ俺』ではくらやみダンスの岡本セキユが脚本を、ヨハクノートの臼杵が演出を担当する。今回は公演に先がけ、早稲田小劇場どらま館での本年度1本目の公演となったヨハクノート『余白の音』およびその後の彼らの作品のレビューをお送りする。

『余白の音』 撮影:飯田奈海
『余白の音』ではアメリカの劇作家ソーントン・ワイルダーの『わが町』を原案に、臼杵が作・演出を担当した(以下では『わが町』の核心部分に触れます)。『わが町』は第1幕・第2幕でグローヴァーズ・コーナーズという町の人々の日常を描き、第3幕でそれを死者の視点から捉え直す。死者は生者たちの生きる時間を見守り、あるいは自らが生きてきた時間を自在に追体験することができるが、決してそれに介入することはできない。自らの死によって生きる時間のかけがえのなさを痛感しても、それを残された生者たちに伝える術(すべ)はないのだ。『余白の音』の「展示上演」という形式はその切実さを観客に体感させる秀逸な演出だった。
- 『余白の音』 撮影:飯田奈海
劇場内に客席は置かれず、「床に描かれた正方形の枠外であればどこから見てもいいし途中で移動しても構わない」と開演前にアナウンスがある。大小3つの正方形は床の中央あたりに並んでおり、観客が移動できるスペースはかなり広い。俳優もまた、自らの出番でないときは観客と同じように床に座り込んで他の俳優の演技を見ていたりする。第2幕までは基本的に正方形の枠内を演技空間として物語は進んでいくが、第3幕でその枠内に入ることができるのは生者だけだ。死者は枠の外から見守ることしかできない。このとき、観客は自身が文字通り死者と同じ場所に立っていることに気づかされる。死者が生者の世界に介入できないのと同じように、観客もまたフィクションの世界に介入することはできない。その疎外感は死者たちの抱く喪失感と強く共鳴する。
『余白の音』は『わが町』を「原案」と呼ぶにはほとんど『わが町』そのものだった点が気になったのだが、そんなこちらの思いを見透かすかのように、臼杵は続けて『わが町』の演出にも挑んだ。

『わが町』
臼杵の卒業制作でもある『わが町』は2016年10月、立教大学新座キャンパスのロフト1で上演された。小さめの体育館ほどの空間に椅子が点在しており、観客はそれに自由に座って、あるいは移動しながら上演を観る。場内には演技空間となるであろう平台も点在している。おおよそ『余白の音』を踏襲した演出であるように思えたが、開演時間になり、機械音声のような言葉がスピーカーから聞こえてくると、一人が椅子からスッと立ち上がってポツポツと台詞を言いながら場内を歩きはじめた。俳優も観客に紛れて座っていたのだ。演技を終えた俳優は空いている椅子に再び座る。舞台衣装を着た『余白の音』の俳優は観客と同じ場所にいても明らかに異質な存在だったが、普段着を着た『わが町』の俳優は完全に観客に紛れてしまう。グローヴァーズ・コーナーズという町とそこに生きた人々の記憶、過去の記憶が観客の合間にふっと泡のように浮かび、そして消えていく。
第3幕になると場内の明かりが消え、照らされたいくつかの平台だけが浮かび上がる。生者の営みが照らし出される一方、ただ声が聞こえるのみの死者たちとともに観客は闇に沈む。生者と死者とが反転するがごとき演出によって、死者と観客との重ね合わせの効果はより劇的なものとなっていた。
- 『わが町』
作品が終わり全ての明かりが消えると周囲を覆っていた暗幕がゆっくりと開き、ガラス窓を通して外の景色が見えはじめる。外はもう暗い。わずかに差し込む街灯の明かりで場内の人々はみな影法師のようだ。俳優と思われる何人かが立ち上がり、同じ方向に去っていく。だが、その数が多い。半分近くの椅子が空いてしまった。立ち去った人々の顔は見えない。さっきまで隣にいたはずの人が、ふと気づけばいなくなっている——。今生きていることのかけがえのなさと、それがいつ断ち切られてしまうかもわからないはかなさにハッとさせられた。

『秒殺・ロミオとジュリエット』 撮影:飯田奈海
ヨハクノートは6月にも『ロミオとジュリエット』に取り組み、早稲田大学Museum liveの一環として演劇博物館前舞台で『秒殺・ロミオとジュリエット』を上演している(リンク先で動画視聴可)。昼休みのわずか15分で『ロミオとジュリエット』を上演する(と言いつつ一連の流れを3度繰り返すので実質5分で上演した)という作品で、ポップな音楽に乗せラップや方言を盛りこんだ台詞回しとナレーションを駆使した巧みなパフォーマンスで昼休みのエンパク前を盛り上げた(3度繰り返した効果がどれほどあったかはさておき)。くらやみダンスとタッグを組んだ『ロミ俺』ではどんな『ロミオとジュリエット』(?)を見せてくれるのだろうか。
(演劇博物館助手 山﨑健太)
関連リンク
【ご支援のお願い 】
早稲田大学は「早稲田小劇場どらま館」を早稲田演劇振興の中核的拠点と位置づけ、早稲田演劇の伝統を継承・発展させ、優れた演劇文化を発信し、教育 を通して、次代を担う演劇人を多数育成することを目指しています。「早稲田小劇場どらま館」を核に、早稲田の新たなコミュニティが形成されることを願い、 これを実現するため、多くの皆さまのご支援を得るべく、「WASEDAサポーターズ倶楽部」を通じた募金「早稲田小劇場ネクスト・ジェネレーション募金」を募集中です。
ご寄付は、学生のため、演劇教育に資する目的のために使用いたします。早稲田演劇振興へのお力添えをいただける皆さまの温かいご支援を心よりお願い申し上げます。