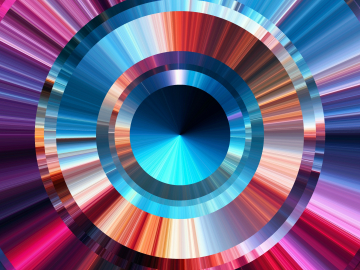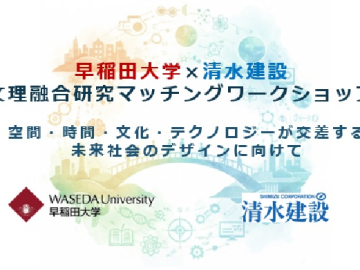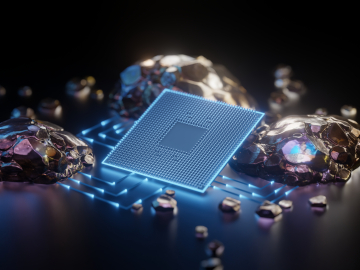早稲田大学では、独創的研究の推進と国際的な情報発信力の強化を目的として、早稲田大学リサーチアワードを設け、大規模な研究を主導的に推進している研究者を「リサーチアワード(大型研究プロジェクト推進)」として、国際発信力の高い研究業績をあげている若手研究者を「リサーチアワード(国際研究発信力)」として表彰しています。
2024年度からは、これに加えて、独創的な研究で本学を先導している研究者を「リサーチアワード(独創的研究推進)」として表彰しています。
独創的研究推進(Leading Research)
正賞(賞状)ならびに副賞(独創的研究推進は賞金50万円)が授与されます。
独創的研究を先導して推進している研究者を表彰します。
早稲田大学リサーチアワード(独創的研究推進)受賞者
WASEDA RESEARCH AWARD(Leading Research)
(50音順)
石原 千秋
石原千秋氏は日本近代文学の分野で、文学作品の評論を中心に多くの著述を世に送り出している。特に夏目漱石の小説を近代社会の諸相に照射して論点を汲み上げる手法については他者の追随を許さない独自の領域を展開している。代表的な著述として『漱石と日本の近代』(新潮選書、2017 年)をあげることができる。それらが科学研究費のプロジェクトとしてなされる点も注目され(既に 6 度にわたって採択)、大学およびその周辺で研鑽を積む人文系若手研究者の指針となっているといえよう。作家の個人的な情報を使わずに、作品に書かれている表現に焦点をあててその構造や意味を解釈する立場を取り、小説を当時の社会や時代の文脈の中で解釈するアプローチへと広がっている。一例をあげれば、「明治・大正期文学における進化論・退化論パラダイム表象に関する総合的研究」(基盤研究(C)、2021 年‐2024 年)がある。マックス・ノルダウの退化論の観点から、夏目漱石の文学を手掛かりに、近代文学と文化について再検討するものであり、日本近代における社会構造の問題点を浮かび上がらせることに成功している。
従来の文学評論に見られた「物語的主人公」ではなく、謎を感じ、謎を前に立ち止まざるを得ない「小説的主人公」という概念を定位し、二葉亭四迷の『浮雲』以来の近代小説の流れの中で新たな漱石作品の位置づけに成功した点は高く評価されるものである。
大島 登志男
大島登志男氏はcollapsin response mediator protein 2 (CRMP2)というタンパク質を軸足に、CRMPファミリータンパク質の脳神経系における役割を神経再生や神経変性疾患等に幅広く展開している。CRMP分子のリン酸化、脳や視神経における神経細胞の再生、神経軸索ガイダンス、神経細胞のポジショニング、軸索刈り込み、神経変性疾患の症状改善など多岐に渡り、実験モデル系もゼブラフィッシュ、モデルマウスの視神経や脳組織で、独創性と独自性に優れた研究展開を行っている。ここ10年で50本以上の高評価の国際誌のほとんどを論文責任者として発信し、この分子の多疾患における役割解明に向け共同研究も展開している。本研究は、アルツハイマー病やパーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症といった神経変性疾患の治療に役立つ可能性があり、社会的にも大きな波及効果が期待される。
大須 理英子
国内外を問わず、外界がどのように内部表象(内部表現)されているかの研究の歴史は長い。一方、人間が何らかの運動を通して外界に働きかける際の心的(または神経科学的)アウトプットが内部表象や脳のメカニズムにどう関係するかの研究が大幅に立ち遅れた。大須理英子氏の研究はその立ち遅れたフィールドで独創的仕事をし、当該のフィールドの牽引的役割をしている日本では数少ない研究者の一人である。計算論的神経科学的理論を背景に感覚運動系の病理(リハビリテーションを含む)に関する独創的研究もあり、心理学、、認知神経科学、計算論的神経科学、医学に亘りインパクトのある研究を継続している。今回のアワードの受賞者として申し分ない。
川西 哲也
川西哲也氏は、高速多値光変調器における世界的なパイオニアであり、近年ではそれを基盤とするマイクロ波フォトニクス、さらに、これらを発展させた光電波融合の研究を進めている。こうして開発された高速多値光変調器は超大容量ディジタルコヒーレント光通信向けに実用化されており、光電波融合についても今後の6G/7Gの実用化に欠かせない技術となっている。これらの取組みは将来の社会インフラに求められる要求条件を先見し、その解決指針と必要な実現技術を網羅的に示すものであり、研究者間の連携と新たな研究領域における技術確立の促進にも資する、極めて優れた研究活動である。これらの成果は、被引用数が100を超える多くの論文を含む多数の論文として発表されている。
一方、氏は、学術的な発表だけでなく、光変調器の必読書となっている書籍を日本語および英語で出版し、最近では光電波融合に関する書籍を英文で出版するなど、学問の普及にも注力している。政府・学会でも活発に活動しており、学術賞も多数受けている。
日野 愛郎
日野愛郎氏は、選挙研究、投票行動、政党研究、現代民主主義研究を専門とする。その知的厳密性と社会的関連性の高さから、政治学分野で卓越した学術的影響力がある。ポピュリズム、有権者行動、制度設計などの社会的に重要な喫緊のテーマに取り組み、政治現象の解明に多大な貢献をしており、国際的にも際立った存在である。特に、最先端の統計的手法を適切に応用し、立法演説やソーシャルメディアデータの分析は革新的であり、従来の研究方法論の枠を超えた独創的な成果を挙げている。また、国際的に権威ある学術誌への多数の論文発表を行い、招待講演、共同プロジェクトへの参加を通じて、研究の普及と政治学界および公共の場において高い評価を得て、その影響力をさらに広げている。これらの成果に加え、競争的研究資金の獲得や国際共同研究プロジェクト等での指導的役割を担うなど、日本および世界の政治学の発展にも大きく寄与している。
宮地 元彦
宮地氏は、身体活動と食事が健康に及ぼす相互作用を生理学や疫学の手法を用いて明らかにするヒトを対象とする実践的な研究を精力的に進めている。例えば、骨格筋のアンチエイジングに効果的な運動・食事療法の開発、健康や疾病における腸内マイクロバイオームの役割の検討など、大変タイムリーで独創的な研究課題に取り組んでいる。それらの研究は、学術性の高さと共に現代社会の健康問題に直結したものであり、健康寿命の延伸の実現に繋がる大きな社会貢献が期待できる。また、研究方法においても、共同研究の組織化など、今後ますます重要となると考えられる独創的研究スタイルを構築していることは高く評価できる。研究成果の発信力の点においても、国際的トップジャーナルへの論文掲載数、被引用数などにおいて申し分ない成果を出している。被引用数が非常に高い論文を多く発表していることからも、氏の研究に対する国際的な評価の高さが分かる。以上のことから、氏は早稲田大学リサーチアワード(独創的研究推進)を受賞するにふさわしい。