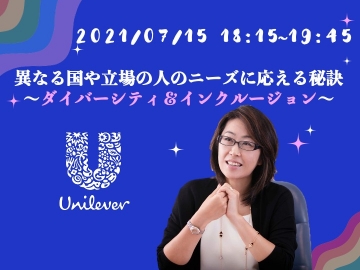政治経済学部 徳山 佳孝
スターバックスから学ぶdiversity and inclusionの講演では、スターバックスが多様性を認め合うための取り組みや、サイニングストアnonowaで働く方から、これからの私たちに求められる姿勢を学ぶことができました。
中でも印象に残っていることが2つあります。1つは、inclusionが指している本当の意味です。私は自分、あるいは自分たちとは何かしらが違った相手と関わる際、自分との違いを認識したうえで、相手を受け入れること、そして相手にとって心地よい環境を作っていくことが正しいと思っていました。もちろん、この姿勢が間違っているわけではないと考えています。しかし、この姿勢では、自分にとっても相手にとっても、「違い」という障壁は消えず、自分と相手が本当の意味で混ざり合うにはほど遠いものだと感じました。真のinclusionはその「違い」という障壁を取り除き、いつも通り自然に関わることです。誰かが特別になる必要はなく、普通の1人としていられる状態がinclusionの理想形であると感じました。
2つ目は、inclusionを考えるうえで示された傘の例えです。雨が降ったとき、中に人を入れてあげるとする。ただ、その傘は大きければいいというものではない。大きすぎると逆に、居心地の悪さを感じてしまうというものです。これは日常生活において、相手への過剰な配慮に当てはまると考えます。相手が自分とは違うと感じたとき、人は必要以上に相手のことを考えてしまう傾向にあるかもしれません。これは決して悪いことではありません。ただ、こちらが歩み寄りすぎたせいで、相手がこちらに歩み寄る道を閉ざしてしまっている可能性があると感じました。
これまでの傾向として、私たちは人々を「自分たち」と「そうでない人たち」の2つに分けていたと思います。そして、自らを多数派と感じた場合、少数派を迎え入れる姿勢をとっていたでしょう。ただ、国際交流が活発化し、一人一人がより多様なバックグラウンドを持つことで、今までの「多数派、少数派」という考え方はもはや通用しなくなっていくと感じます。そしてこれからはより一層、インクルージョンの考え方が大事になってくると考えます。むしろ、一人一人がより個別化されることで、互いに歩み寄りやすくなるのではないでしょうか。大きなグループに入っていくのは体力がいるかもしれませんが、一人一人が互いに混ざり合う状況はそれぞれにとって楽しいものであると思います。これからの社会は、多様であることはもはや当たり前で、インクルージョンがより実現しやすくなっていくと信じています。
最後に、このような社会を実現するうえで人々に求められることは何でしょうか。私は、常に新しいことに挑戦することだと考えます。様々な状況を経験することで、自分のバックグラウンドを広げていけることはもちろん、相手を知る上での土台となるからです。自分が知らないから、相手は違う人となるのであって、自分が知っていれば、相手との差という名の壁を感じることは少なくなると思います。今回の講演を通して、私自身も、1つ壁をとり除くことができたと実感しています。