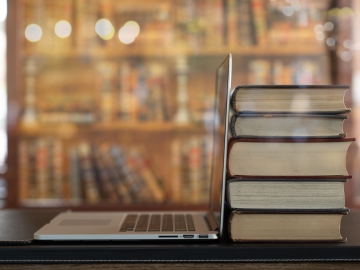歴史に学び、未来へつなぐ 「法実務と学知の交錯」の実践
100年前、近代日本の法制・法学教育と東アジアの法整備に多大な業績を刻み、膨大な知の集積を文書に遺して去った民法学者、岡松参太郎。長い歳月を経て光を見たその歴史的資料の解析と次代への継承を使命として、東アジア法研究所の活動は始まりました。研究の端緒を開いた浅古名誉教授と、現在の所長を務める和仁教授にお話を伺います。
◆知られざる「岡松参太郎文書」との邂逅に始まった研究活動
──「東アジアにおける法制と法文化の研究」をテーマとしておられます。具体的にはどのようなご活動ですか。
和仁:簡潔に申し上げると、「日本統治時代の台湾・朝鮮の法院などの記録史料の蒐集・整理・公開」と「植民地統治関係者の文書資料の整理・保存・公開」を中心に活動しています。現存する日本の植民地統治に関する法制資料を広くさまざまな研究に役立てていただくべく、学界共通の財産として整備・構築することが主な狙いです。同時に、「法実務と学知の交錯」を促す観点から、近代日本の法と法律学・教育学の発展について、また日本の植民地経営と法制度が東アジア諸国の法に与えた影響などについても研究を行っています。

『早稲田大学図書館所蔵 岡松参太郎文書目録』(丸善雄松堂)、『岡松参太郎の遺緒』(成文堂)など研究成果の一端は出版され、一般にも公開されている。
浅古:「法実務と学知の交錯」とはつまり、現実の裁判や政策立案・立法などといった法にまつわる実務の世界と、法律学や歴史学などの学問における成果がどう結びついているか、ということです。それらを研究・検証することが、現代の、またはこれからの法制や社会のあり方を考えることにもつながるわけですね。
──そうしたご活動の成果の一つとして、今年(2024年)8月に『岡松参太郎の遺緒』を出版されました。どのような研究によるものでしょうか。
浅古:この研究所が発足した経緯にも深く関わるのですが、日本の民法解釈学の道筋を切り拓き、台湾の統治に関わるなど明治・大正期に活躍した岡松参太郎が遺した蔵書や文書の数々を、ご遺族が早稲田大学図書館に寄贈してくださったことに端を発します。1999年のことですが、岡松が没した1921(大正10)年以後、約80年にわたって公開されることなく岡松家の書庫に保存されてきたものを、自宅建て替えを機にご提供いただくことになりました。約7000冊もの図書と、書架に並べて15mにも達する文書群からなる膨大な資料です。
そこには、卓抜した研究者であり希代の読書家でもあった岡松自身が作成・蒐集・整理した学術資料や台湾統治などに関わる記録のほか、幕末から明治にかけての著名な儒学者・教育者であった父・岡松甕谷の資料も含まれ、近代日本の黎明期における多彩な分野を網羅した、極めて学術的価値の高いコレクションでした。
寄贈のご相談は当初、国立国会図書館が受けたのですが、寄贈には目録が必要で、その作成に大変な労力と時間が伴うことがわかり、ご縁を得て早稲田大学図書館にご寄贈いただくとともに、我々法学部などの研究者が資料の整理・研究を受け持つことになりました。ちょうどその頃、専門領域の垣根を超え、多様な研究者が協働する場として発足した「プロジェクト研究所」の仕組みに乗り、この東アジア法研究所を立ち上げることにしたのです。
和仁:岡松文書のような膨大かつ広範な資料の目録を作るには、さまざまな領域からのアプローチが必要ですし、数年単位の時間を要します。実際、法律学の各分野はもとより、歴史学、政治学、地域研究といった各界の専門家が他大学や法曹界からも集い、文部科学省の科学研究費補助金を得て研究チームが組織されました。私自身、2012年からの参画ですが、当時は他大学に籍を置きながら主に法制史の面から研究に携わりました。
◆「社会あるところに法あり」を実践した岡松の叡智に学ぶ
──岡松参太郎は日本の法制史を語るうえで欠かせない人物なのですね。東アジアとの接点はどこにあったのでしょうか。

和仁かや(所長/法学学術院教授)
和仁:岡松は二十代でドイツ、フランス、イタリアに渡って民法・国際私法を修めた後、京都帝国大学法科大学(現 京都大学法学部)の開設と同時に民法学の教授を務めます。『無過失損害賠償責任論』などの優れた著作で知られ、ドイツ流の法解釈を日本で発展させた学者ですが、一方では、日清戦争後に台湾総督を務めた児玉源太郎や台湾総督府の民政長官だった後藤新平らの要請を受け、台湾における法の整備に力を尽くした人でもありました。
浅古:清国から割譲された台湾は、日本が持った初めての植民地です。統治の仕方をめぐってはさまざまな意見の対立があり、日本国内の法律をそのまま適用すべきだとする「内地延長主義」と、日本とは言語・人情・風俗などを異にする台湾にそれは適さないとする「特別統治主義」が対立します。結局、後藤新平らが主張する後者が採用され、それにはまず現地の慣習を調べる必要があるとの認識から、主導者として岡松に白羽の矢が立ち、台湾旧慣調査事業が始まったのです。1899(明治32)年のことでした。
岡松はその後20年近くにわたり、満鉄総裁となった後藤新平に乞われて満鉄理事を務めながらも台湾の旧慣調査を続け、法案の作成や政策立案といった統治体制づくりに深く関わります。ただ、内地延長主義を掲げた原敬が1918(大正7)年に首相に就くと情勢は変わり、岡松が心血を注いだ旧慣調査とそれに基づく台湾民事法典の立法努力は実を結ばないまま終わってしまったのですが。
──今思えば、その土地の文化や生活に根ざしてこその法や社会の仕組みといえそうですが。
和仁:そうですね。「社会あるところに法あり」という言葉がありますが、どのような社会を前提とするかによって、法のあり方はまったく変わってきます。その意識なくして法制度は成り立たない。今では当然のようにも思えるその思考を追究した岡松の問題意識は、まさに古くて新しい、非常にアクチュアルなものだったのです。
私たちは今、社会で起こるありとあらゆるレヴェルの問題を法律と司法によって解決し、ルールとして明文化する法化社会へと向かいつつあります。その中で、慣習というものに対してどのような姿勢で臨み、その中から何を、そしてどのレヴェルのルールとして位置づけるかは非常に難しい問題です。岡松が100年前に取り組んだその試みは、今を生きる私たちにも多くの面で示唆を与えてくれるものだと思います。
◆日本統治時代の東アジア裁判記録に見る時代の諸相
──岡松文書の目録作成から始まった研究所の活動は、その後どのように発展していかれましたか。
浅古:寄贈いただいた文書の整理と目録の採録には9年かかりました。2008年に『早稲田大学図書館所蔵 岡松参太郎文書目録』『マイクロフィルム版 岡松参太郎文書』として雄松堂(現 丸善雄松堂)から出版され、一般公開することができました。岡松参太郎文書のような史料は政府が持つ公の記録とは異なり、その作成や運用に携わった人間によるさまざまな書き込みがあったり、完成するまでの草案が含まれていたりして、当時の情勢や考え方を知るうえで非常に重要な意味を持つわけです。

浅古 弘(顧問/早稲田大学名誉教授)
岡松参太郎文書をもとに着手した、日本の植民地統治や東アジアにおける近代法成立についての研究が次のステップです。それを進めるために台湾に行き、遺された台湾総督府関連の資料などを調べるうち、偶然にも、台湾法務部司法官学院(旧司法官訓練所)に保管されていた日本統治時代の台中地方法院の刑事裁判記録を見ることができました。当時、司法院(台湾の最高司法機関)の副院長を務めていた早稲田の卒業生をお訪ねしたことからの引き合わせです。また同じ頃、台湾大学法学院の王泰升教授が裁判記録のデータベース化に取り組まれることを知り、台湾大学所蔵の画像データとも合わせて目録作成事業を共にすることになりました。また、千種達夫や宮内季子のご遺族から文書を早稲田大学図書館にご寄贈をいただき、整理・目録作成をしました。
和仁:実は韓国にも日本の朝鮮総督府が置かれた時代の裁判記録が残っていて、その調査と整理も研究所の活動として進めてきました。これらを比較検討することにより、帝国日本によるかつての植民地統治の実像に迫ることも可能になります。
もちろん、歴史の見方にはさまざまなスタンスやアプローチの仕方がありますが、私たちは法学に立脚しながら歴史学にも依拠し、その地域における法の世界の成り立ちを見ていく。そこには政治や経済との絡みも密接にあり、さまざまな分野からの検証が求められるのです。
──そういった多面的な要素を内包しながら一つの集大成としてまとめられたのが、『岡松参太郎の遺緒』なのですね。
和仁:はい。ここ数年にわたる研究所の活動成果の、いわば中括として、2022年11月に「岡松参太郎⽣誕150年記念国際シンポジウム:東アジアにおける植⺠地法制と学知」を開催しましたので、その内容を踏まえて書籍化したものです。これを足掛かりとして、岡松が現代に投げかけているさまざまなテーマ、例えば法制度、法化社会、あるいは大学制度に関わる諸問題を取り上げて、引き続き考察を深めていきたいと考えています。
◆デジタル時代に考える、価値ある資料・学術成果の遺し方
──先生方ご自身としては、特に関心を寄せている研究テーマはありますか。
和仁:法化社会との関わりでいえば、慣習調査の実態についてはもう少し踏み込んでいきたいと思っています。実は私の主な専門は江戸時代の法制史ですが、琉球法制史にも興味を持って取り組んできました。琉球は台湾との交流も深く、その関係性が互いの慣習や法制度にどのように影響したかとの関心からも、この研究所の活動にも加わることになりました。明治初期の日本でも、西洋から法制度を持ち込む際に慣習調査を行っています。幕藩体制下において千差万別の違いが見られた各地域の慣習を、どのようにして新しい国家の法制度に集約していったのか。そういった研究からも、現代に生かせる視点が得られるのではないかと考えています。
浅古:私としては、岡松参太郎文書の翻刻作業が大きな宿題だと思っています。岡松の文書は非常に読みにくい文字で書かれたものが多いので、読み解くのが難しいのです。これではせっかく公開しても、多くの研究者に活用していただけない。それをきちんと読めるように翻刻し、活字化する取り組みを進めていかなければと考えているところです。
──2023年開催の「法制史学会第74回総会」では、そうした次代への継承を見据えた議論が行われました。
和仁:はい。この法制史学会総会には東アジア法研究所も共催で参画し、浅古先生や私が企画したミニシンポジウムで「紙媒体資料・蔵書の継承」と「裁判手続IT化時代の課題」をテーマに取り上げました。私のほうでは、デジタル化の飛躍的な進展の裏側で紙媒体資料の価値や位置づけが置き去りにされかねない状況を危ぶむ問題意識から、その重要性を確認し、継承を促すための意見を交わしました。
新しい研究成果を発信することだけが、研究者の役割ではありません。価値ある歴史的な資料なり情報なりを確実に次代へとつなぐことも、同じように大切です。今の価値観では不要として捨てられてしまう資料の中に、もしかしたら100年後には価値を持ってくるものがあるかもしれない。デジタル化が所与として定着しつつある反面、紙媒体に対する若い世代の感覚が失われつつある時代に、いかにしてその危機感を訴え、保存・継承にかかる基準を作るか。重要な課題だと思っています。
浅古:そうですね。民事や刑事の裁判記録には「特別保存」や「刑事参考記録」の制度があり、例えば、民事事件で重要な憲法判断が示された事件の記録は「特別保存」として残すべきとされています。ところが、実態はその8割以上が廃棄されていることが明るみに出て、「特別保存」の判断が裁判所に委ねられていることが問題になりました。そのため、今年(2024年)初めに「特別保存」を徹底する新しい制度ができたのですが、そもそもその時代に特別な意味を持つ事件の記録だけを残せばそれでいいのか、というのが私の問題意識です。
未来の人が100年前の裁判記録を見返したとき、その時代の社会相や裁判の傾向が多くの事件から読み解けるよう、特別な意味を持った事件に限らずすべての記録を残すべきではないか。紙媒体の場合、それは物理的に現実的ではないので、一定の割合を残す「サンプル保存」という考え方が有効だろうし、電子媒体なら全記録を残すことも不可能ではないでしょう。すでに民事訴訟手続きのIT化は始まっていますが、デジタル化された記録をどう残し、どう閲覧するかのルールづくりはこれからです。ミニシンポジウムではそうした課題について話し合いました。
──最後に和仁先生、所長としてこれからの抱負をお願いします。
和仁:これまでの研究成果や学術資料を活用して、若手も含めた多くの人が、「今すぐに役に立つかどうか」のみに囚われず、それぞれの研究課題に取り組める基盤となるような環境づくりを進めていきたい。この研究所の究極の目標はそこにあると思っています。

(左)和仁かや 所長/早稲田大学法学学術院教授 (右)浅古 弘 顧問/早稲田大学名誉教授