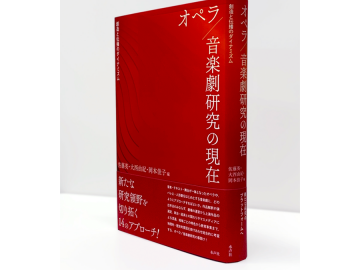▼2022年11月研究例会(第206回オペラ研究会)
- 日 時:2022年11月5日(土)16:30 – 18:00
- 開催方式:オンライン開催(Zoom使用)
※ 事前申し込みが必要です。参加希望者は11/2(水)までにこちらのGoogleフォームから、ご氏名、所属、連絡先(メールアドレス)を記入してお申し込みください。前日(11/4)にフォームに入力したメールアドレスに招待メールをお送りします。(現在は終了しております。)
※ ご出席の際お名前の表示をお願いします。カメラをonにする必要はありません。
発言時以外はミュートにしてください。 - 発表者 : 大西 由紀
- 所属・資格:大東文化大学文学部日本文学科 講師
- 題名 : 「大団円はオペラ座で──日本の洋楽系音楽劇受容の初期において繰り返し使用されたプロットについて」
- 発表言語 : 日本語
- 概要:
本発表では、日本の洋楽系音楽劇の受容史研究において言及されることの多い3つの音楽劇作品について、プロットが互いに似通っていることに注目して再読する。ここで取り上げるのは、外国人の旅回りの一座によるオペレッタを劇中劇として挿入した河竹黙阿弥の歌舞伎『漂流奇譚西洋劇』(1879)、益田太郎冠者が川上貞奴の一座のために書き下ろし、のちに帝国劇場でも改訂上演した『唖旅行』(1908/1914)、宝塚少女歌劇初のレヴューである岸田辰彌の『吾が巴里よ(モン・パリ)』(1927)の3作品である。いずれの演目も、日本人の一行が世界を旅し、言葉や習慣への不案内からトラブルに遭い、はぐれる者も出るが、最後にはパリまたはロンドンのオペラ劇場またはミュージックホールで再会し、皆で演し物を楽しむ、というあらすじに沿っている。このプロットの類似は、過去の研究者にも手短に言及されてはきたが、3作品を突き合わせての精査は行われていない。本発表はこの点に改めて着目して台本や同時代評などの現存資料を読み直し、プロットの類似がなぜ起きたのかを推測するとともに、3作品の相違点にも注目して、演目ごとの特徴を明確にする。
- 発表者プロフィール:
東京大学大学院総合文化研究科博士後期課程修了。博士(学術)。2022年より大東文化大学文学部日本文学科講師。専門は比較文学・翻訳論。日本において20世紀初頭から始まったオペラ/音楽劇の受容について、とりわけ台本の翻訳と翻案に注目して研究している。著書『日本語オペラの誕生──鷗外・逍遙から浅草オペラまで』(森話社、2018年)で日本演劇学会河竹賞奨励賞および日本比較文学会賞を受賞。共編著に『オペラ/音楽劇研究の現在:創造と伝播のダイナミズム』(佐藤英・岡本佳子との共編、水声社、2021年)。 - 司会者 : 葛西 周
次回例会開催予定日
次回例会開催予定日:2022年12月3日(土)
報告者: 大矢 未来
司会者: 釘宮 貴子
e-mail address: operaken-uketsuke[at]list.waseda.jp ( [at] = @)
(この例会案内は後ほど Facebookと Twitterでも発信されますので、そちらでも見ることができます。)