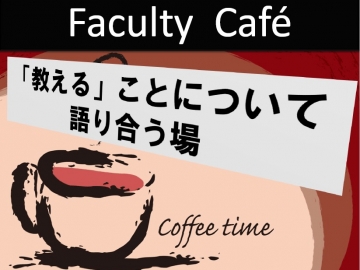2021年度秋学期ティーチングアワード
総長賞受賞
対象科目:Introduction to Political Analysis 01
受賞者:河野 勝
アメリカやカナダの大学では、学部の一年生を対象にした入門レベルの授業は大教室での講義と少人数によるディスカッションとを併用することで理解を深めるスタイルが一般的だという。河野教授は、これをオンラインでもうまく機能させるべく、講義内容を確認する小テストを毎週実施したり、ディスカッションでの発言を学生に相互評価させるなどして、基礎的な知識と理解が深まる授業を実現している。
ベストパフォーマーを推薦させるシステムで、発言を活性化する
この授業は、政治経済学部の英語プログラムEDESSAの一年生全員が受講する必修科目だ。政治学の主要な理論や重要な実証的知見を概観できるよう組み立てられている。
実は、河野教授はほぼ同じ内容の「政治分析入門」という日本語の授業を、その立ち上げから関わり長年教えてきた。今回は、英語プログラム担当の教員がサバティカルを取ったため、代役として受け持つことになった。講義とディスカッションをそれぞれ週1回行う北米スタイルの構成は、日本語の授業でも採用していた。ところが2021年度のこの英語の授業では、コロナ禍の下、来日できない海外留学生を考慮しすべてをオンラインで実施することとなった。非対面でのディスカッションに、どう学生を積極的に参加させるか。それが最大の課題だった。
そこで、河野教授が新たに取り入れたのが、学生同士の相互評価システムである。「毎週、ディスカッションで一番良い発言をしたと思った学生を1人選んで、私に推薦するメールを送ってもらう。学期を通して推薦される回数が多い人には、ボーナスで評価に加点することを約束しました」。友人同士が安易に推薦し合うのを防ぐため、氏名だけでなくなぜ良いと思ったかという推薦理由も記入させた。「オンライン上では、学生はほぼ全員がカメラをオフにしており、真っ黒な画面を前にした状態でしたが、この仕組みがうまくインセンティブとして働いたのか、心配していた割にはディスカッションが活発だったと思います」。
ディスカッションを活性化する工夫としては、当日話し合うテーマを事前に公開しておいた点も挙げられる。「発言回数や内容も成績に反映されるので、中には話す内容をきっちり準備して読み上げる学生もいました。大学に入ったばかりで多くの学生のモチベーションが高かったおかげもあるかもしれませんね」。
理解度確認の小テストで、オンデマンド講義視聴のモチベーションを上げる
ディスカッションセッションは、履修生を3つのグループに分け、2人の大学院生もTAとして進行役をつとめた。「学生は教授相手よりも歳の近いTAに対しての方が、気軽に質問したり意見を言えるものです。今回はTAが2人しかいなかったので私も参加しましたが、本来はディスカッションを仕切るのはTAに任せて、私はそこで出てきた質問に答える役に徹したがいいと考えています」。
グループは日本人も留学生も偏らないよう考慮して分け、3人のディスカッションリーダーはローテーションで交代した。「今回の受賞は、二人のTAの貢献なくしてはありえませんでした。感謝しています」。
ディスカッションで気をつけているのは、個人の思想や信条、特定の政党や党派のプロパガンダを語る場にしないことだ。「政治(の授業)ではなく政治学、の授業なのですよ、だからイデオロギーや主義主張をぶつけ合うのではなく、科学的にエヴィデンスに基づいた発言をしましょうと、初期の段階からかなり厳しく伝えました」。
場があまり盛り上がらないなと感じたときに備えて、予備のトピックを用意しておくのもポイントだ。「あらかじめ決めてあった2、3のテーマに加えて4、5個考えておいて、じゃあこれはどう思う?と投げかけることもありました」。
オンデマンドの講義動画は、ディスカッションセッションに参加する前に視聴することを義務付けている。セッションの7日前までには講義動画と関連資料がアップロードされ、その期間に95%以上視聴した履歴を以て出席の扱いとした。「海外でWi-Fi事情の悪い地域もあることを考慮し、動画はできるだけ短めのクリップに分割するようにしました」。
ディスカッションセッションの冒頭に、講義動画の理解度を確認するための小テストをMoodle上で実施。ノートや資料を参照してもよいが、学生同士が相談することは当然ながら禁止とした。「視聴履歴だけでは、講義動画を真剣に見ていたかどうかはわかりません。5分10分の簡単なものでも小テストを行うのは重要で、ディスカッションセッションに参加する前提として、きちんと講義を聞き、文献やスライドをしっかり読んでおくモチベーションアップに役立ちました」。
いろいろな見方からどれを選ぶのか、自分で判断する力をつけてほしい
この授業は入学して間もない学生が履修することから、楽しく分かりやすいものにしたいとの思いもあった。「早い段階で面白いと思える授業にめぐり逢えれば、政治学にいっそう興味を持ってもらえる。そう思って、難しい概念や複雑なモデルを解説するときも身近な例を使うよう心がけました」。
この授業に限らず政治学を教える上で学生に伝えたいのは同じ現象についても「いろいろな見方がある」ということだ。「政治学には唯一の正解というものはありません。つねに、対立する見方、多様な解釈が共存しています。そのことを理解した上で、それぞれの見方や解釈が論理的に導かれているかをチェックし、どれに説得力があると思うか、なぜ自分はそう思うのかを自分自身で理解できることが重要なのです。授業では政治学のいろいろな考え方を教えますが、最終的にどれがもっとも妥当なのかは、自分で判断できるようになってほしいです」。
過去の日本語の授業では「衝撃的だった」「今まで考えていたのとまったく違うことを習った感じ」「あれが政治学の基礎を築いてくれた」との感想が寄せられていた。今回の英語の授業に関しても、次年度にキャンパスで会った元履修生に「あの授業はとても役に立った」と声をかけられたのがうれしかったという。
今回受賞に至ったのはまわりの協力も大きかったと感謝している。「ピンチヒッターだったんで、学部の事務の方たちもいろいろ相談に乗ってくれました。優秀なTAの二人に綿密に相談しながら進められたのも、幸運でしたし、とても有難かったです」。