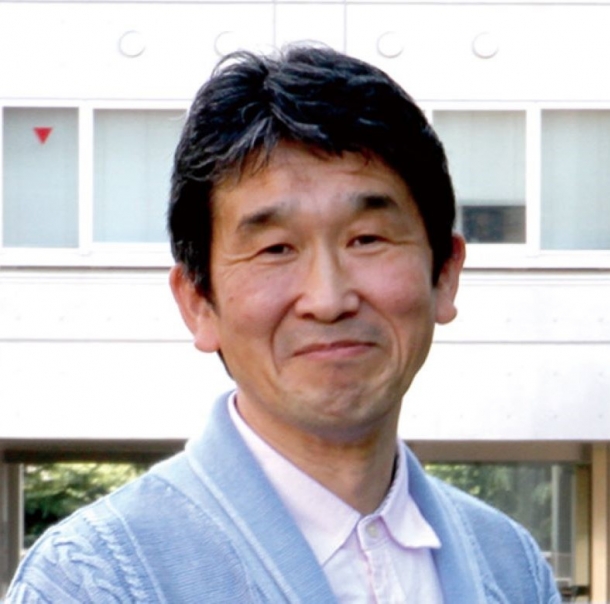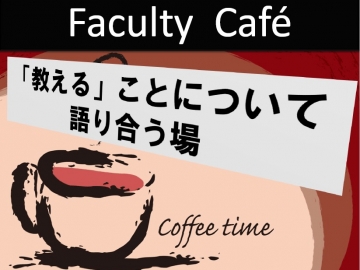2021年度秋学期ティーチングアワード
総長賞受賞
対象科目:映像制作実習 II
受賞者:是枝 裕和/篠崎 誠/高木 創/土田 環
映画製作の流れを実習形式で学ぶこの授業は、第一線で活躍するプロが担当教員となり、実践的な指導が受けられることが魅力だ。しかし、授業の目的は映画監督の養成ではないと断言する。では、この授業を通して学生はどんなことを学んでいくのか。担当教員のうち是枝教授、土田講師のお二人にお話を伺った。
段階ごとの実習課題に取り組みプレゼンし、フィードバックを受ける
秋学期に開講されるこの「映像制作実習Ⅱ」は、春学期の「映像制作実習Ⅰ」を履修した学生が対象で、実質的には通年の科目となっている。春学期に作成した脚本を元に撮影、録音、編集作業を行い、最終的には上映会の企画やプロディース、広報に至るまで、映像制作に必要なプロセスを実習を通して学ぶ。
2015年度に是枝教授が始めたこの授業には、現在4名の教員が指導に携わっている。録音・整音担当の高木講師は作品の仕上げ段階で加わることが多く、基本的には、監督や映画研究を専門とする他の3名の教員が毎回の授業を担当している。
履修学生は選抜を経て登録された35名。制作の段階に応じて個人作業と5~8名でのグループ作業で取り組んだ企画書、脚本、撮影、編集素材などを、毎回の事前課題として授業の2日前までに提出し、授業当日はそれに対する学生のプレゼンと教員の講評で進行するのが基本スタイルだ。「授業時間外の活動が多いので学生も大変ですが、講師陣も、課題提出後の短い時間で中身を確認し、授業ではその場で考えながら対応する即応力も必要なので負担は大きく、授業が終わるとぐったりするほどです。学生の提出してきた課題を丁寧に読む、そして真剣にコメントを返す姿勢が伝わっていたらいいなとは思います」。(土田講師)
プレゼンや講評はすべての学生の前で行われるため、効果的なプレゼンのやり方を学べるだけでなく、各グループが抱える課題やそれに対するコメントを目にすることで、課題や解決法を一般化して学ぶことができる。
講評は、発表者と教員の対話や、他グループからの質疑応答を交えるなど、学生たちが自主的に考えて判断する力を養うよう工夫されている。大切にしているのは、学生の話をよく聞くことだ。「話すのが得意でなく、言葉がなかなか出てこないこともありますが、その学生が何を考えているか、何を言おうとしているのかを感じ取って、こちらもその場で一緒に考えていくようにしています」。(土田講師)
複数の教員で担当する体制は、互いがどうコメントするのか、教員間で良い意味での緊張感や刺激を生むと同時に、学生たちに多様な褒め方や直し方を示せるというメリットもある。土田講師は「是枝先生は絶対に否定から入らないなど、まず学生の良い面を見つけるのが上手」と感じている。是枝教授は「その場に応じた3人のバランスが大事」と指摘。コロナ禍でオンライン授業となった時期も、お互いの反応が分からずバラバラな状態では指導が難しいと考え、教員だけは全員が同じ場所に集まって参加したという。
1年間の学びで得た気づきをアーカイブ化して後輩に残す
作品の完成後も、他者に届けること、伝えるところまで学びは続く。大隈記念講堂に加えて早稲田松竹においても上映会が行われ、学生たちはポスター制作やSNSによる発信などを通して上映会の運営にまで携わっていく。そのすべてを体験することで、監督や編集に携わる学生だけでなく、グループの全学生がそれぞれの役割を担うことになる。
早稲田松竹での上映は、大学との地域連携として先方から申し出てくれたことだが、上映作品は選んでもらうことになっている。「上映される本数は決まっていません。その年に制作された4本のうち、3本が選ばれて1本が落選するという残酷な年もありました。大学側でお金を出して、いわゆる「貸し館」としてスクリーンを貸り上げるのは簡単ですが、それはやりたくない。実際に映画館で上映してもらうのがどのぐらい大変なのかを経験してもらいたいのです」。(土田講師)
チラシを配れば見に来てくれると軽く考える学生もいるが、それだけでは集客はできないという現実を、早稲田松竹の担当者からも指導を受けながら学生たちは学んでいく。
学期末には、1年を通じての反省点や課題の解決法などを、担当したパートごとに集まって「引継ぎ書」としてまとめ、アーカイブ化している。自分たちの学びを振り返るだけでなく、次年度以後の学生たちにも参考にしてもらうためだ。「この授業は学生たちが主役なので、過去の財産も参考にして自主的に考えてほしいと願っています」。
伝えたいことを説明し、納得して動いてもらうのは、普遍的に必要なスキル
「この授業は映画監督を育てるためのものではない」というのが講師陣の共通認識だ。「映像制作の技術をスキルとして学ぶことも重要ですが、表現そのものをどのように成立させるのか、個別の問いに対してみんなで考えることに重きを置いています。作品はあくまで教材であって、共同でものをつくることを通して、いろいろなことを学んでほしいですね」。(土田講師)
実際は映像のプロを目指している学生も多いが、「単に映画界の人材を育てる目的であれば、ここでやるのは違うという気がしています。結果的に後に映画業界に入って来ることはありますし、それ自体はうれしい気持ちもあるんですが」。(是枝教授)
映画制作は特殊なようでいて、仕事を進める上で大事なことは特別なものではないと強調する。「自分がやりたいことを人に説明して納得し動いてもらいながら、たくさんの大変なプロセスを経て、作品はできていきます。映画以外のものに置き換えても必要なことは同じなので、結局は人間が鍛えられるということだと思います」。(是枝教授)