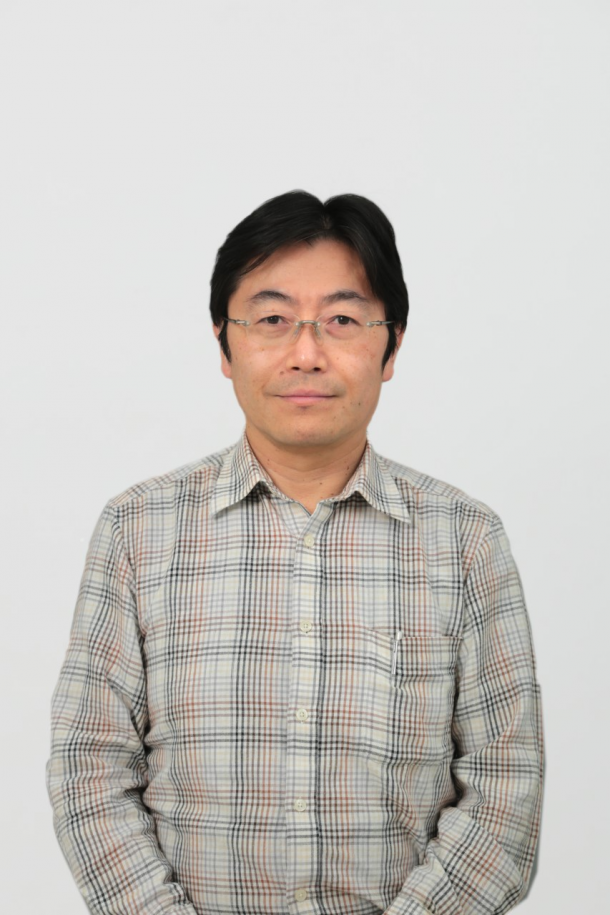2022年度春学期ティーチングアワード
総長賞受賞
対象科目:プログラミング基礎A
受賞者:柏木 雅英
数学の世界では数値計算やシミュレーションなどに欠かせない計算機。近年は数学の証明にも利用されたり、計算機のための数学が生まれるなど、その重要性が増しているという。それを使いこなす能力は、研究のためだけでなく、実社会においても常に必要な能力だと考える柏木教授。プログラミングの技術を学ぶこの授業において、その思いを伝えるため様々な工夫を凝らし、学生からも非常に高い評価を得ている。
プログラミングを通じて、計算機の仕組みと、その可能性を学ぶ
この授業は基幹理工学部応用数理学科の2年生を対象とした専門必修の科目だ。C言語によるプログラミング技術の習得を通じて、計算機の仕組みを学ぶことを目的としている。授業では毎回小さな課題を課し、学生の理解度を確認しながら講義を進める。「単にこれをするプログラムを書けというのではなく、数学の有名な問題解決につながるような課題をいくつも混ぜて、それを計算機を使って調べる経験を重ね、そういう研究方法があることを知ってもらいます」。
応用数理学科では将来的に数学の道に進む学生も多い。「現在の数学研究では計算機の利用は不可欠で、たとえば何かを調べるときに自分でプログラムをさっと変えて試せるスキルはとても役に立ちます。人類が飛行機の発明で空を飛べるようになったのと同じように、自由にプログラムを書けることは人間の頭脳を拡張し、可能性を広げてくれます。将来的に人よりいい仕事ができるようになるには、コンピュータを使いこなせるようになりなさいとのメッセージを込めています」。
対面、遠隔のリアルタイム視聴、録画と3つの受講形態を提供
授業は2020年度、2021年度と完全にオンラインで行っていたが、2022年度からは端末室での対面授業を再開。しかし、日本に入国できない留学生がいたこともあり、オンラインでのリアルタイム配信も継続した。「体調不良や感染の不安を感じる学生もいたようなので、オンラインで受講できる体制も必要だと感じました」。
オンライン配信はZOOMを利用。教室に来ている学生とオンラインで受講している学生とに、それぞれ何が見えていて何が聞こえているかの配慮が必要となるため、慣れるまでは大変だったという。教室に備え付けの固定カメラはあったものの、それでは黒板やスライドの文字が見えない。TAはいないためマイクを持ってまわってもらうこともできず、教室内の学生の声を拾うこともむずかしい。「結局、私は教卓でPCのカメラに向かって講義をし、資料もZOOMの共有機能を使うなど、目の前に学生はいるけれど自宅のパソコンからZOOM中継しているのと同じようなスタイルになりました」。
ZOOMを利用すると録画も簡単なため、講義の内容はMoodleに残しておき、後からでも視聴できるようにした。学生は、対面、遠隔、そして録画と3つの方法から都合のよいものを選べることになる。「教室で対面授業を受けた学生も後から見返して復習に使えるなど、受講体制が柔軟な点は好評でした」。
通常の対面授業では、90分のうち60分で講義をし、残りの30分はその場で課題に取り組ませていた。その間、教室を見て回りながら質問を受け付けたり学生の様子を確認したりできた。しかし、履修生が多いこともあり、遠隔授業では画面共有などを利用しても、各学生がプログラムを書いている様子を確認することは不可能と感じた。そこで、課題は授業終了後1週間以内に提出させることとし、質問があればMoodleから聞くように指示した。「本当は書いているところを細かく見たいのですが仕方ないですね。学生にとっては、30分でできるものを1週間かけてやればよくなったので、難易度が下がって取り組みやすくなったかもしれません」。
柏木教授は、2000年頃から自身のWebサイト上で授業の内容を解説するページを公開している。ここではレポートの書き方なども詳しく説明しており、学生のレポート作成能力の向上にも役立っている。授業中にもそのページを見せながら説明するほか、学生はいつでも自由にアクセスできるので、予習や復習にも利用されている。ここにMoodleで行う小テストへの誘導も設定しており、WebとMoodleの両者をシームレスに連携させているのが特長だ。
苦手意識を持たず、プログラムが書く楽しさを感じてほしい
どのレベルの学生に合わせた授業をするかは、常に悩ましい問題だ。「選択科目では、上位1/3ぐらいを想定してもいいと思うのですが、好きな人だけにフォーカスした内容だと下のレベルの学生は辛くなってしまう。必修科目ではなるべく落ちこぼれる人を作りたくないので、上から2/3ぐらいの学生が一番快適に感じる難易度に設定しています」。
特にプログラミングにおいては、学生一人ひとりの適・不適の差が非常に大きいと感じている。「できる人とできない人で100倍ぐらい生産性の違いが出ることもあるほど、極端な差があります」。学生の興味をひくための工夫として、ゲームやパズルを解くプログラム作りも取り入れている。「計算機の面白さに目覚めた人が専門の方面に進んでくれればもちろんうれしいです。一方で、違う道に進んだとしても、うちの学科の学生なら将来プログラムを書く必要が出てくるケースは多いと思うので、得意でない学生も苦手意識を持たせないようにという点は、常に強く意識しています。」。
自分自身は、高校生の頃に初めて触れたときから計算機の魅力にとりつかれたという。「今やコンピュータはすっかり身近になりましたが、音楽や動画を楽しむだけではない面白さがあることを伝えたいです。当時と比べるとプログラミングは複雑になり敷居は高いですが、自分でプログラムを思い通り動かせれば、自分の脳だけではとても考えられないようなことができるという感覚を持ってもらえるとうれしいですね」。