- ニュース
- 1月19日(月)現政研セミナー開催のお知らせ
1月19日(月)現政研セミナー開催のお知らせ
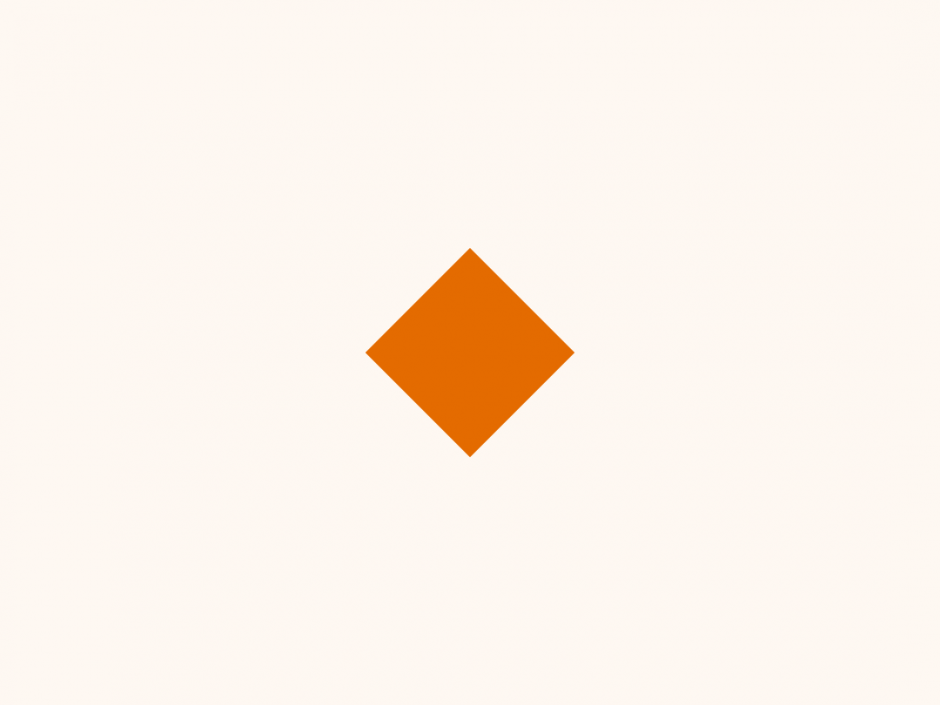
- Posted
- 2015年1月8日(木)
部会名:現政研セミナー
日 時:1月19日(月)12:15-13:30
場 所:早稲田大学 早稲田キャンパス3号館12階ディスカッションルーム
テーマ:Communication with Market Participants for Macroeconomic Policy:
Empirical Assessment using Data in Early Modern Japan
発表者:高槻 泰郎 神戸大学経済経営研究所(准教授)
Abstract:
We introduce the natural experiment that the policy maker sought to
communicate with the market in spite of the fact that he was never
forced to do. We use the Tokugawa Shogunate’s experience of macroeconomic
policy to empirically explore the role of communication. Through the
Tokugawa period (1603-1867), the Shogunate often intervened the market to keep
the rice price stable, based on his absolute authority. We find three
phases of the market interventions during the period from the mid-18th to the
early 19th century. First, the Shogunate conducted the large-sized
intervention in the way ignoring the market participants, but had to abandon it.
Second,in the wake of this failure, the Shogunate conducted small-sized
interventions in the way just following the arguments of the market
participants, which were not so effective. Finally, the Shogunate
achieved the policy goal by the commitment with large-sized interventions as
one of the communication tools to convey his intention to the market
participants.
日本語要旨:
マクロ経済政策を実施するにあたって、政策当局と市場参加者とのコミュニケーションが
重要な意味を持つことは、バーナンキやブラインダーをはじめ、多くの人々が指摘しているところである。その場合、中央銀行は説明責任を果たすべきである、との道義的な理由と、政策をより効果的なものにするための実用上の理由とによって説明されるが、純粋に後者の要因を分析することは難しい。
そこで本報告は、市場参加者に対して情報開示をする、あるいはコミュニケーションを
行う道義的な理由を全く持たなかった徳川幕府が、経済政策を発動するに際して、コミュニケーションの必要性を認識するに至るプロセスを、実証的に明らかにし、コミュニケーションの実用的な側面を浮き彫りにする。
その結果、以下のことが明らかになった。徳川幕府は、米価安定のため、繰り返し市場介入を行っていたが、
(1)18世紀中葉までは、市場参加者の声を聞かずに、強制的かつ大規模な市場介入を行っていた。
(2)その蹉跌を見るや、19世紀初頭には、市場参加者の意見に従って小規模な介入を繰り返すようになっていた。
(3)しかし、単純に市場参加者の意見に従うだけでは効果が上がらないと見るや、市場参加者との対話を深めつつ、大規模な市場介入を実施し、米価の安定化に成功した。
- Tags
- イベント
