- ニュース
- 3月30日(日)現代政治思想研究部会(部会主任:飯島 昇藏)研究会開催のお知らせ
3月30日(日)現代政治思想研究部会(部会主任:飯島 昇藏)研究会開催のお知らせ
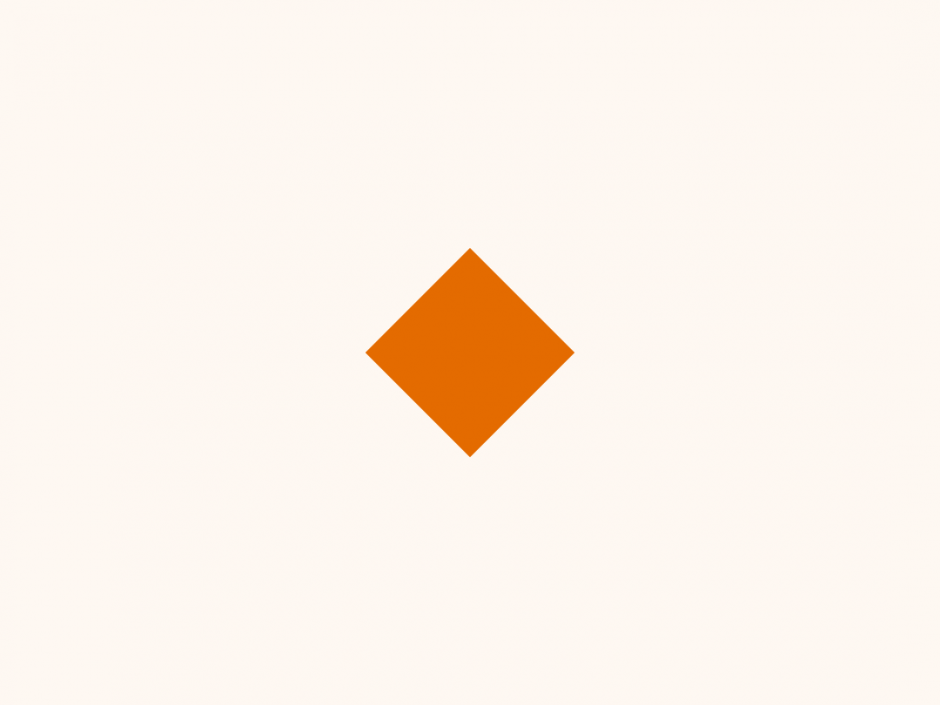
- Posted
- 2014年3月14日(金)
部会名:現代政治思想研究部会(部会主任:飯島 昇藏)
日 時:2014年3月30日(日)10:00-18:00
会 場:早稲田大学1号館 2階 現代政治経済研究所会議室
【1】 10:00-11:00
司会者:大河内 泰樹(一橋大学教授)
報告者:井之口 智亮(早稲田大学大学院博士後期課程)
討論者:井上 弘貴(神戸大学准教授)
テーマ:シティズンシップ教育における相互尊重――多元的社会における相互性に向けて
要旨:シティズンシップ教育をめぐる近年の規範的論議では、価値や信念等の点で多様な
市民間の相互尊重(mutualrespect)についていくつかの解釈が提出されている。
本稿は、社会を構造化している法的・社会的規範が市民の社会的地位に対して及ぼす抑圧や
周縁化の効果に注意を向けつつ、他者を自由で平等な市民として承認するという観点から
相互尊重を捉えるという立場をとる。
そして、こうした意味での相互尊重のためには具体的にどのような能力・資質が必要と
されるのかについて考察する。
略歴:井之口 智亮(いのくち ともあき) 1984年生まれ。
現在、早稲田大学大学院政治学研究科博士後期課程在籍。
主要研究業績:「シヴィリティの両義性と支配――現代共和主義理論の観点から」
(『政治思想研究』第14号、2014年5月刊行予定)、「多元的社会における学校選択とシ
ティズンシップ教育――アメリカ合衆国における公的バウチャー制度をめぐる論争を手が
かりに――」(『早稲田政治公法研究』第99号、2012年)、「政治的討議のためのシティ
ズンシップ教育――個人の自律と他者への共感という概念を軸として――」(『早稲田政
治公法研究』第94号、2010年)。
【2】 11:00-12:00
司会者:木部 尚志(摂南大学教授)
報告者:宮崎 文典(青山学院大学非常勤講師)
討論者:近藤 和貴(早稲田大学助教)
テーマ:友愛と知――プラトン『リュシス』をてがかりに
要旨:〈友〉をめぐって展開されるプラトン『リュシス』の一連の議論には、[1]知への愛に
もとづく友愛関係、[2]他者から愛される人となって、自由を享受し他者を支配することを可能に
する知(と称されるもの)、という2つの要素が見出される。この2つの要素は、ソクラテスの対話活動と、
他者を支配する知を志向するソフィスト的な立場との対比を浮き彫りにするであろう。
本報告では、近年の解釈動向では十分に検討されてこなかった、当対話篇のこうした政治哲学的含意を
明らかにする。
略歴:宮崎 文典(みやざき ふみのり)
1980年生まれ。博士(文学)。
早稲田大学文学学術院助手をへて、現在 青山学院大学青山スタンダード非常勤講師。
主要研究業績:「プラトン『ゴルギアス』における魂の秩序と行為の有益性」(日本倫理学会編
『倫理学年報』60, 2011年)、「不正が恥ずべきこ とであるのはいかにしてか?――プラトン
『ゴルギアス』474c4-475e6をめぐって」(日本哲学会編『哲学』62,2011年)、
「行為と行為の善さ――プラトン『ゴルギアス』466a-468eの解釈」
(西洋古典研究会編『西洋古典研究会論集』22,2013年)
【3】 13:30-14:00
司会者:太田 義器(摂南大学教授)
報告者:日比野 佑香(一橋大学大学院社会学研究科博士課程)
討論者:西永 亮(小樽商科大学准教授)
テーマ:ヘーゲル『精神現象学』におけるケアと身体
要旨:本報告は、ボーヴォワール、ジュディス・バトラー、岡野八代等の先行研究をふまえ、
フェミニズム・クィア理論の観点から、ヘーゲル『精神現象学』の自己意識章を再読するものである。
主人と奴隷の両者を結び付ける「労働」と、その際の身体のあり方に着目し、両者の関係性における
自立性/非自立性の問題を再考することで、ケア実践を社会化するための手掛かりを得たいと考えている。
略歴:日比野 佑香(ひびの ゆか)
一橋大学大学院言語社会研究科博士課程一年
【4】 14:30-15:30
Master of Ceremonies:Shozo Iijima (Waseda University)
Reporter:Takahiro Chino
Commentator: Kazuya Onaka (Hosei University)
Title: Gramsci’s Critique of the Catholic Church
Abstract:
This article explores Gramsci’s critique of the Catholic Church ― the
topic that has left almost unexamined in Gramsci studies. It particularly
focuses on how Gramsci rejects Benedetto Croce’s highly intellectualist criticism
of the Church. According to him, Croce fails to address the nature of the
Church’sstrength, i.e. the popularly grounded character of the Church. Croce’s
verbally harsh critique was only shared by intellectuals and not by masses
whose ‘common sense’ as non-reflected worldview largely stemmed from Catholicism.
By permeating their teachings in people’s common sense, the Church could
keep exercising their influence over the public. In this sense, Croce’s
misfired criticism rather underpins the Church by preserving the status quo ―
the gap between the intellectuals and masses in Italy. Contrary to Croce,
Gramsci proposes to increase social mobility through his critique of religion,
by focusing on people’s ‘good sense’ whereby they can be recruited as a potential
part of intellectual stratum.
略歴: 千野 貴裕(ちの たかひろ) 1982年生まれ。
PhD in Political Science (University CollegeLondon)。
現在、UCL政治学部VisitingResearcher兼、国際基督教大学社会科学研究所研究員。
主要研究業績:「同意と公共性:A.グラムシの市民社会論における同意の形成と解体」
齋藤 純一編『公共性をめぐる政治思想』おうふう、2010年など。
共訳書に、上村 忠男監訳『イタリア版「マルクス主義の危機」論争』未來社、2013年。
【5】 16:00-17:00
司会者:谷澤 正嗣(早稲田大学准教授)
報告者:赤岩 順二(明治大学法学部助教)
討論者:金 慧(千葉大学准教授)
テーマ:現代刑法理論と、カントとヘーゲルの緊急行為論
要旨:ドイツおよび日本の理論刑法学では1960年代から70年代にかけてとくに刑罰論の
領域で「カント、ヘーゲルからの決別」が唱えられた。国民教化のための道徳的強制と
同化する可能性ももつ刑法の領域におけるその主張には今なお耳を傾けるべきものがある。
他方あたかもそれに接し続くかのようにカント法論のテキストの再構成の提案がありまた
再解釈が試みられ、ドイツ刑法学においても再解釈を前提とした研究が登場している。
本報告は、それらの研究を参照して、カント法論とヘーゲル法哲学が言及する緊急行為
(正当防衛、緊急避難)について、19世紀から20世紀初頭のドイツ刑法学における解釈の
偏差を確認したうえで、ヘーゲル法哲学、カント法論における緊急行為論の位置づけに
ついてあらためて検討するものである。
なお本報告は「哲学者における刑法思想」というテーマの一こまとなることを目指したもの
でもあるので最後にその観点から振り返る余裕をもちたい。
キーワード:カント、ヘーゲル、正当防衛、緊急避難、カルネアデスの板事例、緊急窃盗
事例、Klugheit、防衛的緊急避難、対物防衛、ウルピアヌス、叡知的占有
略歴:赤岩 順二(あかいわ じゅんじ)。1961年生まれ。
1991年3月政治学修士(早稲田大学)。2009年3月博士(法学)(明治大学)。
関連研究業績:「緊急避難への対抗と毀損忍受?ヘーゲル緊急権論の再解釈を中心に」
(明治大学社会科学研究所・社会科学研究所紀要 45巻2号,
195-211頁,2007年);(共訳)ミヒャエル・パヴリック「カントとヘーゲルの正当防衛論
(一)(二)(三・完)」(甲南法学53巻1号61-81頁,
3号47-65頁,4号149-165頁,2012-3年);「プラトン『法律』篇845b-860eの一解釈-刑事立法・
司法とソクラテスのパラドクス-」(法哲学会年報(2006),219-228頁,2007年)
【6】 17:00-18:00
司会者:石崎 嘉彦(摂南大学教授)
報告者:小松 優香(筑波大学准教授)
討論者:田中 智彦(東京医科歯科大学准教授)
テーマ:チャールズ・テイラーの「自己論」―多様な「善」に裏づけられた人間存在
要旨:テイラーは主著『自我の源泉―近代アイデンティティの形成』のなかで、西洋近代特有の
「自己」概念がどこから生まれどのように形成されてきたか、その諸源泉を辿り、近代的な
考え方を作り上げているいくつかの構成要素を紐解いた。
それによると近代に焦点を当てながらもプラトンから現代までも思想史的に渉猟し、その変遷を
描き出すことで、「自己」が本来「強い評価」に支えらえた存在であり、人間が自己を状況に
応じて解釈する「自己解釈する動物」であり、それと人間が表現力豊かな言語を身につけ他者と
やりとりする「自己対話性」の葛藤によって生成する生ある存在であることが窺える。
ところが、17世紀の科学革命以降、自然科学の著しい発展にともない、本来の対話的な人間存在を
意味づける表現言語の機能は劣ったものと扱われ見失われつつあり、もうひとつの指示機能のみが
優位に取り上げられるようになった。そこでは、直観や感性、感覚といったものは殆ど考慮されず、
「道具的理性」によって人間はいかなる存在であり、いなかる状態が善いことかではなく、いかなる
行為が正しく、いかなる行いを為すべきかという効率計算と義務ばかりに注視してきた傾向がある。
本報告では、「多様な善に裏づけられた人間存在」として、善の多様性を窺い知るため
のキーワード「強い評価」「自己解釈」「真正さの倫理」等について検証し、その全体像
を示していくことにする。
略歴:小松 優香(こまつ ゆか)1978年生まれ。
日本大学大学院国際関係研究科博士課程単位取得満期退学。
フィンランド国際問題研究所研究員、千葉大学非常勤講師を経て、現在、筑波大学人文社会系准教授。
主要業績:「石橋湛山の思想形成課程と「個人主義」の概念―先行研究における思想的視座」
(日本比較生活文化学会『比較生活文化研究』第14号、2008年);「グローバル・ガバナンスと地球福祉
の検討」(千葉大学公共研究センター『公共研究』第4巻第3号、2007年);
「小国思考の概念と価値判断に関する考察―日本における「小国」思考の水脈」
(日本第学大学院国際関係研究科『大学院論集』第14号、2005年)。
- Tags
- イベント
