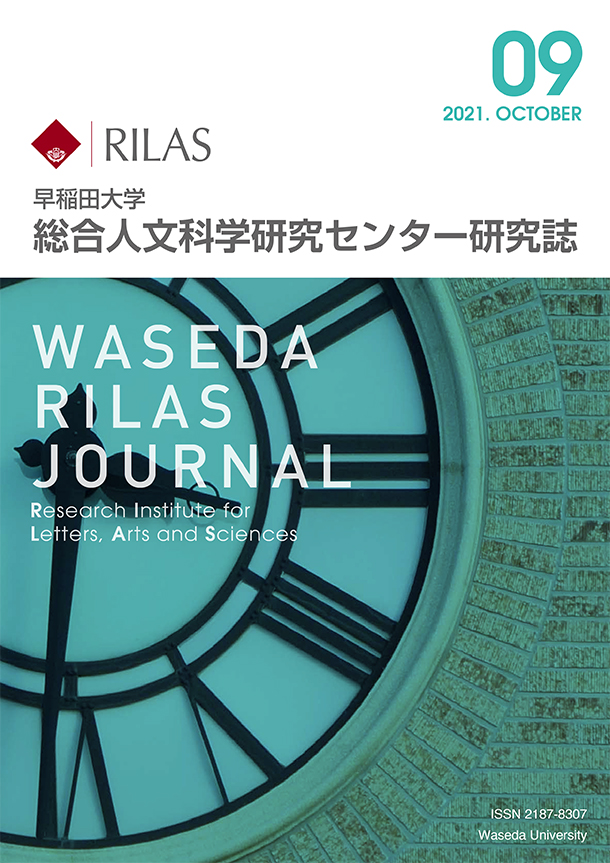- その他
- 総合人文科学研究センター研究誌「WASEDA RILAS JOURNAL No.9」(2021年10月)
総合人文科学研究センター研究誌「WASEDA RILAS JOURNAL No.9」(2021年10月)

- Posted
- Fri, 08 Oct 2021
表紙 Cover
論文(一般投稿)
- 伊川健二
国性爺合戦にみる異国観 - 石丸純一
『懐風藻』道慈伝が描く道慈像 - 馬越洋平
亡き子を探すオルフェウス──「純粋な爪が高々と縞瑪瑙を捧げ」に見る死別の苦悩 - 大木エリカ
新聞小説批評としての谷崎潤一郎「少将滋幹の母」──占領期における文壇への眼差し── - 岡田俊之輔
絕對者を戴く文化、戴かぬ文化──?吉、カーライル、獨步、他 - 尾崎賛美
フィヒテの自己定立論とカントの自己意識論 - 小原 淳
北陸地方に存するドイツ関連史跡の総合的検討 - 久保隆司
山崎闇斎の神道神学思想と江戸前期の朝幕関係の解釈について──分掌・天上論、大政委任論、天海(山王)論の観点から── - 小泉 咲
「物語」に介在する薫──『 源氏物語』「橋姫」から「宿木」巻へ── - 後藤 渡
Une lecture de L’Éternité de Georges Perec - 小林昌平
「接合体」から「螺旋体」へ──ハイデガーにおける「存在史的思索」の深化 - 繁田 歩
存在の概念をめぐるカントとクルージウスの対決 - 謝 敏
疫情背景下戏剧传播模式新思考──以英国NT Live 的“数字化”制作和推广为例 - 陣野英則
時空を超える『源氏物語』──文学上の理念・理論との相互作用── - 高橋憲子
『古事記』の中のオノマトペ──「塩こをろこをろ」の解釈と英訳 - 武田一文
聖堂装飾における十二使徒の選択に関する一考察──典拠と神学的重要性の相克に着目して── - 田辺俊介
沖縄における「ナショナル」・アイデンティティ──その担い手と政治意識との関連の実証分析 - 寺嶋雅彦
「総合哲学体系」の哲学的基礎──スペンサー『第一原理』に基づいて── - 徳泉さち
平斉民が北魏書法に与えた影響 - 長尾 天
神宿るイリュージョンと神無きイリュージョン──クレメント・グリーンバーグとシュルレアリスムをめぐる一視座 - 長澤法幸
サッフォーを悼むルネ・ヴィヴィアン──二つの「祈り」の分析── - 中村優花
『新新文詩』における森槐南の創作の精神 - 福田淑子
カルロ・クリヴェッリ作《無原罪の宿り》──一対の天使をめぐる予型論的解釈試論── - 古屋詩織
マッソンとミロのオートマティスム──1920年代シュルレアリスムにおける画家の実践── - 益田朋幸
スタロ・ナゴリチャネの聖母伝──ミハイルとエウティキオスの装飾プログラム - 山﨑皓平
東方研究の成立と展開──1900-1990年代における主要人物、組織、理念── - 山本佳生
発想の「場所」から引用の集成へ──トポス、ロキ・コムーネス、詞華集── - 湯浅翔馬
Le mouvement des jeunes bonapartistes et l’Action française avant la Première Guerre mondiale (1909-1914) - 渡邉義浩
『史記』三家注の特徴について
研究ノート・報告・翻訳(一般投稿)
- 銭 雨辰
Another Evangelism: Missionary Visuality as Transcultural Conversations in China and Japan, from Pre-modern to Modern Periods - 張 龍龍
Youth Mainlander Soldiers of the Great Retreat and Their Interrupted Lives under the Authoritarian Regime of Taiwan in the 1950s
特集1 RILAS 研究部門「トランスナショナル社会と日本文化」主催研究会「近代北方史の動態を探る─北海道開拓と民衆経験─」、シンポジウム「日琉関係史の軌跡と展望─紙屋敦之氏の研究を中心に─」
- 伊川健二
主催研究会「近代北方史の動態を探る─北海道開拓と民衆経験─」、シンポジウム「日琉関係史の軌跡と展望─紙屋敦之氏の研究を中心に─」 - 田辺陽子
明治期におけるキリスト教伝道とアイヌ民族──函館アイヌ学校を事例に── - 武藤三代平
明治青年による移植民事業と労資関係の形成──北海道開拓および海外植民の経験から── - 深谷克己
紙屋敦之氏の人と業績 - 矢野美沙子
東アジアにおける琉球王国の位置づけ - 深瀬公一郎
薩摩藩の琉球政策と「異国」「領内」──島津重豪期における琉球の使節派遣を中心に── - ティネッロ・マルコ
国際的な視点からみた「琉球処分」──東アジアの視点を超えて
特集2 RILAS 研究部門「現代社会における危機の解明と共生社会創出に向けた研究」主催 早稲田大学総合人文科学研究センター2020 年度年次フォーラム
- 浦野正樹・浅野幸子
東日本大震災10 年の軌跡と大規模災害からの復興をめぐって──新たな「日常」への模索── - 川副早央里・松村 治・浦野正樹・長田攻一
富岡町と浪江町の10 年目──第7回シニア社会学会シンポジウムの議論から──