- その他
- 沖縄文化の伝統と変容に関する研究
沖縄文化の伝統と変容に関する研究
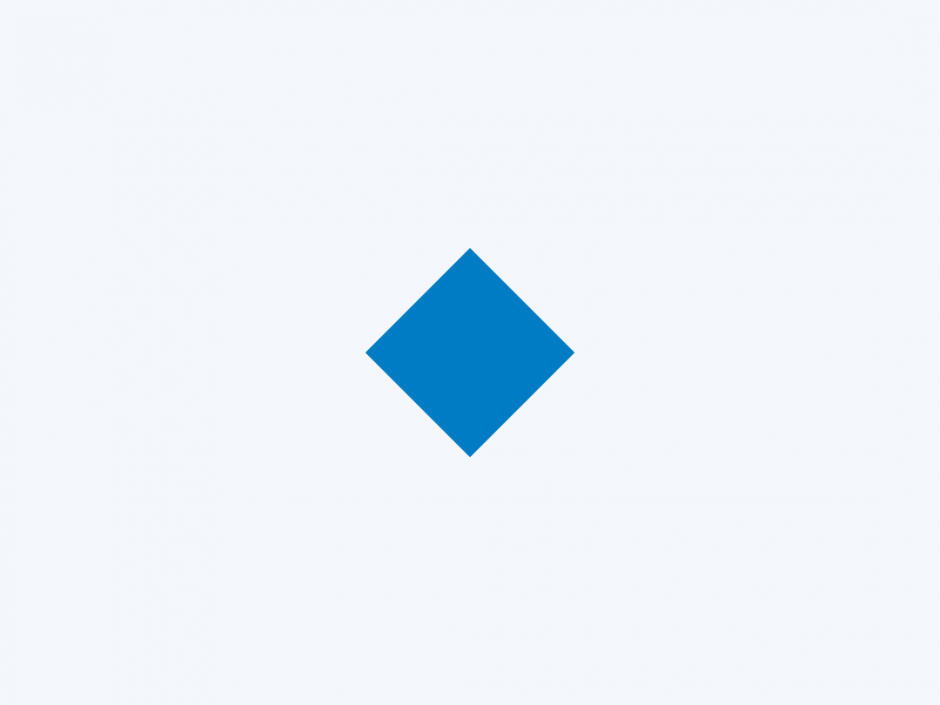
- Posted
- Fri, 16 Apr 2004

研究代表者
蔵持 不三也
KURAMOCHI Fumiya
人間科学部教授
本プロジェクトの概要と目的
本研究は、日本列島において独自の文化を形成してきた沖縄文化をとりあげ、現代に続く「文化の伝統と変容」の具体的な過程を、ひとつのフィールド(調査地)を対象として、学際的・総合的に明らかにすることを目的としている。調査研究の主たる視点は以下の通りである。
- 環境・生態と漁業などの生業の伝統と変容
- 祝祭とスポーツ・遊戯文化の伝統と変容
- 近代以降の移民および都市化と物質文化の伝統と変容
本研究の調査地に選定した浜比嘉島は、沖縄本島の東方に位置し、人口約600、農業と漁業を主たる生業とする小さな島であるが、今もなお多くの民俗文化を残している。一方、この島は、明治以降に多数の海外移民を送り出し、近年では、沖縄本島勝連半島と海中道路および橋によって結ばれ、都市化の波に洗われるようになった。浜比嘉島を本研究のフィールドとして選定した所以である。
本研究の大きな特色は、沖縄に日本文化の古層をみようとする従来の日本民俗学などの視点とは異なり、現代に続く「文化の伝統と変容」の具体的な過程を、多角的な視座から再検討しようとする点にある。また、専門分野の違う複数の研究者が互いに密接な関係をもちながら、フィールドを共有することによって、学際的研究の新しいあり方を実現しようとするものでもある。こうして本研究は、地域研究の新たなモデルを提供するとともに、この地域の将来を考える上でひとつの視座を示すことができるであろう。
1980年代以降、文化人類学を初めとする人文・社会科学の分野において、文化の「伝統」に対する再検討がすすみ、「伝統」が過去からの不変性もつものとする見方は誤であり、いかなる文化も不断に(再)形成ないし(再)生産され続けるものとの理解が広まった。「伝統の創造」というホブズボームらの提唱は、そのことをつとに語るものであるが、他方、特定の固有文化は「伝統」を再編しつつ、文化的アイデンティティーを維持している。本研究はこうした学問的動向をふまえつつ、さらに外国人による沖縄研究にも目を向けつつ、文化人類学のみならず、環境計画学・社会学・考古学・比較教育学など多様な領域から、地域研究を通してこの問題を明らかにしようとするものである。本研究の学問的位置づけは、まさにここにある。
プロジェクト期間
2004年4月~2007年3月
- Tags
- 研究活動
