- ニュース
- 「原発事故、避難者の4割がPTSDの疑い」人間科学学術院 辻内琢也教授の研究グループの研究成果が朝日新聞デジタルで紹介されました。
「原発事故、避難者の4割がPTSDの疑い」人間科学学術院 辻内琢也教授の研究グループの研究成果が朝日新聞デジタルで紹介されました。
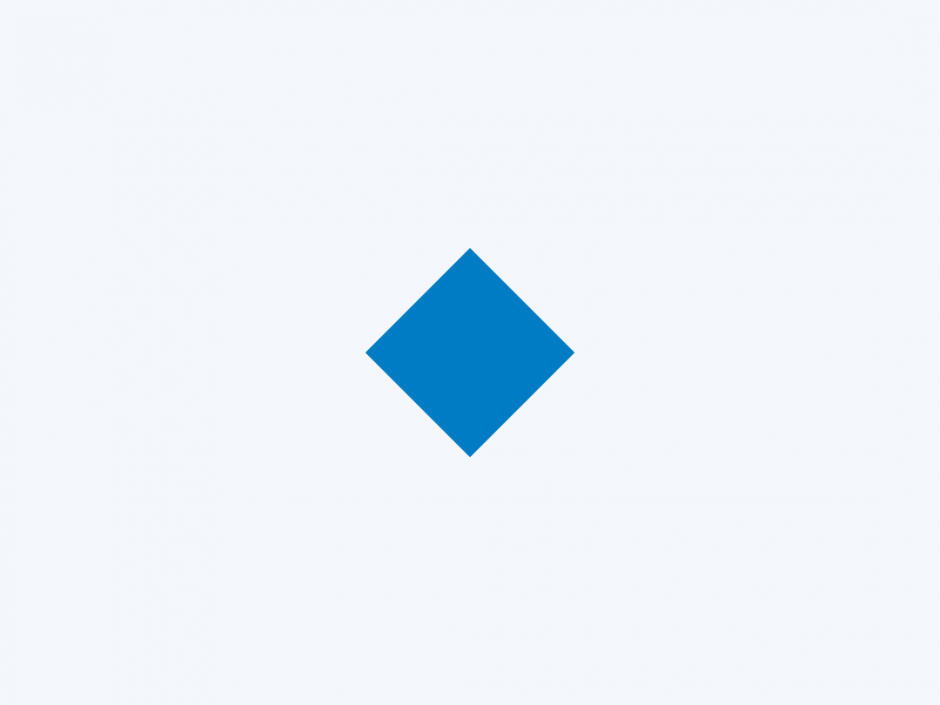
- Posted
- Tue, 14 Mar 2023
人間科学学術院辻内琢也教授が所長を務める災害復興医療人類学研究所の研究成果が、3/9(木)の朝日新聞デジタルで紹介されました。以下、朝日新聞デジタルからの抜粋です。
原発事故、避難者の4割がPTSDの疑い 市民団体など調査(朝日新聞デジタル)
東京電力福島第一原発事故で福島県外に避難した人の約4割が心的外傷後ストレス障害(PTSD)の可能性があることが、市民団体と早稲田大の調査でわかった。震災から12年となるなか、避難先で孤立する状況も浮かび上がり、被災者のもとへ出向く「アウトリーチ」といった支援を求める声があがる。
調査したのは早大・災害復興医療人類学研究所と市民団体「震災支援ネットワーク埼玉」。関東を中心に福島県外へ避難した5350世帯にアンケートし、516件の回答が寄せられた。
調査ではトラウマ体験に対するストレス反応の度合いを測った。その結果、2022年1~4月時点で37・0%の人がPTSDの可能性があった。原発事故の恐怖や津波被害だけでなく、事故後の環境や政府の対応などによって受け続けたストレスが複合的に合わさり、10年以上が経過してもPTSDの疑いがある人が多くいるという。
「賠償や補償への心配」「失業」「避難者として嫌な経験をしたこと」が主な要因と分析された。「嫌な経験」のなかには、避難者であることや賠償金の問題と関連した悪口や誹謗(ひぼう)中傷、からかい、などがあげられた。
避難した人のうち34・5%が「現在も失業している」と答え、その理由(複数回答可)は「自営業を再開できない」が16・3%、「病気を患っている」が14・0%を占めた。
56・8%の人が「賠償や補償に心配事がある」と答えるなど、経済状況の悪化も浮き彫りとなった。さらに「ふるさとで失われたと感じるもの」を聞いたところ、「家」が72・1%、「友人・知人の交友関係」が66・7%を占め、多くの人が喪失を感じていた。
孤独感の高まりも深刻になっている。現在の居住先で地域の友人・知人との付き合いがあるかという質問には、「めったにない」「まったくない」が38・9%だった。
調査を手がけた早大の辻内琢也教授は、「被災者らの交流会はあるが、外に出られない人もいる」と指摘。「ひきこもりやうつ状態の人、高齢者などには戸別訪問の支援が必要だ。(被災者をケアする)復興支援員を増やしていかないといけない」と訴える。
