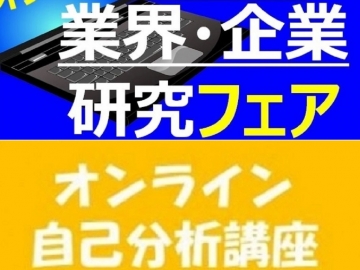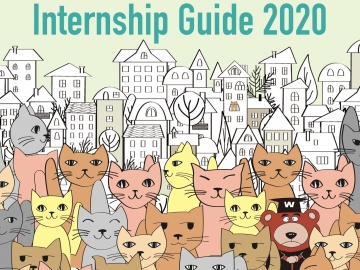OB・OG訪問とは、企業で働いている先輩を訪ねて、その企業の情報や先輩の働き方などについて話を聞くことです。貴重な生の声を聞くことは、就職活動には欠かせない業界研究・企業研究において大変参考になるものです。自分が本当に知りたいことや聞きたいことを明確にして臨むことで、一歩進むきっかけにもなるでしょう。
ここでは、OB・OG訪問のメリットと具体的にどのように進めたら良いのかを、PDCAサイクル(Plan→Do→Check→Act)(※1)に沿って説明していきます。
(※1)参考:ES作成の近道!? PDCAサイクルを意識して「課題解決力」発見(早稲田ウィークリー2018年5月23日)
 メリット1:会社説明会やWebサイトでは得られない情報を得ることができる
メリット1:会社説明会やWebサイトでは得られない情報を得ることができる
先輩に直接会って話を伺うことで、Webサイトや会社案内、企業説明会では得られない、職場の生の情報や先輩の考えを聞くことができます。つまり、現場の社員の意見・本音や社風の一端をじかに感じ取ることができるのです。得たものから業界・企業研究をより深め、自分に合った職業・企業について考えていきましょう。
メリット2:アポ取り→訪問、自ら行動することが自信になる
見知らぬ社会人に自分から連絡を取ることは緊張するものですが、一度行動することで自信につながります。多くの企業が求めているコミュニケーション能力を磨くチャンスにもなります。面接の予行演習のつもりで、マナーや心遣いを意識して積極的に連絡を取り、訪問を実行してみましょう。
では、具体的にどんなことをすればよいのでしょうか。ここからは、訪問の流れをPDCAサイクルに沿ってまとめました。
① 計画を立てる(Plan)
◆目的
その訪問から何を知りたいのかを明確にしておきましょう。
◆訪問する相手
入社3~8年目くらいの中堅社員の方だと、業務全般について幅広く聞くことができます。学部や学生時代の経験など、属性が自分と同じ人に会うと、イメージを重ねやすいでしょう。なるべく多くの人に会うことも大事です。希望する部署以外の方や、競合他社の方にも会うことで、他部署・他企業から見た話を聞くことができ、勉強になるはずです。早稲田大学校友の方かどうかに関わらず、できるだけ現場の話を聞くようにしましょう。
◆開始時期
いつ頃から始めるべきか、決まった時期はありません。準備期、実践期、内定へ向けてなど時期によって知りたい情報や、訪問の目的は変わるはずです。自分なりのタイミングで、できるところから始めて、アポイントの取れた方から会っていただくのがいいでしょう。
NG事項
⇒ 無計画・準備不足の状態で会う。
OB・OG訪問は、ただ会ってもらうことだけが目的ではありません。自己分析や業界・企業研究に着手する前の状態で会うことは、先方に失礼な上、お互いに貴重な時間を無駄にします。
② 行動する(Do)
 ◆OB・OG探し
◆OB・OG探し
ゼミ、サークル、アルバイト、知人など、自分独自のネットワークを最大限に生かして、OB・OGを探しましょう。また、キャリアセンターの「OB・OG名簿」(※2)も役に立ちます。「OB・OG名簿」とは、各企業が作成し、大学に提供された名簿のことです。
(※2)OB・OG名簿、内定実績・内定者名簿の閲覧については、MyWaseda内の『キャリアコンパス』をご参照ください。
◆アポイントの取り方
ここが最初の関門です。OB・OGの方が所属する企業の代表や部署へ直接電話をかけて、つないでもらうのが一般的です。OB・OG名簿に連絡先(人事部など)が記載されている場合には、そこに連絡してください。
◆日時と待ち合わせ
日時は、なるべく先方の都合に合わせます。当日の待ち合わせ時に目印となる建物や、持ち物を事前に確認しましょう。
NG事項
⇒ いきなりメールを送りつけて、返信を強要する。
その時の事情にもよりますが、メールよりも電話の方がお互いの雰囲気をつかみやすく、すぐにアポイントが取れる傾向があります。まずはきちんと自己紹介をし、どのように相手の情報を知ったのかを伝えることが大切です。
⇒ 昼時、始業・終業時間帯に電話する。
慌ただしい始業・終業前後の時間帯や昼休み時間は避けましょう。電話の場合はメモを取ることも忘れずに。
⇒ 行動せずに諦める。
知らない人に電話をかけるのは勇気の要るものですが、少しの勇気を出すこと! この経験は、仕事で電話をかける練習にもなります。しっかり準備して取りかかれば大丈夫です。
③ 事前準備(Check)
◆質問を考える
せっかく直接お話を伺う機会です。企業のWebサイトやパンフレットには事前に目を通しておき、自分なりに感じた疑問や実際に働いている自分をイメージして質問を準備してみましょう。以下、質問の例を参考にしてください。
《準備期の質問項目》
●具体的な業務の内容、1日の流れ、会社の雰囲気
●説明会やセミナーでは分からなかったこと。自分なりに得た情報が合っているかの確認
●実際に働いている中での大変なこと、また、やりがいを感じるとき
●若手社員の活躍状況、キャリア形成(5年後、10年後)について
《実践期の質問項目》
●エントリーシートを持参して、自己PRや志望動機などについて、アドバイスをいただく
●自分の特性を生かしてその企業で活躍できるか、意見を伺う
●採用試験や面接の練習をしていただく
●求められる人材について尋ねる
《内定へ向けた時期の質問項目》
●他業種、他社との比較材料を得る
●残業時間や福利厚生の実情を聞く
NG事項
⇒Webサイトや会社案内を見ればすぐに分かるような質問。
事前に情報の下調べをした上で、現場ならではの話を聞きましょう。
⇒先方の入社年次に合っていない不適切な質問。
先方の所属・年次を確認して準備しましょう。
④ 訪問当日(Act)

◆相手への気遣いとマナー
相手を気遣い、マナーを守りましょう。 例えば、約束の10分前には到着し、時間を作ってくださったことへの感謝を伝えるといいでしょう。
◆初対面の相手ともお互いを確認できるように
事前に目印を確認しておくなど、当日スムーズに会えるように工夫しましょう。
◆お互いの連絡先交換
交通事情など不測の事態が起こることもあります。緊急の連絡先として、お互いの電話番号を事前に確認しておきましょう。
◆質問の時間配分
初めにどれくらいの時間をいただけるのかを伺って時間配分をし、準備してきた質問事項に優先順位をつけて話を展開しましょう。
◆ポイントのメモ
訪問中にメモを取ることの許可を確認して、ポイントをメモするといいでしょう。
◆OB・OGの方は企業の代表
人事の方でなくとも、OB・OGの方は企業の代表として会ってくださっています。もしかしたら、もう採用選考はここから始まっているかもしれないという意識を常に持ちましょう。既に社会に出て、見られているという意識です。
◆素直で謙虚になる
分からないことは素直に認め、教えていただくという謙虚な姿勢で臨みましょう。
◆名刺をいただく
名刺をいただくと、後でまた連絡を取りたい場合や、お礼状やメールを出すときにスムーズになります。
◆さらに紹介してもらう
年次の違う先輩などの話を伺いたい場合は、さらに紹介していただきましょう。出身大学にこだわる必要はありません。
NG事項
⇒コミュニケーション能力をアピールするために、一方的に持論を展開する。
会話のキャッチボールを心掛けましょう。
⇒話を伺うという姿勢をはき違え、質問・準備をせずに終始受け身な態度。
OB・OGの方に訪問を受ける義務はありません。貴重な時間を作っていただいていることを忘れずに。
⇒飲食店などで行われた場合、支払いに関して無関心。
自分から支払いを申し出ましょう。
⇒いただいた名刺を他人に見せびらかす。
名刺は個人情報です。安易に取り扱うことのないよう注意してください。
⑤ 訪問後(Act)
 ◆お礼の連絡
◆お礼の連絡
お礼はできるだけ早く、翌日にはメールか手紙で出しましょう。構成は、次のようにするといいでしょう。(感謝を簡潔にまとめる→得られた情報に対する感想→入社への意欲→感謝)
◆内容の記録
当日の内容や感想は、すぐに記録しておきましょう。
◆意見と情報を生かす
得た情報を大切にして、自分の特性や働く上での自分の価値軸を考える際に生かしましょう。自分はその仕事をやってみたいと思うか、自分の働く上での価値軸と企業の方向性は合っているのか、自分の特性はその業界・企業で発揮できそうか、よく考えましょう。
NG事項
⇒ 忙しさを理由に、訪問後に何もしない。
せっかくの訪問を意味あるものにするように検証することが大切です。
OB・OG訪問は、社会や人に対して自分から心を開いて、たった一人で積極的に飛び込む行動です。既に社会で働いている数多くの先輩方は、きっと勇気を出して歩き出した皆さんを受け止めてくれますよ!
※キャリアセンターでは、さまざまな業界・企業研究に効く講座の開催を予定しています。視点を広げて調べ、主体的な進路選択をするために積極的に活用しましょう。