今回は、篠田監督にとって最後の映画となる「スパイ・ゾルゲ」の上映会前の講演をお届けする。講演後、競走部の後輩からは花束が、応援部からは大きなエールが贈られた。学生時代、箱根駅伝で二区を走ったという文武両道の篠田監督にふさわしい締めとなった。
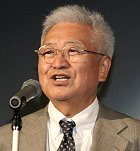
「「スパイ・ゾルゲ」は駅伝の20キロというよりフルマラソンを走った感じでした」
「理想」の末路を目の当たりに
20世紀は共産主義の勃興と終焉の時代だった。ナチス党員のドイツ人でありながらソ連のスパイだったゾルゲ。彼は、現在でいえばNGOにでも入るように、国際共産主義の理想のためにスパイとなった。しかし、20世紀末ベルリンの壁崩壊とともに共産主義の理想は無残に散り果てた。私の人生は、満州事変からイラク戦争まで常に戦争があった。なぜ人は人を殺すのか。ともかく放ってはおけずにこの映画を作ったのだ。
サダム・フセインにはなれない「日本人の宿命」を描きたい

客席に降りて、競走部の後輩らに囲まれ観客と一緒に記念撮影
終戦時、皇国少年だった僕は、日本が負けたら切腹せよと教えられていたのに、その時には配属将校も先生もいなかった。なぜ日本人はこんなに簡単に降伏できるのか。戦争が終われば即デモクラシーへ移行し、8月15日を忘れてしまう。日本には震災や台風があり、過ぎ去るまでは、どんなに立派な哲学を持っていても、同じ共同体に住む日本人となり、個性をすべて失ってしまう。決して降伏しないサダム・フセインにはなれない。この地理的日本人の宿命こそ、描きたかった。二・二六事件、真珠湾攻撃、ゾルゲ事件が、少年時代の三大命題だが、結局60年間でゾルゲだけは私の中に住み付いてしまった。
これは、早稲田大学の新しいカテゴリーを立ち上げる拠点となる実験的映画だ!

後輩への一言…まさに「現世を忘れぬ久遠の理想」
この映画は私の生きた昭和の街並みや路面電車までCGを駆使して再現している。これらは本庄キャンパスにあるデジタル研究施設(TAO)のスーパーコンピュータで制作された。早稲田の新しい映像カテゴリーの出発点だ。








