 政治経済学部4年
政治経済学部4年
渡辺 敦貴
ICC学生スタッフリーダー在職期間
2011年9月〜2013年2月
驚きと悔しさで満ちたSSL生活第一歩
上司である大学職員の方とのある日の会話。
上司:「渡辺君、これやっといてくれる?」
私:「はい、分かりました」
(しばらく後・・・)
私:「できました」
上司:「ありがとう。確認しておきます」
(しばらく後・・・)
私:「そう言えば、俺が作ったあれ、どんな感じに仕上がったんやろ?」
簡単な掲示物の作成。それが、その日私に指示された仕事であった。後日上司が確認した後の完成版を見てみる。すると、最初に自分が作ったものとは全く異なっていて、もはや原型を留めていない。ただただショックだった。掲示物の作成という単純業務さえ、自分は満足にできないのだと。
―悔しい― SSLになって何度、この感情を抱いたことだろう。
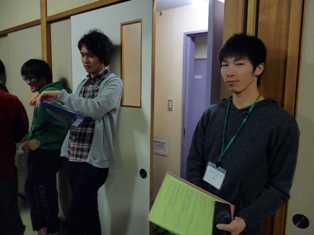 自分はSSLになるまで、ICCのイベントにあまり参加したことがなかった。
自分はSSLになるまで、ICCのイベントにあまり参加したことがなかった。
「ICC? ランゲージエクスチェンジとか、語学系の意識高いイベントやってるとこやろ?」ぐらいの認識しかなかった。
なのでSSLとして働き始めたころは、そのイベントの多様さに驚かされた。著名人を招いてのトークセッション、各国文化紹介のカントリー・フェスタ、深いテーマを掲げてがっつり取り組むキャンプ企画や中長期プロジェクト。企画の多様さや壮大さはもちろんのこと、それをドライブしていく先輩SSLの姿にひたすら感服している自分がいた。かたやキーボードを激しく打ち叩き、分厚い資料を片手に熱く議論する先輩SSL、かたや簡単な掲示物の作成さえ満足にできない自分。原型を留めない形で修正されるポスターや広報文。言われたこと、指示されたことを満足にこなせない自分が、途方もなく悔しかった。
自慢するわけではないが、これまで私は何事にも相応の自信を持って取り組んできた。中学、高校では部活漬けながら勉強もある程度やったし、大学でもインターンシップや留学などに取り組んできた。先生や教授、友人たちからは常に「お前はデキるやつだ」というようなことを言われていて、いわゆる「優等生意識」みたいなものがなかったと言えば嘘になる。だから、ICCでSSLとして採用された時も、特に大きな不安もなく、「バリバリ仕事して、活躍してやる!」と意気込んでいた。 それが、実際仕事が始まると、驚きと悔しさの連続で、何度も唇をかみしめることになるのである。
学生発の企画案を重要視しているICCにとって、言うまでもなく「イベント企画」はSSLの重要な責務だ。多様なバックグラウンドを持ったSSLは、それぞれ自分の問題意識や関心をイベントに乗せ、企画として進めていく。ただ、自分はこれと言って何かに深い問題意識も感じたこともなければ、「こんなイベントがやりたい!」という斬新なアイデアも思い浮かばなかった。
「異文化交流・・・まあ、楽しければそれでいいんちゃう?」、正直、そんなふうに思っていた。結果的に、留学先であったスペイン文化紹介イベントと、いくつかのトークセッションを企画したものの、他のSSLが出していたような「核心に迫るような」深い企画のアイデアはとうとう出せないままであった。
自分の失敗を認めるということ
 プライドの高い自分は最初、ついつい失敗から目を背けたくなったし、実際隠し通してしまったこともあった。ただ、それでは成長できないというのは明白。「変わらなければならない」、痛切にそう感じていた。
プライドの高い自分は最初、ついつい失敗から目を背けたくなったし、実際隠し通してしまったこともあった。ただ、それでは成長できないというのは明白。「変わらなければならない」、痛切にそう感じていた。
落ち着いてよく考えてみると、「自分が手掛けた仕事を上司が確認して修正を加えていく」というのは、組織にとっての成果の向上はもちろん、自分個人の成長やパフォーマンスを上げていくという意味でも非常に有効なプロセスであると感じた。ポスターや広報文だけでなく、担当企画の進行表や進捗管理、ファシリテーションの文言一つひとつに自分の意図や考え、狙いを込めてドラフトを起案するのだが、上司がそれを見たのちに、「どこが」「どう」修正されたのか、そしてそれは「どうして」修正されたのか、上司の意見や狙いと自分のそれを比べてみるうちに、それこそが、ポイントをフォーカスしながら失敗を学び・力に変えていける道なのだという実感が湧いてきた。それまで感じたことのない「悔しさ」の連続によって、いつしかプライドを守ることを忘れ、自分の失敗を前向きに消化できつつある自分がいた。
自分のバリューをどう出すか
SSLとしての経験もだいぶ長くなり、一通りの仕事はこなせるようになった時期、「自分は他のSSLと比べてどういう点でICCに貢献できるのだろう?」ということを強く考えるようになった。「自分のバリューがどこにあるのか」ということである。
前述の通り、残念ながら自分には斬新なイベントアイデアが思いつくことはできなかったが、次第に自分の強みは「0から1を作ること」よりも「1を100にも1000にもすることなのだ」という風に認識するようになった。たとえ「核心に迫る」企画やアイデアを出せなくても、他の人が持っている想いや問題意識、周りにあるニーズを実際の企画と結び付けて具現化し、効率と効果を考えながら企画を推進していく、その導きのプロセスに自分が貢献できることにとてもやりがいを感じた。
 そういった意味で、最も印象に残っているのは「電通×ICC 日本を良くするひらめき杯」である。日本人学生、外国人学生が「日本を良くするひらめき」をテーマにアイデアを競うコンペ形式のプロジェクトだった。
そういった意味で、最も印象に残っているのは「電通×ICC 日本を良くするひらめき杯」である。日本人学生、外国人学生が「日本を良くするひらめき」をテーマにアイデアを競うコンペ形式のプロジェクトだった。
当初、株式会社電通から「日本に対して、留学生や海外経験を持つ人の“外からの視点”を知りたい」という漠然とした提案がICCに持ちこまれたが、企画の内容はほとんど定まっていなかった。その中で、いかにそれを企画として形にするかを1から考え、スキームを組んでいく作業はまさに、それを意識してやってきた自分にとって「集大成」であった。
「募集要項やポスターはどんなものにするか」、「募集説明会は、どんな雰囲気で、いつ行うか、何を伝えるか」、「最後にコンペをやるのだから、その前のグループブレストはこんな風に・・・」など、電通のクリエイター・社員の方々と協働しながら、「誰が?いつ?どこで?何を?どのように?」ということを徹底的にシミュレーションしながら、企画をドライブしていく感覚は、さながらF1レーサーばりの爽快感と緊張感だった。
自分の手がけた仕事に対して、相変わらず上司からは容赦のない駄目出しが出ることはあったし、修正も入れられたが、このころになると、ある程度の自信と余裕を持って受け止め、疑問は率直にぶつけられるようになっていた。悔しさよりも、「一緒にベターな企画を創り上げていく」という協働感覚である。ただ言われたことをやる事務「作業」ではなく、自分で頭を使って進行や流れを考えていく「仕事」を任され始めたことに、上司や周囲からの信頼と期待を感じることもでき、それが自分のさらなるモチベーションにもつながっていた。
「仕事が楽しい!」単純に、そう思えて仕方がなかった。そして、かつて掲示物の作成で唇をかみしめていた昔の自分に、少しは胸を張れる気がした。
1年半を振り返って
ICC学生スタッフリーダー(SSL)として活動したのは、1年間のスペイン留学から帰国してから卒業までの約1年半。
3年生後期からのスタートということもあり、就職活動と並行しながらの時期もあったが、就職先が決まってから、4年生の1年間は、SSLの活動一筋といっても過言ではない。1年半は本当にあっという間だったが、SSLとしての経験を通じて、「仕事」というものの面白さ、難しさ、やりがいに向き合い続けた自分がいた。そして、それは自分の将来を考える上でもとても参考になるものであった。私はもうすぐ卒業だが、この貴重な大学生活の1年半、大いなる情熱を持ってチャレンジさせてくれたICCにとても感謝している。そして、今後も一人でも多くの人が、ここで「悔しさを力に」変えてくれることを祈るばかりである。






