この記事は後編になります。前編を読んでいない方はまずそちらをご覧ください。後編では、中岡さんが英語学習をしてきたからこそ得られたエピソードについてなどたくさんお話を伺っています!英語学習に対するモチベーションが上がる話が盛りだくさんです!

Photo by interviewee
ゲストプロフィール
中岡宏太さん(なかおか こうた)さん
政治経済学部3年
2022年度政治経済学部 学部長奨励賞 受賞
経済学会幹事長
大学入学後にTOEFL iTP 607点、TOEIC925点を取得
大学受験予備校において英語採点を担当
- 自分とは違う環境の人と接する中で価値観の変化などはありましたか?
中岡さん :自分はまだまだ伸びしろがあるんだというのは感じます。私は比較的勉強などは頑張る方だったり、中学高校の時は生徒会長をやるとかちょっと自惚れてしまいがちですが、自分よりも努力している人が世の中にはごろごろいたり、とにかく自分から進んで様々なことに取り組んでいる人がいるんだなと感じて刺激を受けています。
他には日本人の当たり前と外国の当たり前はすごく違うなと感じています。具体例をあげるなら、ジェンダーへの意識ですね。中学生の時にカナダへ行きグループワークをしているときに、一人の学生が「ゲイなんだ」とカミングアウトしてきたときに、自分は「えっ!?」みたいな反応をしてしまったんです。ただ、周りは普通に反応をしていて、そのときに、これが当たり前で、相手のことを受け入れることが必要なんだなと感じました。自分の当たり前が当たり前じゃないんだなと思いました。

Photo by ICC
- 一番自分の中で英語できて良かったな、と思うときはどんなときですか?
中岡さん:少し哲学チックになりますが、自分を表現するといいますか自分について考えることが好きで、自分ってどういう人なんだろう?とか自分はこういう考えをもっているなど、外的に自分を決めることは簡単で、例えば早稲田大学の〇〇という人ですとか成績は〇〇ですとか。一方で、自分の内側から自分はこう考えていて、みたいな表現を使うときに、英語というツールがあるからこそ新しい価値観に触れられ自分を相対化できるものかなと思っています。
- 普段からアカデミックな勉強とは違う英語も楽しみながら触れられていますか?
中岡さん:半分はラッキーで英語にストレスが無いってことが大きいですかね。あとは、知りたい内容があるからこそ日本語英語関係なく情報にアクセスしてるっていう感じです。例えば、この人の話聞いてみようとか、日本の文化について知りたいと思った時にドナルド・キーンさんの講演を聞いてアメリカ人がアメリカ人に日本の文化を説明するとこうなるんだとかっていうのは知りたいから聞いているという感じです。言語化が難しいんですが、たしかに、翻訳機を使えばいいっちゃいいと思うんですけど、英語特有の言い回しとか土砂降りのことを”it’s raining cats and dogs”っていうみたいに言葉ってすごくその人の生活とか考え方を形づくっているものだからその言葉として理解することに意味があると思っています。だから、できるだけ生の英語に触れたいという思いがありますね。
- 翻訳機のお話がでましたが、翻訳機を通さず生の英語に触れていたから体験できたエピソードはありますか?
中岡さん:Princetonでもルームメイトだった仲の良い友達の家族を案内する機会があったんですが、その友達のお母さんがすごいインド訛りの英語だったんですよ。これがもし、翻訳機であれば単語がポンポンでてくるだけだと思うんですが、実際に聞いてみると「インド系にルーツがあるのかな」や「インド系ってここの単語を強調するような話し方なんだとか」を感じたりして、その人のパーソナリティ的なものが見えてくると思うんですよね。あとは、生の言葉を聞いてすごく早口かつ論理的に話す人であれば固いイメージが持てたり、一方で明るくゆっくり話をする人がいればまた別のイメージを持ったりなど、イメージを知るためには翻訳機を通しては伝わってこないものがありますね。
- 英語学習をする中で何か価値観が変わったみたいなエピソードはありますか?
中岡さん:英語によって頭の使い方が変わったなと思います。英語の構造ってあると思っていて、よくアカデミックライティングとかで教えられることですけど、結論ファーストやgeneral to specificみたいなのはめちゃくちゃ大事ですね。日本語の少し余計な話をしていくっていうのはそれはそれで良さはありますけど、結論から話をするのは就活の場面など限られた時間の中で自分の伝えたいことを伝えきるうえでとても大切だなと感じています。この、結論から話をして論理的に物事を伝えるっていうのは、英語に出会ってから頭の使い方が変わったなと思います。トピックセンテンスを意識するみたいな考え方は、プレゼンテーションする場面でも活かせたりするのでほんとに重要だと思います。
細井:中岡さんはこの英語の構造をどこで学んだのですか?
中岡さん:高校の時の塾ですね。塾の英語の先生に言われたのが、「君はすごく、文章を書くのが得意だと思うし、話をするのも得意だと思う。ただ、限られた解答用紙の中で伝えたいことを伝えきるのもそれはそれで技術なんだよ。そのためには、採点官や読み手を意識して知りたいことをまず伝えて読む気にさせることが大事だよ。」という言葉で、その時に染みついていったという感じです。
- 早大生の中には英語の勉強を頑張ろう!と考えている学生が多くいると思います。そういった、方々に英語学習を頑張ってきた中岡さんから何か一言お願いします。
中岡さん:英語学習をする中でなにか目的はあった方がいいなと思っています。英語を学ぶことが目的化されているけどそれはちょっと違う気がしていて、英語をなぜ学習するのかの目的意識をもって取り組んだほうがいいなと思いますね。まずは好きな英語のフレーズやスピーチを見つけると英語学習に対するハードルは下がるかなと思います。
目的がないなら少し過激な言い方にはなりますが、無理してやるものでもないかなと思います。嫌々やるくらいなら好きなことやったら?っておもいます。人間は死ぬってわかっていて、人生は限られているっていう意識を持つことによって、目的意識や自分が何をやりたいか先鋭化されていかないんですよね。なので、限られた時間の中で好きなことをやる、その手段として英語があればいいんじゃないかなと思ってます。
やりたいことが見つからない人に対しては、とにかく色んな人に会ってみてほしいですね。 理由は2つあって、1つは相手は思ってるほど自分のことを気にしていないことです。俺なんかが相談に行ったらめんどくさいかなとか迷惑かなとか、思うかもしれないですが、「あなたの人生はわたしのもの、あなたの人生を変えてやる」みたいな人は少ないと思うので気軽に話を聞きにいってほしいですね。2つ目は大学生特権です。社会人になると利害関係がなしには中々会うのも難しくなってくるかもしれないんですが、大学生だと結構会ってくれるものなので是非試してみてほしいです。色んな人に会って、自分こういうことやりたいんだなというのを見つけていき、今回のテーマに絡めればその中で英語の位置を確固たるものにすれば英語のモチベーションにもつながるんじゃないかなと。これやるためには、このように英語が力になるっていう英語のポジション付けができるといいと思います。
- 中岡さん個人の目標を何かありますか?
中岡さん:個人的な最終目標として、本を書きたいんです。本を書いて自分を表現したり他人の感情に訴えかけるときに自分の視野が狭いと良くないですし、日本人のみならず海外の人にも読んでもらいたいんです。そのためには、英語を使って色んな方とお話するのもそうですし、村上春樹さんのように英語でも本を書けるようにならないとなという思いがあるので英語が必要って感じになってますね。
***
インタビューを終えて
今回は政治経済学部3年の中岡宏太さんにインタビューを行いました。中岡さんと細井(インタビュアー)は同じゼミに所属していることもあり、私は中岡さんの圧倒的な努力量に驚かされるとともに刺激を受けながら日々を送っています。英語学習そのものを目的にするのではなく、ツールとして扱うという点は以前にインタビューをした田村さんと同じ内容であり、いかに英語が自分の目的を達成する手段として重要なのかを感じました。また、英語が使えることで海外の人など多様な人材と交流することができ、その結果として自分を相対化することに繋がっているという話が印象的でした。
私自身も英語を勉強する目的を常に意識しつつ、時には自分を相対化し成長につなげていきたいと強く思いました。
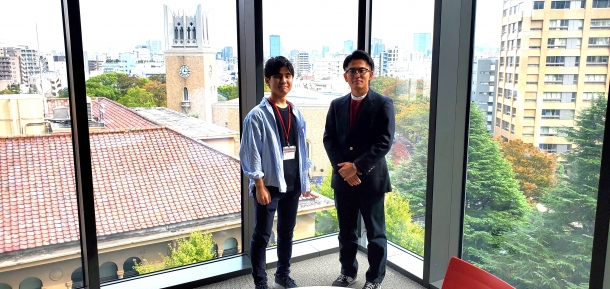
Photo by ICC






