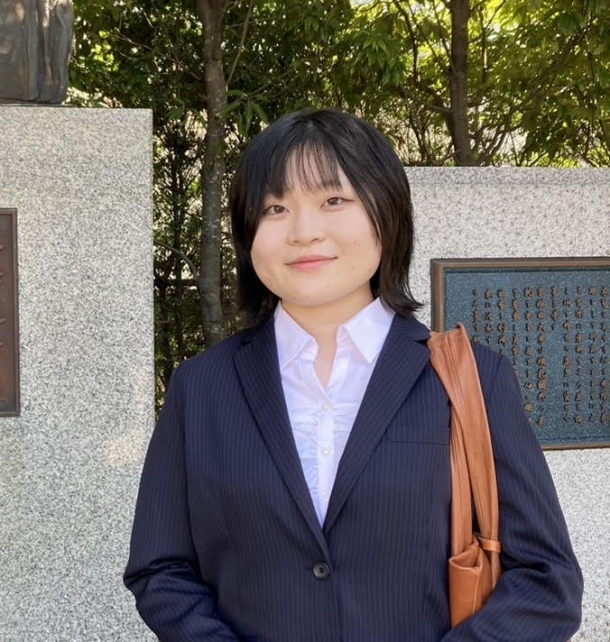文学部 今泉 栞花
キャンパス内を歩いていると、『繊細の森』という立て看板が目に入り、思わず立ち止まりました。大学に入学してから心理学に興味を持つようになった私は、繊細な心を持つHSPについて学びたいと思い、このイベントに参加することを決めました。このレポートでは、イベントに参加した中で印象に残っていることをいくつか紹介します。
今回のイベントは国際文学館(村上春樹ライブラリー)で行われました。多くの本に囲まれ、オレンジ色の優しい光で包まれており、会場に入るだけでリラックスできる素敵な空間でした。
アメリカの心理学者・アーロン博士が提唱したHSP(Highly Sensitive Person)の特徴は「感受性が強い」という言葉でまとめられます。その場の雰囲気や相手の気持ちだけでなく、光や音などの環境の変化もよく感じ取ります。味覚や嗅覚が敏感であったり、カフェインに影響を受けやすいといった特徴もあります。さまざまなことに気が付くので、作業に時間がかかったり、疲れやすいという悩みを持つこともあるそうです。この繊細さは生まれ持った気質であり、神経質な人などの性格に起因するものではありません。この生まれつき繊細なHSPは5人に1人の割合で存在しているともいわれ、近年は日本でも大きく取り上げられるようになりました。今回のイベントでは、HSPの特徴やHSPの人が生きやすくなるヒントが詰まった本、『「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる 「繊細さん」の本』の著者であり、HSPの専門カウンセラーである武田友紀さんの講演をお聞きしました。今回の講演では、HSPに関しての学術的な知識だけでなく、生活が少し楽になるポイントなども教えていただきました。
武田さんのお話の中で、私が特に印象に残っているのが「まるごとの姿で生きる」という言葉です。私たちは普段、特技や長所などといった自分の強みを大切にして生きています。だからこそ自分の苦手なものや短所に向き合わなければならないとき、目をそらしたくなって、自分の理想とのギャップに苦しくなるのです。私自身、今年4月に上京してきて、やりたいことやなりたい姿が明確にあって、やる気にあふれていましたが、慣れない環境の中で生活を送ることに必死で、理想の自分からはほど遠く苦しい思いをしていました。ですが武田さんのおっしゃる通り「まるごとの姿で生きる」ことができれば、それは自分自身をまるごと深く肯定することにつながり、健やかに生活を送ることができます。4月からずっと張りつめていた心がこの言葉を聞いて少し緩み、このイベントに参加して良かったと強く感じました。
イベントの後半では、参加者がいくつかのグループに分かれ、「こんな時はどうする?」というテーマでディスカッションをしました。私のグループには、事前に取り組んだHSPのチェックリストがすべて埋まった人、半分ほど当てはまった人、ほとんど当てはまらなかった人、それぞれがグループの中にいて、全く同じ意見を持った人はいませんでした。例えば「周りに不機嫌な人がいたらどうする?」というテーマでは、これ以上不穏な空気にならないように、それとなく相手の気持ちを汲み取ってなにかパスを出すという意見、巻き込まれたくないからその場を去るという意見、不機嫌であることに気づかないふりをしてそのほかの人との会話を楽しむという意見など多種多様でした。私にとって、「逃げる」という対処法は思いつかなかったので、こういう考え方もあるのかと新たな気付きを得ました。このグループディスカッションでは、HSPであってもそうでなくても、その人が持つそれぞれの繊細さに触れることができ、他者を思いやって生活することの大切さを再確認することができました。

ICC photo
最後に、このイベントでのゲスト講師であるの武田さん、ICCスタッフの皆さん、参加者で豊かな時間を共有することができ、私にとって非常に有意義な時間となりました。HSPについて知識を得られたこと、「まるごとの姿で生きる」という言葉を知れたこと、他者の考え方に触れることができたことなど、今回のイベントで得た知見が今後の私の生活にきっと多くの彩りを与えてくれるはずです。自分にも他者にも優しくいられるように、今回学んだことを大切にしていきたいと思います。