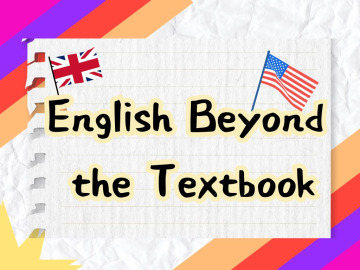R.T.
ICC学生スタッフリーダー
2019年5月~2023年1月在籍
願わくば之をして異文化理解人を戦慄せしめよ。
文字は殺すが霊は生かす
まず、大学生活の4年間を経て、私が何に惹かれ何を学んできたか、振り返ってみる。

空の下なら全てが忘れられる 青い田舎が大好きだった(photo by author)
・Paradox Interactiveの歴史シミュレーションゲーム(2019.4.~)
・民俗学、イスラーム(2019.9.~)
・「恋する小惑星」(2020.1.~)
・旅(2020.2.~)
・日本神話(2020.3.~)
・「宇宙よりも遠い場所」(2020.8.~)
・水族館(2020.8.~)
・西アフリカ(2020.9.~)
・メモ(2020.9.~)
・城めぐり(2020.12.~)
・地名(2020.12.~)
・擬洋風建築(2021.2.~)
・「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」(2021.3.~)
・地質学、岩石学(2021.5.~)
・廃墟巡り(2021.7.~)
・サウナ(2021.8.~)
・隧道(2021.9.~)
・分類学、生物学(2021.10.~)
・「BLUE REFLECTION」(2022.2.~)
・橋梁(2022.3.~)
・日本酒(2022.3.~)
・道路構造物(2022.4.~)
・暗渠(2022.9.~)
・「ぼっち・ざ・ろっく!」(2022.11.~)
・動画編集(2022.12.~)
「一番ハマったこと」を挙げるとすれば、それは間違いなく旅である。旅とは、本を読むこと同じであり、「世を知り、人を知る」ためのものであると、愈々自覚するに至った。名所旧跡を巡るのももちろん楽しいし、一方で成るたけ辺土を歩いてみようとしてみると、都市ではない、そこに住む普通の人びとの暮らしを肌で感じることができて、面白い。そして、改めて集成して思うのは、多少の変動はあれど、ハマってきたものは確実に自分の中で咀嚼し切れているし、今でもその知識は身についている、という確かな自信だ。どの要素も、今日の私を構成するものとして、ひとつも欠くことのできない、大好きなものたちだ。いざいざ旅に出ると、私は、降り立った土地の地名から過去の人びとの歴史を予測し、足元の岩石からはより巨視的な歴史を、あるいは眼前の道路構造物に身近な交通史に思いを馳せ、地域の食を嗜むことで確かな生の実感としてそれを受け取ることができる。そして、サウナの後の酒は格別に旨い。旅の様々な観点から得た知識を旅先の光景に全身全霊で当てはめることで、飽くなき感動と、止めどない更なる知識欲が湧き上がってくる。むべなるかな、世情の都合により海外旅行は一度しか経験できなかったものの、日本全国47都道府県を身一つこの足で巡り、それぞれの土地の良さを知ったことは、日本人としてのアイデンティティを持つ私にとって、ICCに身を置く上での大きな思想的背景を確立したのではないかと考えている。さて、来年度から社会人となる私は、その「旅」を資本主義社会の商品として取り扱う立場になるのだという。学生の身の上からでは知り得なかった旅を知り、覚えることができるのではないかと、ささやかな憧憬に期待する。

真っ白な未来 君と描いて(photo by author)
天網恢恢疎にして漏らさず
次に、私がICC在籍中に自ら企画・立案・運営したイベントについて、その一部を挙げてみる。
・【新入生歓迎イベント】邦楽演奏&茶道体験~ 邦楽を聴きながら、茶道を体験します ~
・【フィールド・トリップ】ICC MUSEUM TOUR ~東京国立博物館で日本の歴史に触れよう~
・【カントリー・フェスタ】オーストリア文化ナイト~音楽も芸術も食も!中欧の大国の魅力とは~
・【ラウンジ】オンライン・ラウンジイベント
・【新入生歓迎イベント】世界地理クイズ大会
・【トーク・セッション】オンライン トーク セッション:南極観測隊員から見た地球~果ての大地にあるたからもの~
・【新入生歓迎イベント】ICCサークル・フェア
・【テーマ・カフェ】オンライン交流イベント with アイスランド:オンラインで北極圏を体感しよう
・【トーク・セッション】Online Talk Session with 近鉄グループホールディングス~今だから知りたい鉄道企業!共創による豊かな社会とは~
・【カントリー・フェスタ】オマーン文化ナイト~知られざる親日国!砂漠と海と中東の秘宝~
・【トーク・セッション】你好、早稲田!Liyuuがみたセカイ
あらためて振り返ると、有難いことに私の趣味や関心分野に応じたイベントを数々実現させてもらえる結果となった。私ならではの興味関心から、固定観念的な「異文化理解」に対しある程度は新しい風を吹き込んだのではないかと思っている。しかし、何よりも重要なことは、旅を通じて確信を得たことであるが、その体験から何を学び、自分自身の生活に落とし込むことができたか、である。鑑みるに、ICCでの業務を通じて私に与えられた命題は、以下の3つである。すなわち、1.自分自身の醜悪さに向き合うこと、2.社会生活の厳しさを知ること、3.異文化とは何かを再定義すること。これらを自らに問い、問い続けた。
1について。誤解の無いように補足するが、私は「醜悪さ」を否定的な言葉として用いているのではない。端的に換言すれば、それは自分自身への戒めであり、常に己の改善点を見つけ出し前向きに生きていくための指針としての、積極的な言葉である。さて、私は元来欠陥の多い不出来な人間で、性、狷介、自ら恃むこと頗る厚く、努力で体裁を取り繕っているだけの、奇人のふりをしている凡人と為り生きてきた。しかしながら、他の学生スタッフの同僚たちは才気煥発、そして参加者も同様に高い熱意と交渉力を持つ方々で、私にとっては常に内在する青春コンプレックスとの戦いであった。その自覚を怠ると、人間にはどんなに努力をしても越えられない壁があるということを忘れてしまい、身の程を弁えて生きなければ、何らかの形で排斥作用を受けるということを、本組織に属するなかで様々なかたちで体験することができた。そして、どんなに信頼を投げかけても上手く交われない人がいて、すなわち信頼は常に一方的なもので、他人に信頼の還元を期待することは控えるべきだということも学んだ。その道理を越えて他人から評価してもらいたいのであれば、まずは、個性を殺し、社会に迎合する器を上手く取り繕ってお為ごかしに生きるという方法がひとつ。進んでふたつめには、自分自身に固有の能力そのものが認められるよう、魂を込めて己のそれを磨き続けるという方法。私は、満足した馬鹿であるよりは不満足なソクラテスであるほうが絶対にいい。そもそも、前者ができるほど私は器用ではない。これが確信できる場であって、私の今後の人生の指針を与えてくれる偉大な経験であった。
2について。大学1年生の5月に学生スタッフとして働き始めたが、これが私にとって初めてのアルバイトであり、以来「組織」という場において様々な刺激を受けてきた。まず、具体的なスキルとして、ビジネスシーンやミーティングの場で必要となる対応スキル、つまりは受付業務、ビジネスメールの書き方、議事録の取り方、イベント写真の撮り方などといったオフィス業務に関する知識を、充実した研修を通じて身に付けることができた。次に、組織で何かを成し遂げるということに関して、ある種の責任感というものを学んだ。組織を支える一員という自覚をもって業務に取り組み、比較的業務に余裕のある時も辛抱強く業務分析や改善への取り組みを行うことで、誠実に乗り越える大切さを知ることが出来たというのは、集団生活が苦手な自分の、多少なりとも成長した部分であると実感している。しかし、上述のように、社会では待っていれば善きサマリア人が現れるというわけではない。4年間同じ組織に所属し、日常業務を繰り返している中で、企画を立案・運営し続けるのは単調で、限界があると感じることも少なくはなかった。その一方で、4年間所属しているからこそ見える組織の姿や継承できる文化、熟成される能力があることを、身をもって知ることができたことも事実であったし、だからこそ自分自身の能力を向上し続ける必要があるのだとも覚えた。畢竟社会人となる前に、充実したその予行演習を体験することができたのではないかと感じている。
3について。ICCに所属するようになって以来、本組織の名称である「異文化」とは何か、日頃から考えるようになった。導き出された結論は、4年間、この組織に所属していて最も強く感じたこととして、個々人がそれぞれの「異文化」像を解釈しこの場に居るという事実である。ICCでは言語ランチやカントリー・フェスタのように、文化的な側面による交流が大文字の「異文化理解」であると認識されがちである。すなわちこの場では、多様性の尊重を大きなテーマとはしていながらも、高名の木登りも斯くの如く、もうひとつの理念である典型的な異文化理解のイメージをある意味では押し付けることで、多様性の大枠から逸脱しているのではないかという疑念を、私はいつの日からか抱いていたのである。その是非については未だに確信を得られるものとはなっていないし、敢えて挑戦する気は毛頭ない。しかし、ヘテロであるということは、何かしらの正義が前提として正当化されていて、もう一方の埒外の存在は疑わしいものとして、ある意味では呪われたものに見えるのである。一方でこの思考法は、逆説的に多様性の絶対性を礼賛しているわけではない。むしろ私は、多様性、就中人権などといった概念をヒトの進化史のボディプランに反するものとして、金持ち資本主義者の道楽に過ぎないとわり切ってきた(それを享受してこの場に居ると知りながらも)。それでは、私にとっての「異文化」しいては「異文化理解」とはいったい何だったのであろうか。すなわちそれは、私にとって未知の、あるいは受け入れ難い全ての概念に対する「違和感」への寛容性である。その違和感は、時には私の無限の知識欲を刺激するものであるが、また一方では度し難い嫌悪感を覚えるものでもある。正直なところ、これら全ては民族的アイデンティティあるいは集合的無意識に通ずる感覚だとも思うが、政治的な話題は好まないのでそれに関する議論は控えたい。まとめるとすれば、人付き合いの全く不得手な私の方から、交流する相手の価値観をある程度は認め、トラブルの無いように遅滞なく生きていくということが、健全な人生のためには求められていると自覚するに至った。しかしながら、父が放蕩息子の弟を赦し、赦されたとはいえ、兄のように不満を抱いてしまうのが普通の人情であり、これはなかなかに難しいことのように思える。そして、1や2の繰り返しにはなるが、他人から隣人と認めてもらえるようにするためには、やはり自分自身の能力を高めることが必要不可欠となってくる。そうあれと、思う。

オマーンイベントを終えて(photo by ICC)
Quae Sit Sapientia Disce Legendo
総括して、自分自身の今後の人生の行く末のための大きな教訓を、豊富なエピソードでもって実感し、身に付けることができたという点で、私がこの組織に参画した意義は大いに果たすことができたと思っている。そして、ICCの学生スタッフを務める上で自ら成長しながら多少なりとも自らの価値を早稲田大学に還元し、より多くの学生にとって魅力的な早稲田を築いていくために貢献出来たこと、さらには早稲田大学に自分が在学していたのだという確かな痕跡を残せた、のではないかと信じたい。

ICCラウンジにて(photo by author)
これらの体験は、決して凡庸な私一人が為し得たものではない。偉大なる先人たちの功績と、数々の協力者の皆さま方の尽力によって成し遂げられた結果のかたちである。夙に気付いているつもりではあったが、このような締めくくりの場で振り返ることで、改めてその実感が強まった。関係者の皆さま方へ、私に影響を与えて成長させていただいたことに、重ねて心から感謝の念を申し上げたい。そして私も、ここでは実現できなかったから、他人に必要とされるような、他人の人生の役に立てるような、他人から愛されるような大人として、これからはさらに大きく成長していきたいと強く思う。ここで漸く、大隈翁の言葉が、言葉ではなく心で理解できるようになった。
諸君は数年勉強の結果、今日この名誉ある卒業証書を貰って初めて社会に出ていくが、諸君が向かう所には種々の敵がたくさんいる。
道徳の腐敗あるいは社会の元気の沮喪などは最も恐るべき敵である。
この敵に向かって諸君は必ず失敗をする。
成功があるかも知れないけれども、成功より失敗が多い。
失敗に落胆しなさるな、度々失敗するとそれで大切な経験を得る。
その経験によって成功をもって期さなければならない。
ところで、この複雑な社会の大洋において、航海の羅針盤となるのは学問である。
諸君は、その必要なる学問を修めたのである。
大隈重信 東京専門学校得業式創立十五周年祝典より(明治三十年)