アントレプレナーシップ人材育成プログラムとして、起業を志す学生のみならず、社会で活躍するための資質として必要なマインド、スキルの習得が可能な各種プログラム(正規科目、非正規科目)として、本学では下記のプログラムを提供しています。
 グローバルエデュケーションセンター(GEC)では、学問分野にとらわれず早稲田大学でしかできない経験を積むための特色ある教育プログラムとして、2017年度より実践型教育プログラムを設置し、「ビジネス・クリエーションコース(以後 BCC)」を提供しています。単位認定される正規科目です。
グローバルエデュケーションセンター(GEC)では、学問分野にとらわれず早稲田大学でしかできない経験を積むための特色ある教育プログラムとして、2017年度より実践型教育プログラムを設置し、「ビジネス・クリエーションコース(以後 BCC)」を提供しています。単位認定される正規科目です。
BCCでは、文系・理系を問わず、全学部生・大学院生向けに、次の3つのステージの科目群を軸に起業や企業における新規事業化の知識を実践的に学ぶことができます。
起業に関する基礎知識に加え、社会で活躍する起業家等の体験に基づく講義により、イノベーション創出や起業に対する考え方やマインドセットを学ぶ。
新しい事業を創造するためのアイデア創造のための様々な手法や実践的なアイデアを考え出す方法について学ぶ。
短期間で新規ビジネスをゼロから立ち上げる「ゼロイチ力」を鍛える。想定顧客へのインタビューによるビジネスモデル仮説検証の実践を通じて、新規ビジネスを創造する方法とプロセスを学ぶ。
*上記3つのステージの科目群から2単位を履修するとともに、Stage4『ビジネスモデル仮説検証プレミアム』または「産学提携科目」の履修により、全体で8単位相当を修得することで、BCCの修了を認定し、修了証明書を発行
2026年3月末までの期間、BCCの科目(一部を除く)は、下掲GTIE事業における②アントレプレナーシップ人材育成プログラムの一環として、同事業の支援を受けて開講されます。
具体的な開講科目などBCCの詳細は下記のリンクからご確認いただき、ご自身のこれまでの学習歴やご関心にあわせて積極的な履修を検討ください。
BCC科目以外も、三菱みらい育成財団助成や篤志家・投資機関等の支援を得て、さまざまな課外プログラムを展開しています。多くのプログラムは早大生以外にもGTIE関係大学の学生や高校生に開放されています。順次内容を更新しますので、ご関心に応じ積極的に参加していただければと思います。
※プログラムの内容は年によって変更されますので、詳細はそれぞれのリンク先よりご確認ください。
成功する起業家がもつ原則を示した【エフェクチュエーション】という考えの一部を使ったワークショップを実施しています。高校生を主な対象としていますが大学1・2年生も参加可能です。
【2023年度は8月1日に開催しました】

※参考:
※エフェクチュエーションについては、社会人も交えて、エフェクチュエーション理論の体感と実践をワークショップ形式で行うイベントも2023年3月5日に開催しました。
◆Effectuation Conference 2023の内容はこちら◆
早大のアントレプレナーシッププログラム関係教員らが登場するオンラインコンテンツを準備しています。主に高校生に向けたコンテンツとなっていますが、大学に入学して間もない方々もぜひご覧ください。
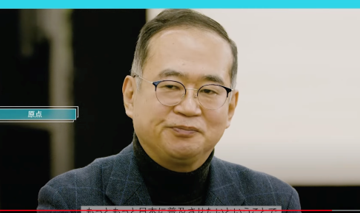

地方自治体や地域のステイクホルダー等と連携しながら「地域イノベーション」をテーマにビジネスアイデアを創出します。
【2022年度は埼玉県本庄市とのコラボレーションで実施しましたが、2023年度は7月26-27日に国分寺市と協力して実施しました。】
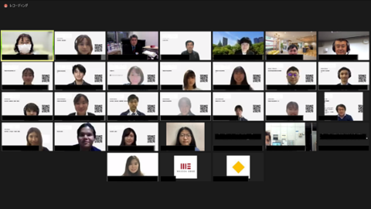
富山県の支援を受けているプログラムです。働きやすさ、暮らしやすさ全国トップクラスの富山県で学生と企業人が共に課題に取り組み、富山県における地域イノベーション・企業内新規事業創造に向けたアイデアを創出します。
【2023年度は8月28-30日に富山市内宿泊の上で開催しました】


医療分野の新製品開発や新規事業は、薬機法の認可や技術的実現リスクなど一般的な新規事業とは異なるリスクプロファイルを有します。この分野での新規事業を効率的に創出するための手法等を体系的かつ実践的に習得してもらうことで、当該分野に挑戦するアントレプレナーを増やし成功確率を高めます。医療現場の困りごとへの共感→医療機器等のアイデア発想から、医療関係者へのインタビュー等を通じたビジネスモデル仮説検証に取り組みます。
【2023年度は9月から10月にかけて対面とオンラインの双方の方法により実施しました。なお、本年度は課外プログラムのみで構成しています。】

米国スタンフォード大学d.schoolでデザイン思考について教えている教員の協力を得た特別ワークショップです。
【2022年度に引き続き2023年度も、W-SPRING(早大博士後期課程生向けキャリア開発プログラム)の一つとして11月に実施し、また本庄高等学院での高校生向け特別プログラムを実施しました。】

◆昨年度の本庄高等学院向け特別プログラムの実施報告はこちら◆
ビジネスアイデア創出や英語ピッチ等に係る国内研修で学生選抜を行い、海外機関でVCや起業家を介した実践的スキルのトレーニングを行います。2018年度より実施しているこのプログラムは、毎年篤志家等からの寄付のサポートを得ています。2018,2019,2022はイスラエルに、2023はメルボルンに派遣しました(2020,2021はオンライン実施)。
【2023年度は3月3日〜3月9日の6泊の現地研修を実施し、4名の学生と2名の社会人を派遣しました。2024年度の実施に向け現在調整中です。】


自らの技術シーズの事業化を目指す学生・研究者を対象とし、「研究者枠」と「事業育成者枠」の参加者が混合でチームを組み、研究シーズを元にした事業化案を練り上げ、発表します。米国バブソン大学の授業に倣い、評価された学生チームが資金(ギャップファンド)を受け取って活動を展開します。
【2024年度の実施については現在検討中です。】
様々なWASEDA-EDGE人材育成プログラムを受講してきた学生を中心として、法人設立及び事業立ち上げを検討している者がアイデア・プロジェクトを発表できる場です。起業家/投資家の前でプレゼンを行い、優秀なチームはスポンサー企業からも賞品を授与されます。
【例年2月に実施しており、2023年度は2024年2月20日に実施しました。】
※上記以外のプログラムが新しく企画され、募集を行うことがあります。ぜひアントレプレナーシップセンターのウェブサイトとtwitterにご注目ください。
https://www.waseda.jp/inst/entrepreneur/
https://twitter.com/Waseda_Entre
上記のような多彩なアントレプレナーシッププログラムは、下記のような外部機関からの助成を得ながら実施しています。

Greater Tokyo Innovation Ecosystem(GTIE),JST「研究成果展開事業 大学発新産業創出プログラム(START)スタートアップ・エコシステム形成支援事業」)は、国際競争力の強化、スタートアップの創出や成長、Greater Tokyoの経済の持続的な発展を実現し、また、エコシステムによるイノベーションを社会に実装し、地域に還元する活動を行うことを目的とした「スタートアップ・エコシステム東京コンソーシアム」に参画する、大学と地方公共団体、大学発イノベーションの取り組みをさまざまな形で支援する民間機関が結集して進めるものです。 具体的には以下の①から③の取組を、2025年度にかけて実施していきます。
①起業活動支援プログラム
東京工業大学を中心として企画運営したギャップファンド(GTIEサーチファンド)を2022年度以降設置し、PoC活動のほか、メンタリングの提供、経営者人材とのマッチングなどの支援を行います。
②アントレプレナーシップ人材育成プログラム
EDGE‐NEXTプログラムで主幹機関を務めてきた東京大学、早稲田大学がそれぞれ実施していたプログラムを総動員し、本構想のステイクホルダーにシームレスに提供でき、コンソーシアムの受講を希望する全ての者がプログラムを受講できる体制の構築を目指します。特に早稲田大学では小中学高校生への教育プログラム、東京外の地域も含めた社会的課題の解決に係るプログラムに取り組むほか、海外機関との協働プログラムや、仮説構築・検証などの手法において国際通用性の高いプログラムを重点的に実施します。
③拠点都市のエコシステムの形成・発展
GTIEおよび東京コンソーシアムの参画機関のネットワークを相互接続し、特に海外ベンチャーキャピタルやアクセラレーターなどとの協業・イベントなどを積極的に進め、ユニコーン創出の確度を飛躍的に高めます。
早稲田大学は、スタートアップ・エコシステム 東京コンソーシアムの理事機関であり、現時点において文部科学省次世代アントレプレナー育成事業(EDGE-NEXT)とJST SCORE(大学推進型)および拠点都市環境整備型といった、大学発スタートアップの創出・育成に係る機関申請事業のすべてに採択されている唯一の機関です。国内外の機関との協業の下での実践的な起業家育成プログラムや、ビジネス創出支援に長けた国内外の専門家の協力により研究シーズから社会的価値の創出を目指すPoCプログラムの運営の実績を踏まえつつ、学内資源をより結集した支援体制を構築し、東京コンソーシアムとの綿密な連携の下で、東京を拠点としたイノベーションエコシステムの構築に貢献していきます。

アントレプレナーシップ教育(WASEDA-EDGE人材育成プログラム)の豊富な実績を基盤に、学内外連携先の強みと英知を結集し、高校生〜大学1,2年生に先端的なアントレプレナー教育を提供し、社会・産業構造の変革を起こす意欲を備えた、将来起業あるいは社内での新規事業創出等による多様なイノベーションを担う候補生であるW-EDGEユース・イノベーター(WEYI)を育成します。