日本のビジネス文化に苦労しながらも、自分の「本当にやりたいこと」が実現できる職場へ
先輩からのメッセージ(1分動画)
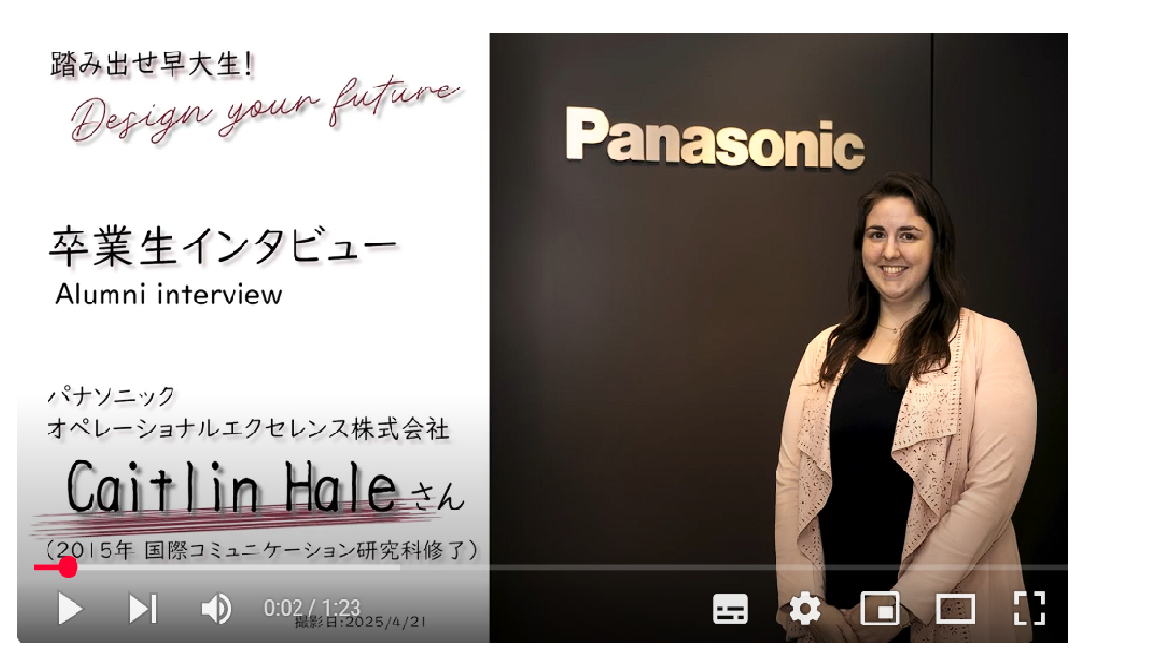
取材にご協力頂いた方:
パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 ヘイル ケイトリン(Caitlin Hale)さん
2015年 国際コミュニケーション研究科修了
2度の交換留学の経験から早稲田大学大学院へ進学、そして日本での就職を意識
私が日本に興味を持ったきっかけは、高校時代の日本留学です。私が通っていた高校は日本の高校と姉妹校のような関係があり、その交換留学プログラムに参加しました。初めて来日した時は英語しか話せませんでしたが、日本語を勉強することに面白さを感じ、アメリカの大学で本格的に日本語を学び始めました。専攻は言語学で、英語や日本語そのものというよりは、脳科学や心理学に近い分野です。在学中は勉強の傍ら、言語学や日本語、歴史の授業のチューターや、アメリカに来ている留学生に対する英会話のサポートも行っていました。
大学3年生の時には、交換留学で早稲田大学を訪れました。当時の経験から日本で言語学の研究を続けたいと考え、大学卒業後は早稲田大学大学院国際コミュニケーション研究科に進学。大学院では、研究はもちろん、趣味で日本各地を旅行して回るなど、充実した時間を過ごすことができたと感じています。
修士課程後のキャリアを考えるタイミングでは、博士課程への進学も視野に入れていました。しかし、研究職や教員の道に進むのは、社会人を経験した後でもできるのではと考えるように。これまで学んだ日本語や言語学が生かせる、コミュニケーションに関わるような仕事につきたいと思い、就職活動をスタートしました。
日本ならではの就職活動文化に対応しつつ、企業との相性を見極めることが重要
就職活動で苦労したのは、やはり言語の壁です。私がよく行っていたのは、日本の映画やドラマを字幕・音声ともに日本語で見ることです。リスニング力と漢字の知識を一度に身につけることができます。「話す」力については、友人との会話をはじめ、日本語を話す機会を積極的につくっていました。また、就職活動ではビジネス表現や敬語など、普段使わない語彙に戸惑うこともあります。就職活動や面接を通じて慣れていくことに加えて、私は日本語能力試験(JLPT)のN1レベルの取得を目標にしていました。いきなり目指すのは難易度が高いため、まずはN2レベルやその他の資格取得を目指すのも一つの方法です。言語の壁に加えて、日本の就活の「暗黙の了解・知識」にも苦労しました。表面的な表現と本当の意味の違いを理解するのにも時間がかかりましたし、次のステップが何か、どこで情報を得れば良いのかもわかりませんでした。周囲に外国籍の先輩も少なく、情報収集には苦労しましたね。修士論文を前倒しにして就職活動にかける時間を確保したり、就職に特化した日本語の授業を受けたりして、念入りに準備をしました。
そしてもう一つ大きな悩みだったのが、外国籍であることをどこまで打ち出していくべきかということ。たとえば他の学生に合わせてリクルートスーツを着ていった際も、「日本に合わせてくれてうれしい」と言われたり、「日本に合わせなくてもいいのに」と言われたりと反応はさまざまです。外国籍に寄せられている期待や、それをどの程度アピールすべきなのか、そのバランスがとても悩ましいものでした。ただ、その反応を通して、企業ごとの文化や価値観の違いがよく見え、企業との相性を見極めるヒントにもなりました。そうした意味でも、面接などでは無理に飾らず、ありのままの自分で望むことが大切だと思います。
企業探しでは、「人と会社とのコミュニケーションから喜びを生み出せる仕事」を志していました。加えて、日本語と英語の両方が活かせる国際的な仕事がしたいという希望や、自分の意思でキャリアを柔軟に選びたいという思いがあり、幅広い事業に取り組む会社を探していました。そうした中で出会ったのが、現在の職場であるパナソニックグループです。国内外での幅広い事業や業務、そして「社会の公器」という理念をもとに、利益だけでなく社会や人とのつながりを大切にする姿勢に強く惹かれました。後から気づいたことですが、当時住んでいたアパートの家電はすべてパナソニック製でした。無意識のうちに「いい会社だな」と感じていたのかもしれません。会社の魅力を発信する仕事がしたいと思っていた私にとって、自然な選択だったと今では思います。
お客様だけでなく社員からも「いいね」と思ってもらえる会社を目指して
今年の4月でパナソニックグループに入社してちょうど10年目になります。比較的短期間で頻繁に異動しており、広報や映像制作、広告の制作、採用コンテンツの発信・制作などさまざまな業務を経験してきました。また、人事部門として役員の社内外コミュニケーションを担当したり、ブランド戦略に携わる機会もありました。現在は会社の歴史を伝える部署に所属しており、「コーポレート・コミュニケーション」という枠組みの中で多岐にわたる分野に関わっています。また、社内には勤務時間の約20%を別の部署で働ける「社内複業」制度があり、私も1年半活用しました。発信の立場としてグループ全体を俯瞰し、さまざまな人や技術を取材するなど、日々新しいことに関わることができるよい機会でした。
私のやりがいは、「この会社がいいね」と思ってもらえるような仕事に携われること。お客様だけでなく、従業員の皆さんにもやりがいを感じてもらい、また「この会社にいてよかった」と思ってもらえるような情報やメッセージの発信を目指しています。たとえば、取材された方自身がその経験を誇りに感じたり、嬉しく思ったりしてくれることがあります。また、コミュニケーションを通じて一人ひとりの挑戦意欲や、これまで培ってきたスキルや能力を最大限に引き出せることも魅力の一つ。たとえば、これまであまりスポットライトが当たってこなかった取り組みに注目を集めることで、思わぬ反響や効果が生まれることもあります。何十万人に影響を及ぼす仕事は大きな責任が伴いますが、同時にやりがいや誇りを感じます。
後輩へのメッセージ ~自己分析で「自分の軸」を発見し、それに合う企業選びを ~
就職活動では、「自分の軸」をしっかり持つことが重要です。私は「人を喜ばせたい」という思いがあり、コミュニケーションを通じてそれを実現したいという明確な志向がありました。自分に合うもの、自分が大切にしている価値観、思いは人それぞれです。だからこそ、まずは自分自身と向き合って、自分のやりたいことを就職活動の軸にすることがとても大切だと思います。それを実現するためにはどんな仕事や業界、職種があるのか。最初は曖昧でもいいので、少しずつ自分の目指す方向をはっきりさせ、整理しながら自己分析をしていきましょう。
また、自分のやりたいことに対して、この企業は合っているのかどうかを判断するためにも、情報収集が重要になってきます。いろいろな会社が実施しているセミナーや、ネット上に発信されているコンテンツを活用して、できるだけ多くの情報に触れることが大切です。会社の価値観やスタイルを知り、自分がいいなと思える場所を探していきましょう。「もしかしたらこの会社は自分には合わないかも」という感覚も大事にしてよいと思います。自分の軸を貫き通せる場所で、自分のやりたいことを実現するために、妥協せず企業選びや情報収集に取り組んでみてください。


