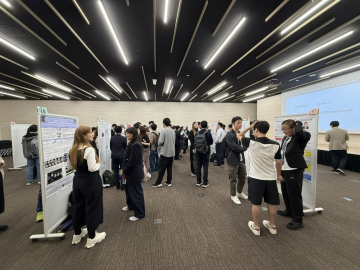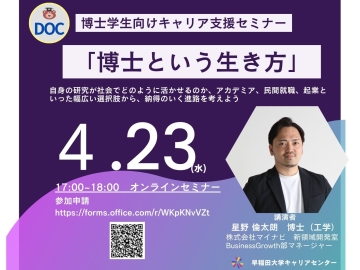ジョブ型研究インターンシップ体験インタビュー
トヨタ自動車株式会社 東富士研究所

産業界へのキャリアパス拡大や博士課程の魅力を向上させる取り組みとして始動した、ジョブ型研究インターンシップ。「研究遂行の基礎的な素養・能力を持った大学院学生」を対象に、原則2カ月以上、有給、企業側によるジョブ(職務)の提示、大学側での単位科目の扱い、などが特徴です。早稲田大学では、昨年度に続き、今年度も博士後期課程より1名が参加。参加した動機、インターンシップ前後での意識の違い、今後のキャリアなどについて語っていただきました。
キャリアの可能性を広げる一歩を踏み出し、
自身の適性を知る大切な時間

早稲田大学 創造理工学研究科総合機械工学専攻
草鹿研究室 博士後期課程2年
青山 颯汰氏
自身の研究内容ほか、企業との共同研究、学会での交流が参加の決め手に
– ジョブ型研究インターンシップ制度について、どのように知りましたか。
私が在籍の研究室には、在籍以降、博士前期課程から博士後期課程に直接進学した学生がいなかったため、同制度に関する情報はほとんど入ってこなかったのですが、早稲田大学の博士学生を支援するW-SPRING(早稲田オープン・イノベーション・エコシステム挑戦的研究プログラム)に採択されて、そこでジョブ型研究インターンシップに登録することになったことをきっかけに知るようになりました。企業現場ではどのように研究が行われているか、そして、自分の研究がどのように企業の開発で生かされるかなどに関心が湧き、応募しました。
– インターンシップ先はどのように選んだのですか。
 大学では、自動車に関連する三元触媒という後処理システムの研究をしています。三元触媒とは、自動車の排ガスに含まれる炭化水素(HC)、一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)という三種の有害物質を同時に浄化する触媒をいい、これを化学反応ベースでモデリングを行ったうえで、この触媒がどのような性能を発揮するかを予測するのが主な研究内容です。今回のトヨタ自動車の「職務内容」に、将来パワートレーンの開発やエミッション低減技術の先行開発とあったのが、インターンシップ先を選んだ大きな動機です。実は、大学の研究活動の中でトヨタさんを含めたいくつかの企業と共同研究しており、その中で、触媒の浄化性能を予測したうえで、それぞれの触媒を評価していました。また学会等でも、今回メンターになっていただいた中山さんはじめトヨタの方とお会いしており、すでに繋がりがあったことにもご縁を感じました。
大学では、自動車に関連する三元触媒という後処理システムの研究をしています。三元触媒とは、自動車の排ガスに含まれる炭化水素(HC)、一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)という三種の有害物質を同時に浄化する触媒をいい、これを化学反応ベースでモデリングを行ったうえで、この触媒がどのような性能を発揮するかを予測するのが主な研究内容です。今回のトヨタ自動車の「職務内容」に、将来パワートレーンの開発やエミッション低減技術の先行開発とあったのが、インターンシップ先を選んだ大きな動機です。実は、大学の研究活動の中でトヨタさんを含めたいくつかの企業と共同研究しており、その中で、触媒の浄化性能を予測したうえで、それぞれの触媒を評価していました。また学会等でも、今回メンターになっていただいた中山さんはじめトヨタの方とお会いしており、すでに繋がりがあったことにもご縁を感じました。
非常に濃いスケジュールの中で効率的にこなす術が身に着いた
– どのようなスケジュールで行われたのでしょうか。
期間は7月22日から10月18日までの3カ月弱です。勤務先は静岡県にある東富士研究所でしたが、その間でも大学の研究活動は続いていたので、概ね2週間ごとに静岡と東京とを行き来しつつ、静岡では8:30~17:30で勤務して、東京では朝、テレワークで仕事をした後に大学に行くという生活でした。期間中、学会発表のための予稿原稿の提出や発表資料作成をするなど自分の研究でもやることがあり、必要に迫られる中でいろいろなことを効率的にこなす術が身に付きました。インターンでは、ジョブディスクリプションによってやるべきことが明確化していたことも効率化につながったと思います。振り返れば、非常に濃い3カ月でした。
– インターンシップで苦労したこと、印象に残っていることなどお聞かせください。
苦労した点では、一人暮らしをしたことがなかったので、生活面で若干苦労しました。むしろ、職場にいるときのほうが安定・集中していたかもしれません。また、給料をもらう立場上、ある程度の目標は達成しなければならない・成果を創出しなければならないという焦りが、特に後半にはありました。印象の点では、自分の研究である三元触媒とは異なる上流側のことを学べたこと、そして、エミッションをどう低減していくかという課題を、一から考えられたことが大きな成果(経験)だったという印象があります。ほか、歓送迎会には多くの方に集まっていただき、大変嬉しく感じました。
いずれの道に進むにせよ、企業の世界を経験することで知識・知見が広がる
– インターンシップ就業前と就業後とで、就職や研究活動に対して考え方が変わったことはありますか。
 就職に対する考え方は大きく変わりました。そもそもジョブ型研究インターンに参加した理由の一つが、今後のキャリアをどう形成するかにあったので、最初にこれを職場のみなさんに伝えました。それに対して、トヨタのありのままの様子を見せていただいたことで、同社に入社する意思も芽生えましたし、採用方針についても知ることができました。
就職に対する考え方は大きく変わりました。そもそもジョブ型研究インターンに参加した理由の一つが、今後のキャリアをどう形成するかにあったので、最初にこれを職場のみなさんに伝えました。それに対して、トヨタのありのままの様子を見せていただいたことで、同社に入社する意思も芽生えましたし、採用方針についても知ることができました。
修士課程学生の時に行っていた就職活動の時にはアカデミアに進む考えはあまりなく、修了後はメーカーか国の研究所を考えていました。修士1年のときに、オンラインによる3日間のインターンシップに参加しましたが、今回、長期のインターンシップを経験したことで、いくつかある選択肢のうち、自分の適性がどこにあるのかを見出す理由探しができたとも言えます。
– 最後に後輩の皆さんに向けたメッセージをお願いします。
ジョブ型だからこそ、長期に参加して企業を深く知ることができます。私も、大学で共同研究していたとき以上に、トヨタさんの印象は良くなりました。アカデミアの道を志望する人でも、一度、企業の世界を経験してみれば、知識や知見がずいぶん広がるはずですし、後に学会などで企業の方とお会いしたときに有意義な議論ができる関係を築くことができます。また、職務が自分の研究内容に近ければ、研究を違う視点で見ることができたり、研究の意義を深く理解できたりします。ともすれば、博士課程にいるだけでは自分が社会の中でどれほどの位置にいるのかがわからなくなります。その意味で、ジョブ型研究インターンシップは自分の力がどこまで通用するかを知るいいチャンスになります。
メンターの声

トヨタ自動車株式会社
パワートレーン先行開発部先行機能開発室
伊藤 弘和 氏
今回のジョブ型研究インターンシップでは、OJTを通じて仕事の目的や進め方を共有し、仕事の流れを体感していただきました。
インターン期間の始めにプロジェクト全体の目的や企業の研究所としての視点も共有したうえで、プロジェクトの一部である「自動車のエミッションを下げる」に対して、触媒でどのように効率よく低減していくかを一緒に考えてもらうようにしました。ご本人のこれまでの大学での研究と比較して扱う範囲が広くなる様子だったため、いくつか刻んだ仕事のステップの中で、進め方を議論し、自身で業務を組み立ててもらうようにしました。設定した中間目標に到達する期間をあらかじめ共有し、以降は、毎日会話をしながら進め方を相談していきました。今回は大学との両立が必要とのことで、仕事の計画は2週間をひと区切りとしてマイルストーンを設定しました。
インターン生といっても博士課程の学生なので、私たちが持っていない知見をお持ちの場合がありますから、教えるだけでなく、われわれが教わることも少なくありませんでした。その意味で、会社の人間からではない「見え方の違い」に気付かされました。青山さんには、今後一緒に働けたら良いなと思いつつ、今回得た経験が生きてくれば嬉しい限りです。
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
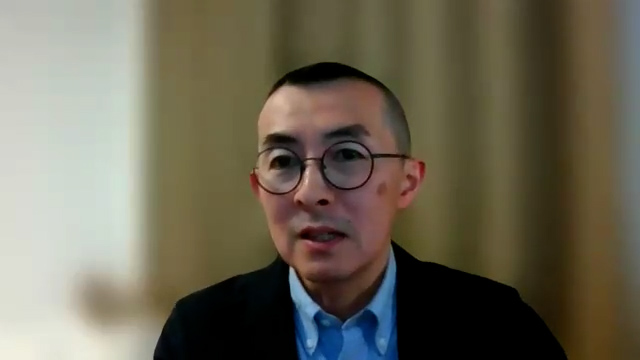
トヨタ自動車株式会社
パワートレーン先行開発部先行機能開発室
中山 茂樹 氏
ジョブ型研究インターンシップは自職場では新しい取り組みであり、私たちが持っていないような知識を持つ人を迎えることで、新しい視点で仕事を見る機会を与えて頂けました。また、従来難しいと思っていたことが、新たな知見で解決できるかもしれないという期待を抱きながら、いわば「仲間」が加わる感覚でした。
従来、新入社員の配属はジョブ型ではなかったため、本人の希望に沿わない場合もあったようです。ジョブ型の場合は入社後最初に担当する業務に馴染みやすいと思われますが、仮に専門と違う業務内容の部署に配属された場合にも、知識や業務経験の幅が広がりやすい利点もあるようですので深く考えすぎる必要は無いように思います。今回は長期インターンシップということで、企業での開発現場を感じて頂けるように、メンバーも自然体で接するように努めました。今後の進路を考える際の良いご経験になったなら幸いです。