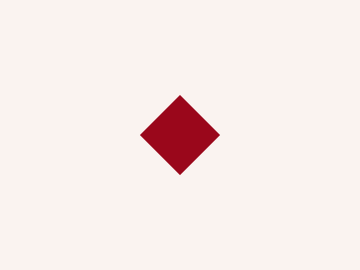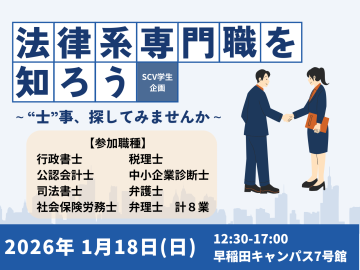広野 彩子(Hirono Ayako)
1993年政治経済学部経済学科卒業。新卒で大手新聞社に入社し、2001年1月から日経BP社の経済週刊誌「日経ビジネス」の記者に。2005年米プリンストン大学大学院修士課程修了。2016年4月から2年間日本経済新聞社Nikkei Asian Review編集部に出向。現在は日経ビジネス副編集長。
大学ではジャーナリズムと決めていた
もともと大手紙の新聞記者をしていた父親の影響もあり、大学ではジャーナリズムを勉強しようと高校生の頃から決めていた。政経学部だけを狙っていたのは、昔新聞学科があり、ジャーナリズムの伝統があると聞いていたから。経済学科だったがゼミはマスメディア論を学ぶゼミに入った。経済学科の学生と政治学科の学生が半分ずつで、社会科学系の学術書を読みながらディスカッションした。その流れで就職先も報道一筋かというと、迷いもあった。出版社や銀行・証券会社などの大企業も見た。だが出版社は基本的には報道の現場取材がなく、当時のいわゆる大企業はまだ女性が活躍できる状況ではなかった。「ここまで勉強してきて結局補助的な仕事で終わるのは嫌だ」と思った。また父親が優秀な女性記者の話を聞かせてくれ、男女で同じ仕事をする機会が与えられることを知っていたこともあり、「女性でも評価してくれる人がいるかもしれない」との希望をもって報道の道を志した。あえて父の会社は受けなかった。
社会人1年生
書くことが得意だったこともあり、その後トントン拍子で大手新聞社に入社が決まった。研修を終え、配属されたのは鳥取支局。会社が無利子で貸し付けてくれた100万円で新車を買い、カメラを買い、記者1年目の生活が始まった。朝は6時から7時頃に起きて宿直明けの警察官(6~7署)に電話し、報道しなければいけなさそうな事件・事故がなかったかを聞く。何かあれば実際に署にも顔を出し、昨日起きたことの詳細を聞く。たいていは何もなく平和で、初めて書いた仕事はしいたけ栽培のビニールハウスが全焼した火事だった。受け手側の感覚では小さなニュースのように思えるこの火事も、当事者にとっては死活問題。オーナーであるおじいさんは「明日からどうすればいいのだろう」という感じで絶句して現場を見つめていた。この現場で学んだのは「視聴者(ニュースを消費する側)としては大きな事件ではないかもしれない、だがたった15行のベタ記事の行間には、感情や人間関係や人々の生活の詳細がつまっている。報道は切り取って社会的に重要な部分だけを伝えるが、伝える側はできるだけたくさん、あえて書かない部分も知ってから書かなければいけない」ということだった。
報道って、何だろう?
そんなこんなで1年が経ち、鳥取で2年目を迎えた。年が明けた1月17日、阪神淡路大震災が起きた。上司の命令で急いで飛行機で現場に向かい、阪神支局で仕事することを命じられ、体育館などの避難所や遺体安置所でカメラを片手に8日間、ほとんど寝ずにがむしゃらに働き続けた。現場ルポを書くために被災者と共に避難所に宿泊して、夜中の余震の恐怖も味わった。鳥取に戻ってからは過労で1週間くらい高熱を出して寝込み、その後も1,2か月は頭の中でサイレンが鳴り続け、実際にサイレンが鳴ると、びくりと怯えた。しかしその中でも一番、今後の記者人生を左右するぐらい大きな出来事が、遺体安置所での遺族の取材中に起きた。停電のため真っ暗な部屋の中で、娘さんを亡くしたらしき男性が泣いているのを見つけた。男性が出てきたので、朝刊のために何か話を聞かなければと思い、「どうしたんですか?」と声をかけると彼はポツリポツリと事情を話し出てくれたのだが、ふと我に返って、「…あんた誰や?」と強い口調で尋ねてきた。「○○新聞社の者です」と言うと、男性は「場所をわきまえろ!」と怒鳴り、ぶわあっと崩れるようにしゃがんで泣き出してしまった。その瞬間、「自分はなんてことをしてしまったのだろう。最悪だ、傷つけてしまった」とものすごいショックを受けた。仕事をしなければいけないけれど、聞かなければいけないのだけれど、自分の仕事が相手を傷つけてしまう。「自分は何をやっているのだろう」「事件記者って何だろう?」「災害報道って何なんだろう?」と、言葉にならないモヤモヤが心の中に芽生えた。
決断は突然迫られる
さらに、ニュースを世の中に知らせることに社会的意義はあるのだけれど、はたして自分はそれで幸せなのだろうか?という疑問が生まれてしまい、しばらくスランプに陥った。鳥取の次は京都に配属されたのだが、そこでは鳥取以上に大きな事件・事故が起き、より一層必死に働いた。しかし身体はボロボロで、体調を崩した。ストレスで急性虫垂炎になり緊急開腹手術を受けたり、首全体に真っ白なアトピー性皮膚炎を発症したり、小腸にびらんができて、長い間食事制限を受けた。そんな中、大阪の整理部に異動することになった。「社会部に来ないか?」と誘ってくれた先輩が何人もいたが、そこに男性と同等に機会を得て働ける保証はないように思えた。「たとえたくさん特ダネをとってもお前は所詮女だから」と言われることも多く、まだまだ女性差別があからさまに根深く残る時代だった。女性が活躍できそうな環境を求めて外資系メディアへの転職を考え始め、米国か英国の大学院留学をしようと決めたのもこの頃だ。震災報道の経験から、より前向きな報道にかかわれそうな経済部を志向するようになっていたので、整理部異動は不本意だったが、整理部はシフト勤務。この機会を最大限利用しようと考え、英語の勉強を本格的に始め、空いた時間はほぼすべて英語学習に費やし、英検1級を取り、通訳学校に通った。学習日記を主体とする英語学習のホームページを開いたら、数多くのアクセスが集まって、ネット上で切磋琢磨する友人がたくさんできた。
そしてチャンスは突然やってきた。英語の勉強をしていると聞きつけた上司が、新聞社で海外留学を推薦してくれるというのだ。しかし全く同じ時期に日経ビジネスの記者をやっていた知り合いから、今度中途採用をするからぜひ受けてみないか、ととても熱心な誘いを受けた。「どうして同じタイミングでくるのだろう」。二つの選択肢で迷っていた矢先、横浜に住んでいた父親が吐血して倒れた。生死の境をさまよい、母親が動揺している様子が伝わってきた。「海外留学にも行きたいけれど、今は家族のために東京に帰らなくては!」と思い、転職を選んだ。
経常利益って何ですか?
日経ビジネス記者になったものの、最初は財務諸表の読み方もわからず、まさにゼロからのスタートだった。当時お世話になり影響を受けた先輩が米コロンビア大学のジャーナリズムスクールを出ていた影響もあり、やはり自分も海外で勉強したいという思いが、突き動かされるように一層強まった。しかしそう思ったのはまだ入社してから一年も経たない時期で、女性はすぐに辞めるだろうと思われていたため、上司が推薦してくれたにもかかわらず社費留学で行くことはかなわなかった。だが熱意を伝え続け、「どこか受かったら、来年何とかしてやれるかもしれない」と上司に言ってもらうことができた。そこからはさらに、猛烈に仕事もしながら猛勉強、準備に準備を重ね、CWAJ(College Women’s Association of Japan)という、在日の様々な国籍の女性らがつくる、女性らの留学を支援する奨学金団体から給付型の奨学金をいただくことも決まり、見事ハーバード・コロンビア・プリンストンの政策系大学院の合格を勝ち取った。その中でも一番講義のレベルが高く思え、また学費免除で生活費支給という好条件だったプリンストンに入学を決めた。日本国内での知名度より、自分の力になる環境を最優先に選んだ。これは高校時代にちゃんと勉強をしてこなかった反動からくるものだった。「新聞記者時代も知識不足や視野の狭さから自分の限界を感じていた。やはりもっと海外に出ないといけないし、もっと勉強しなくてはいけない、こんな自分で終わりたくない!」。
自分で自分を「放り投げた」1年間
休職扱いで留学できる制度を会社に新設してもらい、1年後にはまた職場復帰するということで、結局会社からは一銭も受け取らずにスタートした留学生活。海外経験もほとんどなく、横浜市の公立の小中高で学び、ESSなどの経験もなかった。超ドメスティックに育った人間が、知り合いが一人もいない環境で、しかも国語が一番得意なのにその強みが生かせないという異言語空間。まさに身一つの挑戦は本当に大変だった。しかしクラスメートには米国の女性外交官や米軍の女性パイロット、インドのエリート官僚など様々なキャリアを持った多様な仲間たちがいて、全員で助け合いながら切磋琢磨し、お互いの国に対して文句も言い合いながら、ここで一生分の勉強をしたというくらい濃い1年間を過ごした。現地で過ごすうち、様々なチャネルを通じ英語で伝わっている米国や日本に関する情報と、日本のメディアが伝える米国や日本の政策情報がかなり異なることに気付き、日本では統計分析含め重要な知の訓練がなおざりにされていると感じた。日本に帰ってきてからまずは「日本人には知られていない先端のアカデミアを日本人に伝えたい。それは日本にとって重要ではないか」と考えながら、様々な新規事業に携わった。日経ビジネスオンライン(当時はNBオンライン)の開発メンバーとなり、沢山の新コラムを立ち上げた。リーマンショックによって中止になってしまったが『日経ビジネスマネジメント』という“理論から実践に落とし込む”発想でつくるアカデミックな季刊マネジメント誌の実験的な開発を任されるなど、様々な新しい仕事をした。この頃、行動経済学者のリチャード・セイラー氏をはじめ数多くのノーベル賞経済学者や著名な欧米の経営学者に次々とインタビューをして、記事として発信し続けた。
変化と試練は、人生のスパイス
ただ、海外の最先端を伝えるだけが、やりたいことではなかった。根底に変わらず流れているのは「世界に向けて日本から自分が発信したい」という、留学中に感じた強い思いだった。外資系メディアで外国人寄りの視点から日本のことを発信するのではなく、日本で生まれ育った自分が、日本人として海外に発信をし、世界の人に日本や日本人の良いところをもっと分かってもらいたい。外国人の目から見る日本の姿が誤解されているようだったら、違うということをきちんと伝えたい。「日本を正しく理解してほしい。やはり世界の人々とコミュニケーションをしないといけない」。2年間のNikkei Asian Review出向を終え日経ビジネスに戻ってきたが、今もそうした思いは変わらず、何か新しいことに関わりたいと考えている。
後輩に向けてメッセージ
学生の皆さんに伝えたいことは、今の自分が持っているもので将来の自分を決めつけないでほしいということ。今、皆さんが、学生時代の私がそうだったように何も持っていないように思えても、あるいは隣の恵まれた環境で幼少期を過ごしたバイリンガルの学生がまばゆすぎてかなわないような気がしても、そんなことは人生の中で大した意味はない。言語は結局ツールにすぎず、自分という人間がどんな「コンテンツ」を世の中に生み出し、貢献できるのかが何より重要。私は高校時代、陸上競技部で短距離走者だったけれど、人生は長いマラソンレースみたいなもの。変化や試練をスパイスに、それを楽しみながらマイペースに走り抜けていく中で、きっとなりたい自分に近づくことができる。
インタビューを終えて
まずはじめに、「学生のためになるなら!」とインタビューを引き受けてくださった広野さんに感謝の意を表したい。ご自身が体験されたことを赤裸々に話してくださり、貴重なお話を聞くことができた。自分は今回のインタビューの前まではジャーナリストになりたいと考えていたが、厳しい仕事の話を聞いて「果たして自分に務まるのだろうか?本当に自分がやりたいことなのか?」と正直自信をなくしてしまった。しかし熱意によって留学を実現させたこと、前例のない制度を会社に創ったことなど、とても勇気づけられた。そして、きっとどんな仕事であれ甘くはないのだと改めて思った。エンパワーしていただきありがとうございました!(文化構想学部3年 水庫郁実)
地方支局にいた新人時代の阪神淡路大震災の経験から、記者という職業に疑問を持つようになったというお話が印象的でした。広野さんのお話を伺い、仕事は大変なものなのだな、と思うと同時に、お話の内容やお話されている様子から、広野さんの温かいお人柄や心の強さが伝わってきました。内容も大学に普通にいるだけでは聞けないような貴重なお話でしたが、何より、広野さんご自身の努力や才能以外にも、人と信頼関係を築く力や精神的なタフさといった広野さんの人間力によって、転職や留学など様々なことを成功なさってきたのだな、と学びました。(政治経済学部3年 H.K)
このインタビューはキャリアセンターの学生ボランティア「学生キャリアスタッフ」が企画・実施しました。