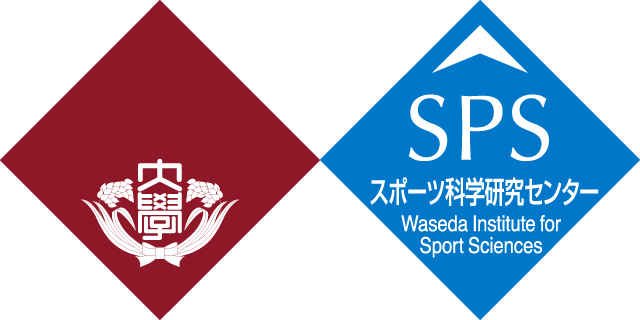- その他
- 所沢 スポーツサイエンス研究会(2015年度)
所沢 スポーツサイエンス研究会(2015年度)
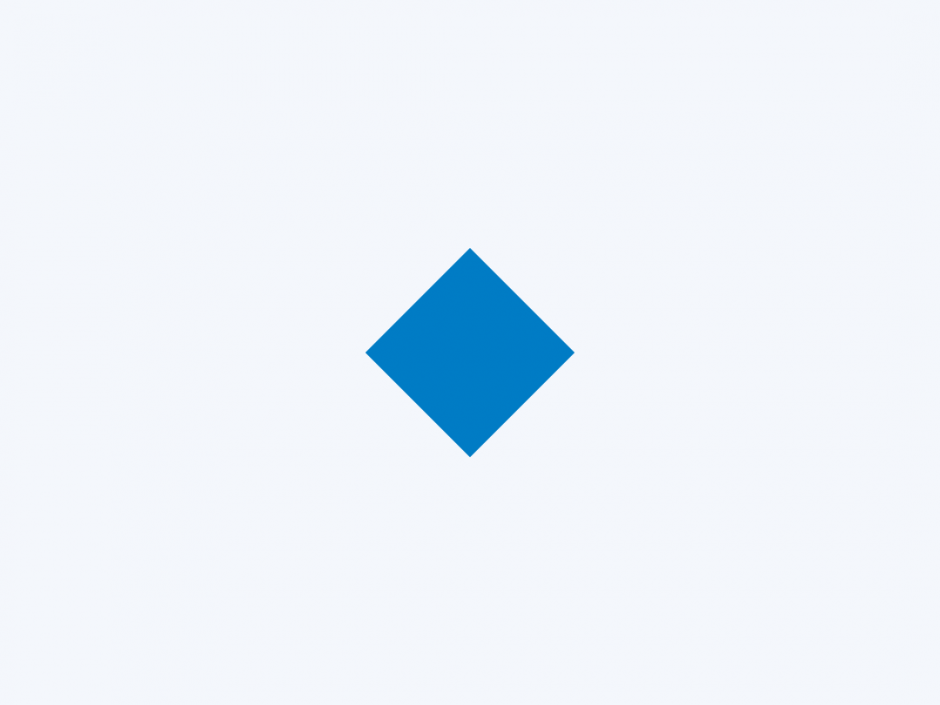
- Posted
- Wed, 16 Dec 2015
第154回 兼 2015年度 修士論文発表コンテスト 2月8日(月)13:00より
<セッション1> 座長:永見智行 先生
- 一過性レジスタンス運動が脳血流量および動脈スティフネスに及ぼす影響 中村宣博(村岡研究室)
- 健康の殿堂―19世紀後半のアメリカにおけるYMCAと「筋骨たくましいキリスト教」― 松下大樹(石井研究室)
- 個別の運動スキル要素と複合した運動スキルの相違 渡部潤(彼末研究室)
- 中国武術のグローカリゼーション―日本における中国武術の受容と変容を事例に― 劉暢(志々田研究室)
- 2012年ロンドンオリンピック・パラリンピックのスポーツレガシー~構造分類フレームワークを使用して~ 小川祥加(間野研究室)
<セッション2> 座長:舟橋弘晃 先生
- 学童期における副菜摂取が栄養摂取状況及び全身持久力に及ぼす影響 遠藤有香(田口研究室)
- 大相撲観戦する訪日外国人のスポーツ旅行行動に関する研究:大相撲観戦ツアーに着目して 高田紘佑(原田研究室)
- 体幹スタビリティと各種パフォーマンスの関係 久保孝史(樋口研究室)
- Jリーグクラブにおけるトリプルミッションモデルの定量的分析に関する研究 奥下諒(平田研究室)
- 送風による中間冷却が間欠的運動能力および認知機能に及ぼす影響 坂井禎良(広瀬研究室)
- 側方動作時における慢性足関節不安定症の下肢キネマティクスとブレースの効用 大澤健介(福林研究室)
<セッション3> 座長:松下宗洋 先生
- 水球競技の投球動作におけるボール速度に対する体幹および上肢の貢献 塩田義裕(矢内研究室)
- 小型センサを用いたスケーティング動作の推定 橋本航一郎(誉田研究室)
- スポーツ・スポンサーシップにおける関連性説明の活動がスポンサーシップ効果に与える影響:創造されたスポンサーフィットとスポンサーに対する態度を従属変数として 姜泰安(松岡研究室)
- 埋め込み理論を用いた地域のスポーツ産業クラスター内の組織間ネットワーク構造の様相:ネットワークの形成と発展プロセスに焦点をあてて 長尾百合子(武藤研究室)
- スペイン代表におけるゲームパフォーマンスの変遷―2010W杯・EURO2012・2014W杯を対象として― 竹中達郎(堀野研究室)
- トレーニング期別にみたアスリートの睡眠時間・身体疲労度と身体パフォーマンスに関する研究 出町奉丈(内田研究室)
結果
第1位 塩田義裕(矢内研究室) 第2位 高田紘佑(原田研究室)第3位 坂井禎良(広瀬研究室) 第4位 姜泰安(松岡研究室)
第153回 2月3日(水) 16:30より 所沢キャンパス 100号館 5F 第一会議室
演題
世界のトップコーチングの今: トップ・コーチ像から見える専門性とそのコンピテンシーに着目して
演者
勝田隆先生(国立スポーツ科学センター)
内容
「コーチ」に類似した呼称は多様であり、「指導する者」という意味で捉えれば、トレーナー、デベロッパー、メンターなどがある(勝田,2003)。また、チームゲームに目を転じれば、「ヘッドコーチ」、「ポジションコーチ」、「コーチング・ディレクター」、「コーチング・コーディネーター」なども散見される。このような呼称の多様性は、コーチングの分業化あるいは専門化を示唆するものと考えられ、この特徴は、特に高度化および国際化する今日のトップスポーツ強化組織において顕著である(JRFU,2015)。ここでは、国際競技力強化に関する組織における、分業化および専門化したコーチングの今日的な動向に着目する。特に、国内外で活躍するボールゲームのトップ・コーチを事例的にとりあげ、それぞれ求められる職務(jobdescription)やコンピテンシー(competency)などについて検討を加え、世界のトップコーチングの現状について論じる。
ここでの検討と考察が、我が国のコーチング教育および研究活動に対して、さらなる深化と広がりをもたらす一助となれば意義あることと考える。
第152回 12月1日(火) 16:30より 所沢キャンパス 100号館 5F 第一会議室
演題
Coordination dynamics of whole-body rhythmic sensorimotor synchronization:
A comparison study of street dancers and non-dancers
演者
Dr. Akito Miura(Waseda University, Japan)
内容
I applied dynamical systems approach to basic street dance coordination pattern, and revealed two distinguishable coordination modes. Participants (skilled street dancers and novice controls) were instructed to synchronize repetitive knee-bending movements in stance to a metronome beat over wide range of movement frequencies in two coordination modes: down-on-the-beat (knee flexion synchronized with the beat) and up-on-the-beat (knee extension synchronized with the beat). When they were instructed to perform up-on-the-beat, both groups showed unintentional phase transition to down-on-the-beat at higher movement frequencies. In contrast, when they were instructed to perform down-on-the-beat, phase transition to up-on-the-beat was never observed. The critical frequency where phase transition from up-on-the-beat to down-on-the-beat was significantly higher in dancers than in non-dancers. In addition, when the participants were instructed to resist the unintentional phase transition, only dancers were able to do it. These findings suggest that rhythmic whole-body sensorimotor synchronization obeys principles of self-organization, and that skilled dancers were able to modify such pre-existing tendencies to achieve artistic expressions.
第151回 11月9日(月) 16:30より 所沢キャンパス 100号館5F 第一会議室
演題1
パラリンピックとスポーツ医科学
演者
河合純一先生(日本スポーツ振興センター・スポーツ開発事業推進部)
内容
パラリンピックの歴史、現状、未来についてスポーツ医科学の視点から述べる。パラリンピックは障碍者のリハビリテーションとして誕生した。しかし、現在では競技スポーツとしてのパラリンピックを生み出した。とはいえ、障碍者にとってのリハビリテーションがなくなるわけではない。まだ、解明されていない様々な研究分野があることを紹介する。また、パラリンピック大会においては、競技性と平等性を両立させるためのクラス分けというものがある。この方法についても、日夜研究が続けられている。障害種ごと、競技ごとの違いを説明し、理解を深めたい。さらに競技用具を使用する競技も多く存在している。材料工学、人間工学の立場からの貢献策をお伝えする。そして、2020東京パラリンピックに対し、スポーツ医科学は何ができるのかを共に考える機会とするため、現在実施されているスポーツ医科学サポートについて触れる。そのことを通じて、早稲田大学のスポーツ医科学は、これからどのようにしてパラリンピックと関わり、社会に貢献していくのか、その方向性を提示したい。
第150回 9月16日(水) 17:00より
演題
The Paralympic Athlete– Common Performance Issues
演者
Prof. Vicky Goosey-Tolfrey(Loughborough University, UK)
内容
It is well known that ‘Paralympic Sports’ evolved from medical rehabilitation programmes since the 1950s (McCann, 1996). Burkett (2010) provides a nice review of how technology helps the rehabilitation practitioner to regain a level of function for their client; for an athlete with a disability, the highest expression of this return to function is to compete at an elite level in the Paralympic Games. The Paralympic Games provides sporting opportunities for athletes with many types of disabilities with differing levels of impairment. Without a thorough understanding of the physiological consequences or medical issues of the specific impairment groups then the sports practitioner faces an extremely complex challenge with the implementation of effective sport medicine and applied sports science support. At the 2012 Paralympic Games in London a large injury and illness survey was undertaken as a collaborative project between nations. It appears that the injury and illness rates in Paralympic athletes are similar to those in other events in able-bodied sports, but patterns of injuries and illness are different. Upper limb injuries (35%), particularly of the shoulder (17%) were most common which is most likely due to many athletes requiring a wheelchair for either daily ambulation or their sporting performance. Higher injury rates were found in older athletes and certain sports like Visually Impaired Football-5-a-side (22.4/1000). The incidence rate of illness was also reported and this was found to be highest in the respiratory system, skin, gastrointestinal and genitourinary system. As the Paralympic Games include a wide array of sporting classifications it is beyond the scope of this presentation to cover all disabilities. Therefore this presentation will focus on what the findings of this aforementioned injury and illness survey mean for the training practices of wheelchair athletes and to discuss current research on the thematic topics: i) the travelling athlete; and ii) nutritional and body composition assessment considerations for the Paralympic athlete.
第149回 7月20日(月) 16:30より 所沢キャンパス 100号館5F 第一会議室
演題1
健康づくりのために必要な身体活動・体力とその評価
演者
川上 諒子 先生(早稲田大学スポーツ科学学術院 助手)
内容
我が国では、2013年3月に厚生労働省より「健康づくりのための身体活動基準2013」が策定された。「健康づくりのための身体活動基準2013」では、生活習慣病や運動器障害、死亡などのアウトカムと身体活動や体力との関連について検討した前向きコホート研究のメタ解析の結果に基づき、健康づくりのために必要な身体活動・体力の基準が示されている。しかしながら、基準策定に使用された研究は、欧米の研究が中心となっており、日本人を対象とした研究はわずかであった。また、これらの基準は様々なアウトカムとの関連を検討した研究を1つに統合することで策定されているが、実際に各疾患とどのような関係にあるのかについては明確になっておらず、基準の妥当性を検証していく必要がある。一方で、国民1人1人が基準の達成状況を把握するために、自身の身体活動や体力を簡便に評価できる方法を提案することも重要である。本研究会では、これまでに我々のグループで行ってきた健康づくりのために必要な身体活動・体力に関する研究成果を紹介するとともに、身体活動や体力の簡易評価法に関する知見も紹介する。
演題2
ポピュレーションレベルの身体活動促進を目指した取り組みと今後の課題
演者
松下 宗洋 先生(早稲田大学スポーツ科学学術院 助手)
内容
身体活動は非感染性疾患や介護予防の効果が期待されている。しかし、我が国の成人における身体活動は過去10年間低下傾向にある。したがって、我が国の健康増進において、ポピュレーションレベル(地域集団など)の身体活動促進は公衆衛生上の課題の一つである。今までに行われてきた身体活動促進プログラムは、教室型運動指導に代表される個人から数十人を対象とした個人レベルのプログラムである。しかし、この個人レベルの身体活動促進プログラムを集団レベルの身体活動促進に活用するには、集団全体に対するインパクトが少ない等の課題が指摘されている。したがって、ポピュレーションレベルの身体活動促進には、個人レベルのプログラムだけではなく、集団レベルのプログラム(例:歩きやすい環境の整備など)を複数組み合わせた戦略の構築が重要である。これまでに発表者は、インセンティブ制度や運動環境整備を中心としたポピュレーションレベルの身体活動促進を目指す取り組みの効果検証を行ってきた。そこで本研究会では、その効果検証の結果や今後の課題について紹介したい。
第148回 6月1日(月)16:30より 所沢キャンパス 100号館 5F 第一会議室
演題
「歩き方を変える」だけで10歳若返る! -生活習慣病・介護予防のための新しい運動処方システム
演者
能勢 博 先生 (信州大学医学系研究科・疾患予防医科学系専攻・スポーツ医科学講座)
内容
ヒトの体力は20歳代をピークとし、それ以降10歳加齢するごとに5-10%ずつ低下する。そして、体力が20歳代の30%以下にまで低下すると要介護状態となる。一方、この体力低下に比例して高血圧、高血糖、肥満などの生活習慣病が発症するのは興味深い。事実、加齢による体力低下と医療費の上昇は非常に良く相関する。そこで、我々は、インターネットを用いた遠隔型個別運動システムを開発し、6,000名以上の中高年者を対象に「インターバル速歩」による体力向上が生活習慣病に与える効果を検証した。その結果、5ヶ月のトレーニングによって体力が10%増加し、生活習慣病の症状が20%増加し、慢性関節痛・うつ指標が50%改善し、医療費が20% 削減された。さらに、炎症促進遺伝子のメチル化を測定したところトレーニング後にメチル化が亢進し、それらの遺伝子活性が抑制されていることが明らかとなった。以上、体力維持・向上こそが生活習慣病・要介護の予防と治療に最善の方法であることを述べる。
第147回 5月20日(水)17:00より 所沢キャンパス 100号館 210教室
演題
心と身体を繋ぐ神経基盤
演者
西村 幸男 先生(生理学研究所・認知行動発達機構研究部門)
内容
スポーツ選手は類い希な身体機能だけでなく、同様に不屈の闘志を兼ね備えているが、その闘志と運動パフォーマンスを説明する脳内メカニズムについては未だ不明なところが多い。また、脳損傷後には運動麻痺と同時にうつ症状を併発し、そのうつ症状を軽減し、意欲をあげることで運動機能回復を促進しうることが経験的に知られている。我々は、このような心の奥底から沸き立つ闘志・意欲とそれにより制御される身体運動制御の神経基盤・心と身体運動制御機構の因果関係を解明することを目指している。それを達成するために、中脳辺縁系を生体全体・精神状態の維持・制御可能な起源であると仮説を立て、中脳辺縁系の神経活動の操作とそれに支配されている大脳皮質活動、行動を一度に観察することで、それぞれの機能的連関・因果関係を神経生理的・計算論的に検討した、我々の最新の研究結果を紹介する。
第146回 4月24日(金)16:00より 所沢キャンパス 100号館 5F 第一会議室
演題
The Influence of Binocular Vision on Sensomotor Learning Process
演者
Mgr. Václav Salcman, Ph.D.(University of West Bohemia, Czech Republic)
内容
The goal of the study is to identify a possible descriptively associative relation between sensomotor learning process and the quality of binocular vision. Realized on a homogeneous sample of students in sports, the research file was extended up to 72 probands, when compared with the pilot study (2012). To investigate the level of visual functions (single binocular vision), we used the troposcope, to determinate the level of sensomotor learning process we used the mirror drawing test. Following statistical processing of the gained data confirmed the significance of the relationship between visual functions and motor learning process is medium (rs = 0.31). After processing the collected data, a statistically significant relationship between the studied variables was ascertained. These operations were done using the software called Statistica 8.0. With regard to the limited sample size, this research cannot be generalized, and its results are considered to be valid in a group of students of physical education and sports at the age of 21 to 26 years.
Keywords: sensomotor learning, visual functions, neuromuscular co-ordination, mirror drawing, simple binocular vision, and stereopsis.
- Tags
- 研究活動